実は、「老いた水牛は若草を食べる」という言葉は、もっと広い意味を持ち、海外在住のベトナム人男性だけでなく、若い女性を好む年配の男性を指しています。このことわざは「老人は太鼓を叩く」という言い回しに似ています。太鼓は紙でできた太鼓であり、子供にとっては単なるおもちゃであるため、「老人は年齢にふさわしくないものを欲しがる」という意味です。
起源から言うと、「老いた水牛が若い草を食べる」ということわざは、1980年代から1990年代に現れたものではなく、はるか昔の中国の蘇東坡の時代、つまり11世紀から12世紀に遡ります。
「老牛吃嫩草」は、宋代の蘇東坡の詩「老牛吃嫩草」を翻訳したもので、「老牛が若草を食べる」という意味です。(ちなみに、昔は牛を水牛だと思っていた人が多かったのですが、実は牛は牛、水牛は水牛です。)
張仙は著名な詩人で、蘇東坡の友人でもありました。ある日、張仙(80歳)は蘇東坡を妾の結婚披露宴に招きましたが、花嫁がまだ18歳であることを告げませんでした。到着した蘇東坡は、「老人が若い娘を娶る」という光景に驚きました。友人の意図を理解した張仙は微笑み、すぐに4行の詩を読み上げました。「私は80歳、あなたは18歳、あなたは美しい女性、私は白い髪。あなたに夢中、私たちは同い年、たった60歳しか違わない」。
「老牛が若草を食む」場面で張仙が満足げな様子を見せるのを見て、蘇東坡は彼を嘲笑した。「花嫁は18歳、花婿は80歳、白い髪に赤い宝石、夜はオシドリが布団に閉じ込められ、梨の花が芙蓉を押さえている」。蘇東坡は「一树梨花压海棠」という文章を作った時、張仙が「梨の木」、花嫁が「芙蓉を押さえている」という意味を込めていた。梨の花が芙蓉を押さえているということは、「老牛が若草を食む」ということを意味する。それ以来、「老牛腎吃草」という表現は中国全土に広まり、後に台湾教育部の客家常用辞典にも収録された。
英語にも、 「老牛が若草を食べる」や「老牛が若草を食べる」というフレーズに対応する慣用句があります。例えば、「五月十九日ロマンス」「五月十九日の関係」などです。「五月」は若い女性、「十月」は老人を指します。「五月十九日ロマンス」という用語は、中世のジェフリー・チョーサーの『カンタベリー物語』に由来すると考えられています。この言葉は単に「五月十九日」や「揺りかごを奪う」とも呼ばれ、自分より年下の人と結婚したり関係を持ったりすることを意味します。
一方、年上の女性が若い男性と浮気をしたり結婚したりすることを「老婆機操縦士(おばあちゃんのかんとう)」といいます。これはベトナム語で「操縦士(若い男性)」、老婆機操縦士(おばあちゃんのかんとう)」という意味の比喩表現です。広東語にもこのことを表す慣用句があります。 「煲老藕(ぼうろうんぐう、bou1 lou5 ngau5)」は「古いレンコンを茹でる」という意味で、「年老いた妻が若い夫と結婚する」という意味です。
[広告2]
ソースリンク



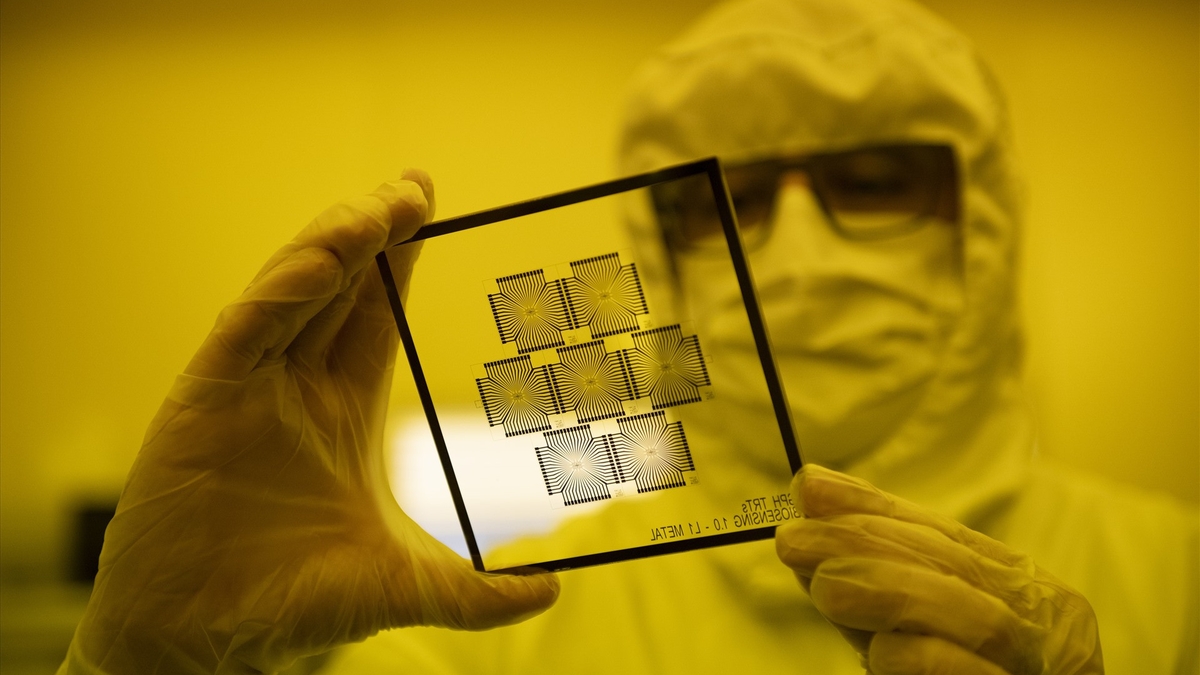
![[写真] ダナン:数百人が嵐13号後の重要な観光ルートの清掃に協力](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/07/1762491638903_image-3-1353-jpg.webp)

































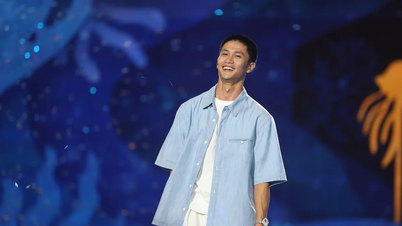


























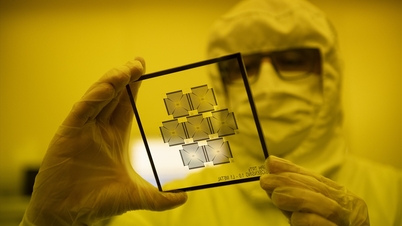




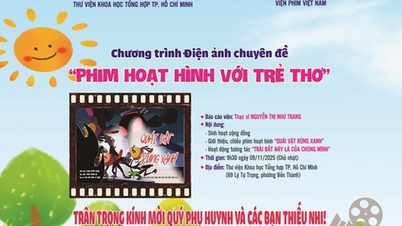






























コメント (0)