任意加入社会保険加入者の給付金を増額
チャビン代表団のタック・フオック・ビン氏は、社会保険法案(改正版)の3つの視点、5つの目標、11の主要内容に賛同し、この法案には、社会年金給付の追加や受給年齢を80歳から75歳に引き下げる規定など、中央委員会決議第28号に忠実に従い、画期的な規定が数多く含まれていると指摘した。ビン代表は、年金受給年齢を段階的に引き下げていくためのロードマップを策定する必要があると述べた。
法案に規定されている任意の社会保険支援政策に関して、代表は有権者との接触を通じて、国民が本当に望んでいるのは、任意の社会保険だけでなく、社会保険加入者全般を国が支援することだということがわかったと述べた。
代表らはまた、法案起草機関がなぜ児童保険を法案に含めなかったのかと疑問を呈した。
ヴォー・マイン・ソン代表( タインホア代表団)は、社会保険料の最低年数を15年に短縮する方向で年金条件を調整するという提案には同意する一方で、年金水準は保険料納付期間と保険料支払いの基準となる給与・所得水準に基づいて算出されるため、社会保険料納付期間の条件を緩和すると、非常に低い年金で退職する労働者が増えることになると述べた。同時に、社会保険法改正案では最低年金水準の規制が削除された。同代表は、これは多くの労働者が懸念していることであり、彼らは年金が低すぎると生活を保障する最低水準がないのではないかと心配していると述べた。

国会議員らがグループで社会保険法案(改正)について議論(写真:マイン・ズン)
労働・傷病兵・社会省社会保険局長のファム・チュオン・ザン氏は、社会保険法案についてさらに説明し、グループ代表者からの質問に答える中で、今回の法改正の目的の一つは社会保険の適用範囲を拡大することだと述べた。国際的な経験によれば、社会保険の適用範囲を拡大するには、強制社会保険と任意社会保険という二つの形態を調和的に組み合わせる必要がある。
「強制社会保険に加入している人々に加え、非公式セクターの労働者にとって社会保険への加入はより困難です。政府は彼らが任意の社会保険に加入できるよう支援する必要があります」とジャン氏は述べた。
社会保険局長は、任意の社会保険に適用される22%の給与拠出率に関して、これは強制社会保険に加入している労働者グループに対応するように設計された率であると説明した。
任意社会保険加入者に対する出産補助金(1出産あたり200万ドン)について、ザン氏は、この制度を利用するには社会保険加入者が拠出金を支払わなければならない一方、任意社会保険加入者に適用される200万ドンという額は拠出金不要の支援金であると述べた。国が任意社会保険加入者に対して多くの支援制度を設けている理由は、一般調査によると任意社会保険加入者の70%が貧困ラインに近いためである。拠出金水準がさらに引き上げられると、彼らは貧困ラインに陥る可能性がある。そのため、この支援付き出産補助制度は、労働者が任意社会保険に加入することを奨励するためのものである。
法案草案によって年金受給額が低下するとの意見に対し、社会保険局長は、2016年から2022年の間に、20年間の保険料納付期間がないため、30万人の労働者が社会保険から脱退したと述べた。保険料納付期間の短縮により、これらの労働者層に年金受給の機会が与えられる。低賃金でも、月額36万ドンの補助金しか受け取れない無年金よりはましだが。これらの労働者は、年金受給に加えて、老後の健康管理のための健康保険にも加入している。
社会年金受給年齢について、労働・傷病兵・社会問題大臣のダオ・ゴック・ズン氏は、ロードマップによれば、まず80歳から75歳に引き下げられ、その後、さらに引き下げるためのロードマップが策定されると述べた。給付額については、政府は各時期の社会経済状況に応じて柔軟な規定を設けることを提案している。ダオ・ゴック・ズン大臣によると、受給額は法律で「厳密に規定」されているわけではなく、政令で示されるため、政府はバランスと調和を確保しながら積極的に管理できるという。
児童保険が法案に含まれていないという意見に対し、大臣は、国には現在、児童に特化した支援策が数多くあると述べた。政府は法案にそれらを盛り込んでいないものの、現時点では児童を支援するためのあらゆる政策は保障されている。

ダオ・ゴック・ズン大臣がグループ討論会で社会保険法案(改正)に関する国会議員の意見を聞いている(写真:マイン・ズン)
社会保険給付を一度に2つ受け取る選択肢に対する懸念
グループディスカッションセッションで代表者から最も注目を集めた問題の一つは、政府が提案した2つの一時的な社会保険給付プランでした。
社会保険の一時給付金の受給問題について、ディエンビエン代表団のタ・ティ・イエン氏は、社会保険加入者は失業したらすぐにお金を引き出して緊急の経済的ニーズを解決したいと望んでいるが、政府は労働者、特に就労年齢を過ぎて高齢で体が弱り収入がなくなった労働者に長期的な保護を提供したいと考えており、彼らが家族や社会の経済的負担になることを望んでいないと述べた。
タ・ティ・イエン氏によると、社会保険料の支払いは実際には老齢年金であり、健康保険に連動しており、健康保険は均等に支払われ、納付年数や社会保険給付の水準には左右されない。健康保険の社会保障の適用範囲拡大を目指し、社会保険を一度脱退した人も引き続き国から保障される。したがって、同代表は、すべての人々に長期的で持続可能な社会保障を保証するという選択肢2に傾いていると述べた。なぜなら、決議28では、社会保険に加入して退職給付を享受する期間を予約する場合は給付を増やす方向で、また一度社会保険を受給する場合は給付を減らす方向で、社会保険を一度脱退する状況を減らすための適切な規制があることも明記されているからである。

タ・ティ・イェン代表 (ディエンビエン代表団)
一方、選択肢2を支持するトラン・ティ・ニ・ハ代表(ハノイ代表団)は、社会保険料の引出率を50%ではなく、従業員の保険料負担率に合わせるべきだと提案した。これにより、従業員は拠出した金額のみを引き出すことができる。雇用主が拠出した金額は、将来、年金の一部を支給するために留保される。
社会保険料の引出額に関して、ホー・ドゥック・フック財務大臣によると、オプション2では従業員が50%を引出し、残りの50%を保有できるとのことです。しかし、50%の引出額の基準はどこにあるのでしょうか。これは、拠出能力と引出能力に基づいて決定する必要があるからです。
「企業が従業員のために拠出する部分は、従業員の所有物ではあるものの、年金受給のためには残しておき、後々も引き続き拠出する必要があります。例えば、社会保険基金の拠出金の構成は25.5%で、そのうち8%は従業員が拠出し、17.5%は企業が拠出します。18%のうち、3%は傷病・出産、0.5%は傷病・事故、14%は退職・死亡給付金です。ですから、企業が拠出する14%は従業員が長期保有できるように残し、残りの11.5%は従業員が希望すれば引き出せるようにすべきだと思います。そうすれば、約46%を引き出して54%を残すことになります」と財務大臣は見解を述べた。
[広告2]
ソースリンク





















































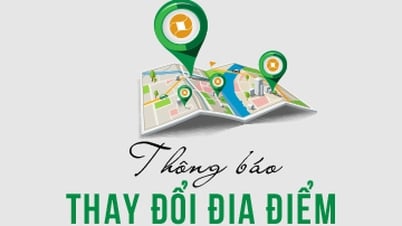
















































コメント (0)