
税務署の情報によると、企業家計の税額計算方法は、原則として直接納税方式を採用する企業と同様である。大きな違いは、中小企業が課税所得(経費を除く)に対して法人所得税を納税し、増値税を控除方式で納税し、会計制度(会計帳簿の開設、財務諸表、会計帳簿、会計書類の作成)を実施する点にある。
一方、規模を問わず、中小企業に相当する規模の事業所( 農林水産業、工業、建設業の分野で売上高が30億ドンを超える事業所、または貿易・サービス業の分野で売上高が100億ドンを超える事業所など)を含むすべての事業所は、収入に対する直接法で個人所得税、付加価値税を納税し、会計制度を実施しない(事業所は一括納税)か、または簡易会計制度を実施して単一帳簿を保管し、会計口座を開設したり財務諸表を作成したりする必要がない。
したがって、企業と事業家計の税制と税務行政には差異があります。現行の法政策体系は、事業家計と企業の間に相対的な差異を生み出しており、登記手続き、納税義務とインボイス、会計制度、そして専門的な管理規制といった面でその差異を反映しています。
具体的には、事業登録および税務登録については、事業世帯は地区/県財政計画事務所で登録します(2025年7月1日以降、事業世帯は本社所在地の町/区財政計画事務所で事業登録申請を提出し、結果を受け取ることができます)。必要書類は簡素(事業登録申請書、世帯主の身分証明書など)で、登録発行までの期間は3日です。一方、企業は省の事業登録事務所で登録します。必要書類はより複雑(事業登録申請書、定款、会員/株主名簿など)ですが、有効な場合は3日以内に処理されます。

税務登録に関しては、法律によりワンストップの仕組みが認められており、企業または企業世帯の登録時に税務情報が税務当局に伝達され、同時に税コードが発行されます。しかしながら、実際には、これまで(2023年7月1日以前、企業登録と税務登録の相互連携手続きが実施されていなかったため)、税務当局と企業登録の緊密な連携が欠如していたため、企業世帯の企業登録は完了しているものの、税務登録が完了していない状況が依然として存在しています。
会計・インボイス制度については、企業(小規模企業を含む)は規定に従って会計制度を実施し、すべての販売・サービス取引(一部の特別なケースを除く)について電子インボイスを使用する必要があります。一方、ほとんどの事業所(一括納税団体)は会計帳簿を保管する必要はなく、税務当局の判断のために収入を申告するだけで済みます。インボイスが必要な場合は、税務当局が個別に発行します。申告した事業所のみが電子インボイスを定期的に使用し、企業と同様に収入と費用を完全に記録します。
この違いにより、企業に比べて事業所の収入と支出の透明性がはるかに低くなり、税務管理が困難になるとともに、一部の事業所が収入を低く申告して納税額を減らす抜け穴が生じることになります。
税額計算方法について、税務署は、企業は控除方式(所得税と控除可能な付加価値税を計算)または収益に対する直接方式を選択できると述べた。企業家は基本的に収益(契約または直接申告)に対して税額を計算しており、事業モデルに転換しない限り、法人所得税のように経費を控除した所得に基づいて計算する個人所得税の仕組みはない。
この違いにより、企業は税額計算において合理的な経費を控除できるのに対し、事業所世帯は収入に対して定率で税金を納めるため、実際の税率は低くなりますが、コスト要因が考慮されていないという問題が生じています。事業所世帯の事業拡大を促すため、個人所得税の計算において経費控除を認めることや、大規模事業所世帯の個人所得税率を法人所得税率に近づけることが必要であるという意見が多くあります。
その他の義務や管理に関しては、税務署は従業員の社会保険、防火、労働安全、偽造請求書や偽造書類の防止などに関して企業に厳しい管理を課していますが、事業所はこれらの義務について十分に検査・確認されていないことがよくあります。
一方、一部の優遇・支援制度は企業のみに適用され、事業所には適用されません(例:中小企業向け法人税の優遇措置、金利支援、事業所の立地など)。この違いは、多くの事業所が、税負担(一時金の低額化)や検査・制約の少なさといった点で事業所モデルの方が有利であると考え、企業への転換を望まないという心理につながっています。
一般的に、現行の法制度は、事業内容や規模ではなく、法人格に基づいて事業家計と企業を区別しており、両者の公平性を欠く状況となっています。このことが、意図せずして事業家計による事業運営が企業設立よりも有利な状況を生み出し、多くの事業家が企業への転換を躊躇する障壁となっています。したがって、本プロジェクトの重要な課題の一つは、国際慣行に則り、納税義務や経営体制の面で企業と同様の方向で事業家計を運営していくよう、事業家計と企業間の政策格差を徐々に縮小していくことです。
世界では、ベトナムのような「事業世帯」という別個の概念を持たない国が多数ありますが、個人事業の類似モデルは存在します。個人事業は、個人が所有し、無制限の責任を負い、利益が所有者の課税所得に含まれる形態で、通常、個人事業、事業世帯、個人事業の 3 つの実体で構成されます。
これらの国では、個人事業主は登録手続きが簡単で、費用が低く、法人所得税ではなく個人所得税が課されることが多いです。
税務行政に関しては、多くの国では、小規模事業者は法人を設立することなく、個人納税者コードで事業を営むことが認められています。しかし、売上高や従業員数が一定額を超える場合は、事業登録を行うか、事業者として会計・税務申告制度への準拠が求められます。多くの国では、小規模事業者に対して、事務負担を軽減するため、一括納税や簡易課税制度を適用していますが、規模が大きい場合は、帳簿申告に切り替える仕組みが常に用意されています。
税務局の調査によると、現在中国にはベトナムと同様に、個人企業と企業家(個人企業家と小規模企業家)が存在している。しかし、これらの主体にはそれぞれ独自の奨励政策と規制があり、個人企業は個人企業法で、企業家は民法で規制されている。
シンガポール、マレーシア、タイでは、個人事業の登録は容易で、個人所得税を支払うことができます。しかし、タイでは、収益が一定額を超える場合は法人を設立する必要があります。
一部の国では、家計経営の企業化を支援する措置も実施されています。韓国と日本では、家計経営が企業化してから最初の数年間は税金を免除または減税する政策が実施されています。中国では、新たに企業化した家計に対して営業免許税を免除し、個人所得税を減額しています。インドネシアでは、家計の企業登録を促進するため、小規模事業者の税務申告を簡素化しています。
さらに、各国は、事業者が税金を申告・納付するのに便利な電子納税システムの構築に注力しており、複数のソース(銀行、電子請求書、POS端末など)からのデータを統合して事業者の家計収入を監視し、収入の損失を防いでいます。
国際的な経験から、一般的な傾向として、手続きや税率の面で事業世帯に最大限の条件を整える一方で、平等性を確保し、税務管理の効率性を高めるために、大規模世帯が十分な規模に達した時点で正式な企業枠組みに組み入れるロードマップを用意することが挙げられます。
ベトナムにおける家計経営体の割合は、他国と比較して依然として低い水準にあります(人口の約2.17%、米国は約6.9%、タイは約5.6%、英国は約8.5%など)。これは、起業や事業拡大を促進する適切な支援政策があれば、個人経営の発展や企業化の余地が依然として大きいことを示しています。
出典: https://nhandan.vn/kinh-nghiem-quoc-te-ve-quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-post915007.html


























![[ビデオ] 第18回ハノイ党大会プレスセンターの開設](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/14/1760428755332_img-1843-9688-png.webp)
















































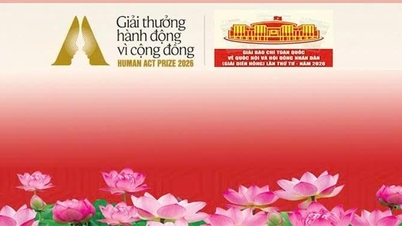
























コメント (0)