ベトナム石油総公社(PVOIL)は、2026年初頭からのベトナムにおけるバイオ燃料の義務的使用に関する政府の新たなロードマップの実施に備えて、2025年8月1日からハノイ、ハイフォン、ホーチミン市のガソリンスタンドでE10バイオ燃料の販売を試験的に開始する。
世界において、バイオ燃料への移行は、多くの国にとって環境、 経済、そしてエネルギー安全保障の観点から大きな意義を持っています。各国の政策、技術、生産能力、そして持続可能な開発目標の違いに応じて、バイオ燃料への移行に向けた独自のロードマップが策定されています。
ブラジル
ブラジルはバイオ燃料、特にサトウキビ由来のエタノールの開発と利用において世界をリードしています。ブラジルのバイオ燃料への移行は、技術的な側面だけでなく、エネルギー安全保障、 農業開発、そして温室効果ガス削減に向けた長期的な戦略を反映しています。1973年の石油危機を受けて、ブラジル政府は1975年にプロアルクール計画を開始し、輸入ガソリンの一部を国産バイオエタノールに置き換えることを目指しました。
当初、このプログラムは補助金、信用供与、ブレンド・流通インフラへの投資を通じて砂糖産業を支援することに重点を置いていました。恵まれた自然条件、高いサトウキビ収量、そして効率的な技術プロセスのおかげで、ブラジルは急速に成長し、米国に次ぐ世界第2位のエタノール生産国となりました。

米国のトウモロコシ由来エタノールとは異なり、ブラジルのサトウキビ由来エタノールはエネルギー変換効率が高く、二酸化炭素排出量が少ない。これは、ブラジルが化石燃料への依存を減らし、輸送に伴うCO₂排出量を削減するという二つの目標を達成する上で役立つ。
ブラジルの経済発展における重要な転換点は、2000年代初頭以降の「フレックス燃料車」の普及です。これらの車は、従来のガソリン、純エタノール、あるいはその両方の混合燃料で走行できます。現在までに、ブラジルで販売される新車の90%以上がフレックス燃料車です。これにより、消費者は市場価格に基づいて燃料を選択できる柔軟性が得られ、エタノールが国内輸送燃料市場の40%以上を占めています。さらに、政府は市販ガソリン(E27)に最低27%のエタノールを混合することを義務付けており、これは世界でも最も高い比率の一つです。
ブラジルは国内需要への対応に加え、特に欧州およびアジア市場へのバイオエタノールの主要輸出国でもあります。同時に、持続可能性の向上と耕作地への負荷軽減のため、バガスと稲わらを原料とする第二世代バイオ燃料への多額の投資を行っています。そのため、ブラジルのバイオ燃料移行ロードマップは、一貫した政策、強固なインフラ、技術革新、そして国内市場からの高い受容性を兼ね備えた包括的なモデルとみなされています。
インド
インドは、世界で最も積極的かつ野心的なバイオ燃料移行ロードマップを推進する国の一つとして台頭しています。14億人を超える人口と燃料需要の増大を背景に、政府はバイオ燃料を環境問題の解決策としてだけでなく、経済・エネルギー戦略の重要な手段と捉えています。インドは2003年以来、エタノール混合ガソリン(EBP)プログラムに基づき、ガソリンにエタノールを混合してきました。しかし、このプログラムが本格的に本格化したのは、ナレンドラ・モディ首相率いる政府が野心的な再生可能エネルギー目標を掲げた2014年になってからでした。
インド政府は2021年、当初の計画より5年早い2025年までにガソリンへのエタノール混合率20%(E20)を達成する計画を発表しました。この目標は、国内の燃料需要の約85%を占める石油輸入を削減し、国内農業部門の安定した生産市場を創出するという総合戦略の一環です。政府は補助金、優遇融資、エタノールに対する物品税免除など、一連の支援政策を実施し、国営石油会社に対し、2023年から主要都市でE20ガソリンの販売を義務付けました。

この移行は、燃料混合インフラの急速な発展と、E20適合車両の大量生産・登録によって支えられています。さらにインドは、食料源との競合を回避し、温室効果ガス排出量をより効果的に削減するため、第一世代のサトウキビ、トウモロコシ、キャッサバの代わりに、稲わらや農業廃棄物から作られる第二世代バイオ燃料への投資を進めています。
長期的なビジョンを掲げるインドのバイオ燃料への移行は、単なる技術的な措置ではなく、クリーンで自立的かつ持続可能なエネルギー経済の構築に向けた戦略的な一歩でもあります。世界が急速にグリーンエネルギー源への移行を進める中、インドはますます先駆者としての役割を担っています。
中国
世界最大のエネルギー消費国である中国は、大気汚染の削減とエネルギー安全保障の強化戦略の一環として、バイオ燃料に大きな期待を寄せています。中国では、ガソリンにエタノールを混合した燃料の使用が2000年代初頭に正式に開始され、吉林省、遼寧省、河南省などの一部の省では、E10バイオ燃料(エタノール10%)の導入が先駆的でした。2017年、北京市は2020年までにE10を全国で義務化するという野心的な計画を発表しました。この目標は、数千万トンに上る膨大なトウモロコシ在庫を処理する必要性と、深刻化する都市環境汚染を削減するというコミットメントによって支えられました。
しかし、この移行ロードマップの実現プロセスはすぐに大きな課題に直面しました。10以上の省・市で初期段階の実施段階を経た後、E10の全国展開は停止されました。主な理由は、バイオ燃料と食料資源の競合に対する懸念です。中国は人口の多い国であり、特に気候変動、疫病、そして世界のサプライチェーンに影響を与える地政学的不安定性という状況において、常に食料安全保障を最優先しています。トウモロコシ、小麦、キャッサバを原料としたエタノール生産は、特に食料価格が急騰する傾向がある状況では、長期的には持続不可能と考えられています。

同時に、中国政府は電気自動車や水素などの再生可能エネルギーの開発に重点を移しました。これにより、バイオ燃料はグリーンエネルギー戦略の焦点から外れました。しかし、広東省、山東省、河南省などの一部の地域では、特に公共車両や公共交通機関向けの試験プログラムにおいて、E10ガソリンが依然として使用されています。
中国はまた、食用作物への依存を減らすために、わらや農業廃棄物を利用する第二世代バイオ燃料技術にも投資している。
中国のバイオ燃料への移行は計画通りには進んでいないものの、同国が初期段階から着手したことは、将来のエネルギー転換に向けた重要な基盤を築くものとなった。今後、原材料と技術の問題が解決されれば、バイオ燃料は依然として中国の多様化と低炭素化に向けたエネルギー政策を支える役割を果たす可能性がある。
出典: https://khoahocdoisong.vn/lo-trinh-chuyen-doi-sang-xang-sinh-hoc-post2149044045.html









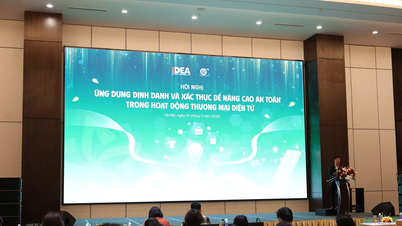



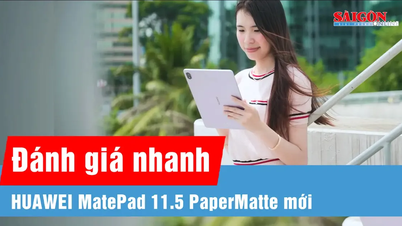







![[インフォグラフィック] ハティン省の寺院で珍しい山ガメが発見される](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/01/1761959604793_thumb-rua-nui-vien-jpg.webp)



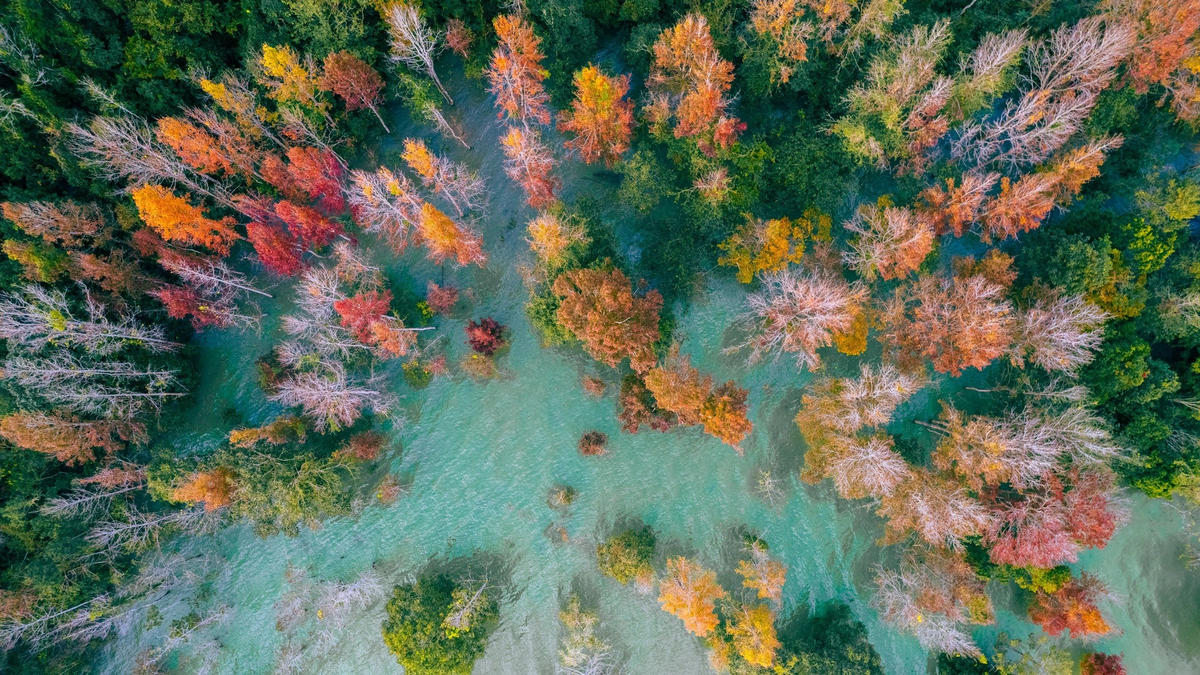




























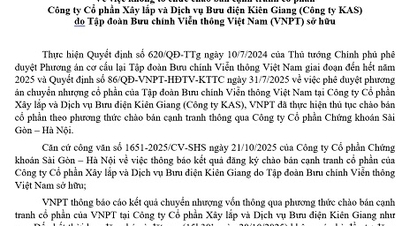

















































コメント (0)