ロイさんはタンチャウ省スオイデイ村の庭で竹を切っている。
長期的な愛着
グエン・ヒュー・ドゥックさん(56歳)は、自分の家族が最初に竹箸作りを始めた家族の一つであり、その後、安定した収入源を得るために近隣の他の家族と仕事を分担したと語った。
ドゥック氏によると、当時は仕事があまりなく、近所のどの家も家の周りに丈夫な竹を植えていたため、両親は竹箸を作って売ろうと思いついたそうです。当初、竹箸は柄の長さが約30センチ、刃の長さが20センチと非常に重く、手に持つには重すぎたため、家族で新しい削り跡をつけました。最初は金ノコの刃で跡をつけ、父親が手で研いで丸い凹みを作り、竹箸を丸く均一な形に仕上げました。
その後、市場の布屋で薄くて鋭い布切り刃があることを知り、両親はそれを買い、箸のラベルを研いで近所の箸屋に売るようになりました。小さくて鋭い手研ぎのラベルのおかげで、毎日削られる箸の数は以前よりも増え、より美しくなりました。
ドゥック氏によると、最近は近所の人たちがペーパーカッターで作った刃を好んで使っているそうです。この2種類の刃は非常に耐久性があり、摩耗するとドゥック氏のところに持ち込まれ、古い刃に新しい刃を取り付けて研いでもらいます。1枚の刃で4枚の刃を研ぐことができ、現在は刃の巻き取り機も設置して研ぎを補助しています。研ぎの料金は、1回につき1枚3,000ドンです。
チュオン・フオック村で長年竹箸職人として働くトラン・タン・チョンさん(49歳)は、生まれたときから両親がこの仕事をしているのを見てきたと語ります。両親から、近所の竹箸職人は高収入だと聞き、その仕事を学び、現在に至っています。
当時、どの家も家の周りには丈夫な竹林が生い茂っていました。箸を作るために竹を切り尽くすと、人々は別の集落へ買いに行かなければなりませんでした。チュオン・フオック集落が都市化されて道路が拡張されると、各家庭が土地を売却し、竹を切り出して家を建てるようになりました。そのため、今では集落には以前のように丈夫な竹が生えている家は少なくなっています。
ダックさんは箸研ぎ器を使ってさらに多くの箸を研ぎました。
今では、広大な土地を持つ地域では、竹林でタケノコを栽培する人が増えており、箸の原料となる竹は以前よりもはるかに豊富になっています。チョンさんの家族は主に、既製の竹を購入して箸を作っています。長年この仕事に携わってきたチョンさんは、どの竹がタケノコを売るために庭で栽培された竹で、どの竹が自然に生えた竹なのかを容易に見分けることができます。
自然に育った竹は、通常、肥料や水を与えません。古くなった竹は、幹に白い斑点が多く、芯の部分はタケノコ用に育った竹よりも黒っぽくなります。表皮を削るたびに黒っぽい部分が現れ、箸に美しい表情を与えます。竹が古ければ古いほど、箸は美しくなります。十分な日光に当てれば、箸は色づき、丈夫で美しく、カビが生えたりシロアリに食われたりすることもありません。
現代社会において、近隣地域では時間と労力を節約するために機械で箸が作られており、生産量も伝統的な竹箸よりも多い。チョン氏はこう語る。「機械で削られた竹箸は、手書きの箸ほど美しくありません。箸を削る際、職人は竹の樹齢に応じて、次の層が美しく見えるように、表層を削る力加減を調整する必要があるからです。しかし、機械は事前にプログラムされているため、どんな竹でも同じ動作を同じ力で行うことができます。」
キャリアの浮き沈み
村落の人々は長年にわたり竹箸の商売に携わってきましたが、必ずしも良い収入をもたらしてきたわけではありません。村落の竹箸商売は、「箸を作っても誰も買ってくれない」という時期もありました。チュオン・フオック村の多くの人々は、商売をやめて工場や企業に就職しました。
グエン・タン・ロイさん(62歳)も、この集落で長年箸職人として働く一人です。10歳の頃、父親の跡を継ぎ、家族のために竹を切り、箸を作っていました。21歳で結婚し、箸作りの仕事を始めました。当時は、箸の片方の端を色に浸して模様を描いたものが好まれ、箸一組ごとに絵付け職人に絵付けを依頼していました。
今では、消費者は昔の派手な色彩よりも、竹の素朴な見た目と香りを好むため、家族のパーティーで使うために大量に購入する人が多い。そのおかげで、彼の村の竹箸は省内の市場を席巻し、その後、西部諸州にも広まった。
商人の中にはカンボジアとの売買も行っている人もいます。2000年代、特に2014年にピークを迎えた時期には、箸の注文は豊富で、村では買い手と売り手が賑わっていました。それ以来、人々の生活は向上し、村で箸を作る世帯の数は日に日に増加しています。
トゥイさんは割った竹の細片を集めて束ね、お客さんが箸を作るのに使えるようにしています。
しかし近年、竹箸作りの事業は不安定になっています。箸は大量に生産されているものの、購入する人が少ないのです。多くの業者が価格を値下げしているため、収入が原価を賄えなくなっています。ロイさんは数ヶ月間箸作りを中断していましたが、その後仕事が恋しくなり、再び竹を仕入れて箸作りを始めました。
彼には4人の子供(男2人、女2人)がいますが、そのうち2人は竹箸作りをやめて工場で働き、1人の息子は鉄製品の購入に切り替え、40歳の娘だけが箸作りを続けています。家事を終えると、近所の人に買ってもらうために割り箸を作り、削って天日干しし、市場に持って行って売ったり、自分で買い手を探したりしています。
ロイ氏の娘、グエン・ティ・タン・トゥイさんは、「私は毎日2000本の割り箸を割っています(箸職人は1000本を1000膳と数えます)。普通の割り箸は1000本あたり18万ドン、古い割り箸は1000本あたり20万ドンで販売しています。近所の人たちに買ってもらい、削って乾燥させてもらっています。1000本の割り箸を乾燥させた後、束ねて1000本あたり50万~75万ドンで売っています。つまり、この仕事は利益を生むのですが、ここの高齢者たちは余暇に何をすればいいのか分からないのです」と語った。
ロイさんは、チュオン・フオック集落の多くの家族と同様に、現状の竹箸作りによる収入の不安定さに多くの懸念を抱いています。孫の世代が、先祖代々受け継いできた伝統的な竹箸作りの職業を守り続けられるのか、それとも永遠に失われ、「かつてはチュオン・フオック集落にも竹箸作りの村があった」という話だけしか聞けなくなるのか、彼には分かりません。
ゴック・ジャウ
ソース





![[写真] ホーチミン市は2025~2030年任期の第1回党大会前夜、国旗や花で華やかに彩られている](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760102923219_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-43-png.webp)




![[写真] 朝鮮労働党創立80周年記念パレードに書記長が出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760150039564_vna-potal-tong-bi-thu-du-le-duyet-binh-ky-niem-80-nam-thanh-lap-dang-lao-dong-trieu-tien-8331994-jpg.webp)























































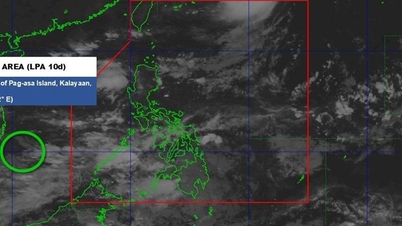



































コメント (0)