桜の国で大きな印象を残しているベトナムの企業があり、国際的な交流や会議でその名前が挙がると、私だけでなく多くの人が大変誇らしく感じます。
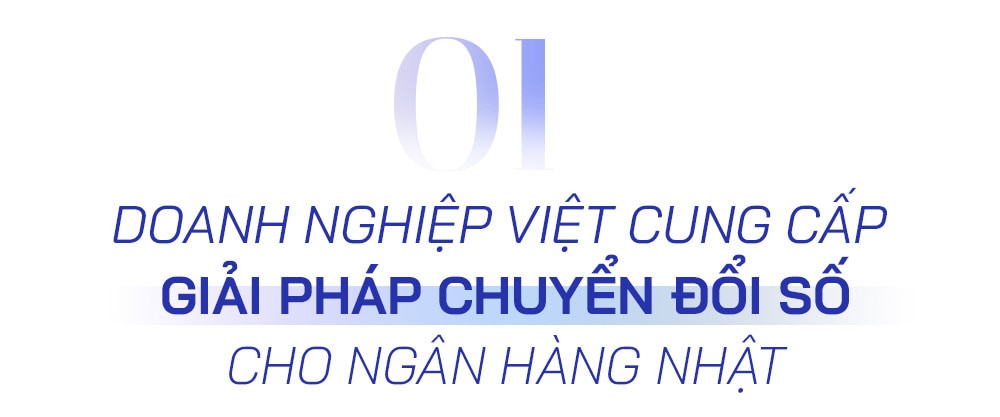
リッケイソフト社は2012年に設立され、主にグローバルセグメント(世界市場)に注力しています。 Rikkei CEO の Ta Son Tung 氏は、 ハノイ工科大学の元学生で、日本政府から奨学金を得て 3 年間日本に留学しました。

2016年にRikkei Softは日本に法人Rikkei Japanを設立し、2020年には大阪に支店を設立しました。現在、Rikkei Softはベトナムに4つの支店、日本に4つの支店(東京、大阪、福岡、名古屋)を持っています。
2023年5月現在、Rikkei Softの従業員数は1,600名を超え、そのうち100%が外国語を話し、94%が大学卒業、残りは大学院卒です。社員の43%が勤続年数3年未満であり、Rikkeiが近年急速に成長していることがわかります。
市場規模で見ると、Rikkei Soft は 500 社以上の法人顧客と 1,000 件以上のプロジェクトを抱えています。過去には日本市場が Rikkei の収益の 100% を占めていましたが、現在では日本は約 80% を占めるに過ぎません。残りは米国、シンガポール、タイ、オーストラリア、ニュージーランドなどの他の市場から来ています...
「Rikkeiは日本から世界へ」という理念のもと、2023年にはRikkei Japanはタイに支店を設立し、その後は韓国やその他の国にも支店を設立する予定です。この会社の見解は、日本のような先進国から来ることで他の市場へのアクセスが容易になるというものだ。

Rikkei Soft のエコシステムには、次のような多くのメンバー企業、製品、ソリューションが含まれています。Rikkei Digital は、デジタル変革と東南アジア市場に特化しています。立経アカデミーは、元留学生やインターン生が日本に帰国・在籍しITエンジニアとして活躍できるよう、日本語・IT研修を提供するとともに(日本留学経験のある留学生を中心に)、日本での留学生研修も行っており、1,000名を目標としています。 Rikkei Incubatorはスタートアップ企業に資金を提供します。 Rikkei AIはAIを活用したソリューションを提供します。 Rikkei IT Serviceはソフトウェアサービスを提供しています。
当社の調査によると、Rikkei Soft の強みの一つは、日本の銀行向けにデジタル変革ソリューションを提供していることです。出張中に私たちが驚いた発見の一つは、日本の銀行システムの多くがかなり昔に「古典的な」COBOL言語を使って構築されており、時代遅れになっていたということです。これらの 50 年以上前のシステムにはドキュメントがなく、プログラマーは亡くなっています。時間が経つにつれて、銀行データは非常に大きくなり機密性も高まるため、従来のシステムの負荷に対応できなくなります。そして今、これらの銀行はクラウドに移行する必要があります。
Rikkei は、情報技術に精通し、銀行業務をしっかりと理解している従業員のチームを構築します。このグループは、古い Cobol プログラム コマンドをそれぞれ読み取り、スキャンしてドキュメントを書き換え、開発チームに転送してプログラムをビルドし、クラウドに配置します。
これまでは中国企業によって行われていました。 Rikkei は金融分野での自社の発展のために、コードを書くだけでなく専門家のチームを構築することに尽力してきました。
かつては、中国のIT企業が日本への最大のアウトソーシングサービスプロバイダーでした。しかし現在、中国が支払う単価が日本より高いため、中国は日本市場から撤退し、中国市場に戻ってきています。
2023年には、日本在住のベトナム人の数が初めて中国人の数を上回る(47万人対44万人)。したがって、日本は、情報技術分野のベトナム企業にとって、中国企業が残したギャップを埋める絶好の機会である。
今問題となっているのは、人材不足という「問題」です。リッケイソフトの代表は私たちに対し、ベトナムの情報技術人材育成プログラムにODA資金を活用することを情報通信省が政府と協議し日本側に提案してほしいと希望を表明した。
日本政府は優秀なベトナム人学生が日本で学ぶことを支援する奨学金制度を設けています。 Rikkei Japan と NTQ Japan の創設者は、ハノイ工科大学の優秀な学生のために日本が後援する HEDSPI プログラム出身です。
Rikkei Soft のリーダーたちは、近い将来、ベトナム政府が日本政府にそのようなプログラムを再現するよう協議し、提案することを期待しています。
現実は、これが非常に優れたプログラムであることを証明しており、ベトナムの情報技術企業が日本のデジタル変革市場を開拓するための後押しとなるでしょう。

FPTジャパンは2005年に設立されました。現地企業と比較すると、FPTジャパンは競争力のある収入、サポートポリシー、従業員とその家族へのトレーニングの面で多くの利点を持っています。例えば、多くのベトナム人エンジニアが定期的に日本に仕事に行っている状況を踏まえ、FPTジャパンでは、社員が来日した際に滞在できる場所として、日本全国に合計600棟以上の寮を貸し出しています。落ち着いたり、家庭を持ったりすると、彼らは退去して他の従業員のために場所を空けます。
2023年初頭、フォーチュン誌の権威ある組織であるGreat Place To Work Institute Japanは、FPTジャパンを「働きがいのある会社トップ100」に選出しました。 FPTジャパンホールディングス、FPTソフトウェアジャパン、FPTテクノジャパンは、健康企業ゴールド認証を取得しました。

FPTジャパンは、大規模プロジェクトのためのリソースを準備するだけでなく、「Go Japan」「Enjoy Japan」、最近では「退職金」(失業給付)などの特別な政策を継続的に導入し、優秀な人材を惹きつけています。
FPTジャパンでは、オンラインコースを通じて各個人が日々成長し、基礎知識体系の補完や特定の目標達成までの時間の短縮に貢献しています。
FPTジャパンは2023年4月、東京に社員向け研修センターを開設し、70名の学生に同時に情報技術の研修を実施できる体制を整えました。同社の週末の日本語教室にも250人以上の社員が参加している。
社内研修制度に加え、FPTジャパンの日本語学校では現在、日本の専門学校への進学を目指して、ベトナム人学生150名に日本語を教えている。日本とベトナムに日本語教育を組み合わせたIT職業訓練校を開設することで、日本国内のベトナム人人材の活用と、ビザが切れて帰国したベトナム人人材の再利用を図ることが目的です。統計によると、約30万人のベトナム人が日本で様々な職業を学んでいますが、その多くは学業を終えても仕事がなく、帰国しなければなりません。
FPTジャパンのリーダーたちとの数回の議論や会議を通じて、私たちはこのビジネスを成功させる「秘訣」のいくつかを理解しました。
1つは「日本人を活用して日本市場へアプローチする」ことです。 2020年に従業員の大半が日本人であるFPTコンサルティングが設立されました。ベトナム人を雇用した場合、日本人のように言語、文化、ビジネスを理解するには何十年もかかるでしょう。そこで同社は、他社から日本人を採用することを決定した。
2つ目は、「Offshore」から「NearShore」および「BestShore」に切り替えることです。これまでFPTジャパンは日本国内にのみオフィスを開設し、業務を受注してベトナムへ移管し「オフショア」方式で業務を遂行してきました。しかし、最近日本では、海外に仕事を派遣せず、国内での仕事のみを割り当てるという方針になっています。この方針に対応するため、FPTジャパンはオフィスを日本の各都市にある支店に変更し、「オフショア」アプローチではなく「ニアショア」アプローチを導入しました。
2017年、FPTジャパンは初の「ニアショア」センターであるFPT沖縄&R&D株式会社を設立し、後にFPTニアショアに改名し、福岡と北海道にも支店を開設しました。 2023年6月には栃木県と静岡県にも支店を開設予定。
FPTジャパンは、日本におけるテクノロジーおよびITサービスの市場シェアを継続的に拡大し、大手日本企業の重要なデジタル変革プロジェクトの実装に数多く参加し、2025年までに日本のITサービス企業トップ20入りを果たし、2027年までに収益10億米ドルを達成することを目指しています。

FPTジャパンは現在、北海道から沖縄まで日本国内に15の拠点と本社を構え、約500社の顧客を抱えています。 2022年の売上高は380億円(3億6000万米ドル相当)に達すると予想されています。 2023年には480億円(21%成長)に達し、FPTソフトウェアの収益の37%を占めると予想されています。
当初は数名の従業員から始まったFPTジャパンは、2023年5月までに、600名の日本人を含む19か国以上の2,500名以上の従業員を抱えるようになりました。 2023年末までに3,000人に達すると予想されています。
このベトナム企業はまた、「アメリカに勝つ」というスローガンを掲げ、2027年までに10億ドルの収益と5,000人の従業員を達成し、世界の一流企業と競争できるグローバル企業になるという大きな目標を設定しました。
これらのベトナム企業は、桜の国で多くの印象的なイメージを作り出しており、国際的な交流や会議で彼らの名前を挙げるときに、私だけでなく多くの人が非常に誇らしく感じています。
記事: TS。情報通信省情報技術産業局副局長 グエン・タン・トゥエン氏
デザイン:ミン・ホア
ベトナムネット
































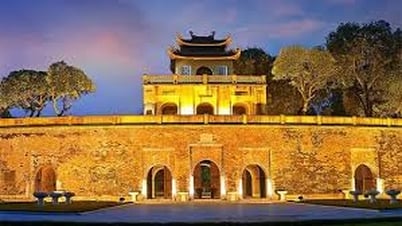


















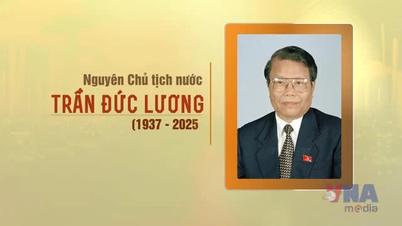








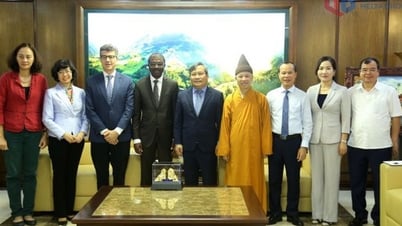
















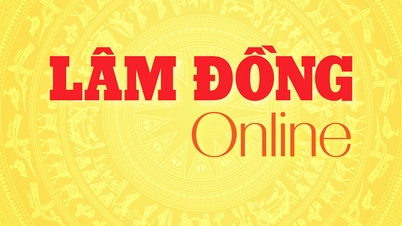








コメント (0)