 |
| 中国広西チワン族自治区の市場で買い物をする消費者。(写真:新華社) |
具体的には、日本経済は2023年に名目成長率が5.7%を記録し、中国は4.6%増加しました。
この驚くべき反転は、日本がインフレに陥り始め、中国がデフレ圧力に直面している中で起こった。
世界第2位の経済大国である中国は、昨年実質5.2%の成長を記録しました。実質成長率は前年比で加速しており、これは新型コロナウイルス感染症の影響で経済が急激に縮小した2022年の3%成長からの回復によるところが大きいです。
しかし、インフレを考慮した名目成長率は、前年の4.8%から2023年には4.6%に減速する。
米国やドイツなどの国は名目成長率が6%を超えており、日本以外の主要先進国と比べると中国の減速が目立っている。
一方、北京では、長引く不動産価格の低迷と、特に若年層を中心とする厳しい雇用市場の影響を受け、内需は依然として低迷している。同時に、インフラや産業セクターへの投資が供給能力を押し上げ続けており、経済に持続的なデフレ圧力がかかっている。
また、消費者物価は2024年1月まで4か月連続で前年同月比で下落しており、生産者物価指数は2022年10月以降前年同月比でマイナスとなっている。
ムーディーズ・インベスターズ・サービスのアナリスト、リリアン・リー氏は、中国がここ数週間で講じた政策措置は経済成長の促進を狙ったものだが、実際の結果はまだ不透明だと述べた。
「2024年の名目GDP成長率への影響は、これらの措置と将来の景気刺激策が市場の信頼感を改善し、持続可能な形で需要を押し上げることができるかどうかにかかっている」と彼女は述べた。
独立系調査会社ガベカルの中国戦略家トーマス・ガトリー氏によると、世界第2位の経済大国である中国のデフレ圧力は今後も続くか、あるいはさらに増大し、世界の物価に下押し圧力をかける可能性が高いという。
「歴史的な不動産ブームが明らかに終焉を迎えた今、 政府は将来の成長を牽引するため、製造業の拡大に全力を注いでいます。中国は今後数年間、デフレ国であり続けると信じるに足る十分な理由があります」と彼は述べた。
同時に、中国の製造業の力は、特に中国が2001年に世界貿易機関(WTO)に加盟して以来、過去20年間にわたり世界的なインフレを抑制する重要な要因となってきた。
ガトリー氏は、中国要因が価格を押し下げる可能性があると考えている。「世界価格に対する中国の影響力は、より明確にデフレ方向に傾いている」と同氏は述べた。
[広告2]
ソース








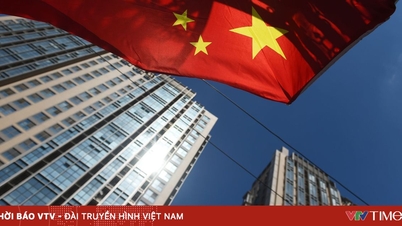




























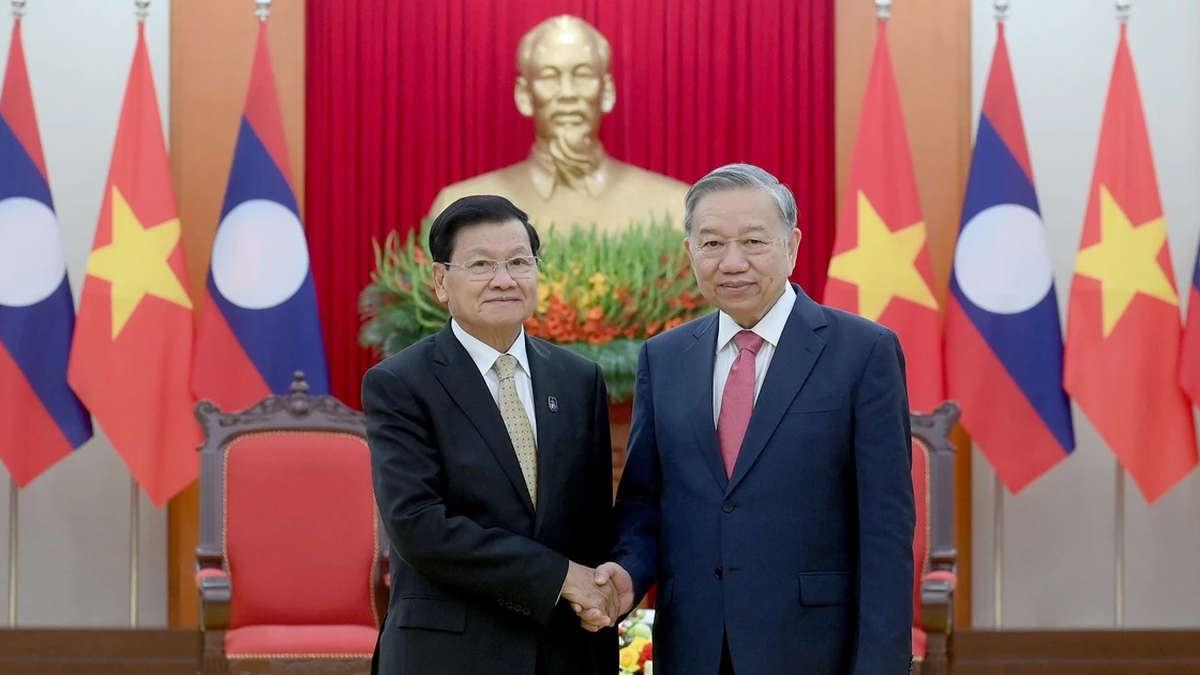











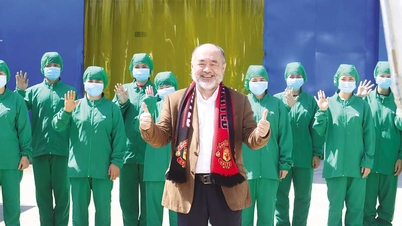




























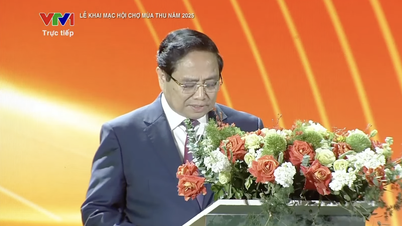





































コメント (0)