優れた専門家と一緒に学び、実践しましょう
2022年、Nguyen Anh Minhさんは学生でありながら、 Viettel Telecomでデータサイエンスを専攻するインターンとして、夢の環境で実力を試すことができました。アン・ミンさんはハノイ工科大学の数学と情報技術の卒業生代表で、実務経験のあるエンジニアになりたいと考えています。この学生にとって忘れられない思い出は、割り当てられた仕事で最高の結果を出すために会社に泊まり込み、夜を徹して働いた日々です。大学とビジネス環境での3か月にわたる並行トレーニングを経て、ミンさんは他の何百人もの学生よりも優秀な成績を収め、そのまま滞在して働くよう招待されました。
 |
ハノイ工科大学の学生が2024年若手創造性コンテストで最優秀賞を受賞 |
ミン氏によると、この実践的な研修プログラムは、学生が一流の専門家から専門スキルを磨かれるだけでなく、テクノロジーに情熱を持ち、後に同僚となる若者と出会い、交流し、夜通しテクノロジーについて議論できるという点で非常に価値があるという。教室を離れてダイナミックな環境で2年間働いた後、ミンは責任と規律の訓練、やる気を引き出す方法を知っている人々との働き、若者への信頼、彼らを「独力で泳がせる」のではなく人材育成に重点を置くことなど、多くの価値観を学びました。
 |
2024年青少年創造製品展におけるハノイ工科大学の科学研究成果 |
ミンさんと同様に、2024年には、学生のグエン・ティ・リンさんがハノイ工科大学を優秀な成績で卒業し、若手人材育成プログラムのチャレンジに6か月間参加した後、グループに採用されました。 Linh はクラウド ソリューション エンジニアの役割を担います。リンさんにとって、会社で研修を受けた時期は、継続的に勉強し、ソフトスキルを向上させる必要があったため、最も成熟し、最も多くを学んだと感じた時期でした。当時、多くの人が「女の子でもテクノロジーはできるのか?」と疑問を抱いていました。彼女はテクノロジープロジェクトに取り組み始めたとき、仕事のために午前1時~2時まで起きていなければならないというプレッシャーを感じるのがいかに大変で、いかに普通のことかに気づいた。彼女が驚いたのは、エラーが多かったプロジェクト段階で、人々が午前4時から5時まで議論していたことです。技術的な知識やプロジェクトの実施経験だけでなく、仕事をする上での「闘う」精神も学びました。 「さらに、後にプロジェクトに参加した学生たちは、同じ企業に勤めていなかったにもかかわらず、テクノロジーに情熱を燃やす人々のコミュニティ、ネットワークを形成し、互いに交流しました」とリン氏は語った。
「国家は中核研究、基礎研究、技術移転に投資するとともに、大学や大学院の研修施設に体系的かつ綿密に投資し、中核技術に関連する基礎科学の発展を優先し、人材を他国に派遣して国の主要産業を育成する戦略を立てる必要がある。」グエン・ヴァン・ミン教授
Viettel軍事産業・通信グループの人材組織部門責任者であるVu Thi Mai氏は、同部門は長年人材競争の問題に直面しており、技術に長けた質の高いデジタル人材をどのように育成するかという課題を設定したと語った。目的は、企業の人材を「充実させる」だけでなく、国の労働市場に向けて若く優秀な人材を育成することにもある。大学と企業が連携し、学生にビジネス研修プログラムへの参加を紹介することで、質の高い人材を育成する共鳴モデルを研究しています。
「世界各国の企業は人材育成プログラムを実施し、研修生のマネジメント戦略を構築しています。多くの人材が成長し、企業のリーダーへと成長しています。大学と企業の連携と共鳴が人材育成に大きな効率性をもたらしていることがわかります」とマイ氏は述べた。
大学での研修とは異なり、インターンは企業に招待され、国内外の評判が高く経験豊富な専門家から徹底的な研修を受け、技術知識を向上させます。しばらくすると、学生たちは自分自身に挑戦するために大きなプロジェクトに「放り込まれ」ます。各学生は、指導と即時の作業のために、プロジェクトでの実務経験を持つ人とペアになります。多くの学生が、プロジェクトに取り組んでいた 3 か月間、効果的かどうかは別として、学んだ知識を仕事に応用する機会でもあったため、全員がストレスを感じ、食べることや寝ることを忘れて能力を最大限に発揮していたと話していました。このプログラムは、デジタル人材を育成し、テクノロジー分野の学生に刺激を与えることを目的としています。彼らは研修ユニットで直接働くわけではないが、テクノロジー分野の学生にとってインスピレーションの源になるだろうと信じている。
科学技術大臣グエン・マイン・フン氏によれば、科学技術イノベーション法案は基礎研究を高等教育機関に移すことを提唱している。これが国家の主要な方向性です。この変化は、各国が大学を研究センター、特に基礎研究の中心とみなす国際的な慣行と一致しています。なぜなら、大学には最も基礎的な研究を行う人材、特に講師、教授、学生、大学院生などの若い人材が集中しているからです。
大学と企業が協力
同社の採用担当者は、実際には学校を卒業したばかりの学生は経験も仕事のスキルもない「白紙の状態」なので、職業訓練が必要であり、将来良い製品を作るために夢と志を持つように促されていると語った。以前は科学が好きで研究に熱中していたものの、もっと現実に「浸る」必要があった生徒もいます。
ハノイ工科大学は毎年、科学研究をする学生と企業、科学者、スタートアップ コミュニティを結びつける会議を開催しています。 2025 年、学生のテーマは、環境、エネルギー、教育技術、デジタル変革など、生活における具体的な問題の解決に重点を置くようになります。
研究期間終了後、学生たちは発表や討論を行い、専門家、テクノロジー企業、投資家、イノベーションの専門家が招待され、評価、コメント、優れたトピックの選択のプロセスに直接参加します。ハノイ工科大学は、これが学生と労働市場、研究と製品の商業化の間に実際的な架け橋となると考えています。
最近、ハノイの大学は、国の社会経済発展に貢献する、教育機関における科学、技術、革新、国家のデジタル変革の飛躍的進歩に関する決議57号を実施するための解決策を議論するセミナーを開催した。貿易大学学長のブイ・アン・トゥアン准教授は、関連組織の連携を促進し、リソースの交換と活用を促すオープンイノベーションエコシステムが必要だと述べた。
トゥアン准教授によると、現在のボトルネックとなっているのは、リソースの分散、効果的なリソース共有メカニズムの欠如、メカニズムとポリシーの非同期により、ハノイが期待通りにオープンイノベーションエコシステムをまだ構築していないことだ。そのため、政府機関、企業、大学・研究機関間の連携を強化する必要がある。ランホアラック ハイテクパークをオープンイノベーションパークとして構築し、エコシステム内の関係者を結び付けてリソースを引き付けて共有するセンターにします。彼は、革新的なメカニズムで企業を誘致し、訓練における大学や研究機関の存在感を高めるための連携と協力の政策を強調した。
ハノイ教育大学の元学長グエン・ヴァン・ミン教授は、科学技術はどの国にとっても進歩と発展の鍵であると語った。現在の解決策の一つは、コア技術を見極め、その技術を習得するための人材育成やインフラへの投資に注力するとともに、国内企業や法人と大学、研究機関との強固な関係を構築し、製品を迅速に市場に投入することです。同時に、科学技術イノベーションの発展を支援するための基金を設立する必要がある。
出典: https://tienphong.vn/thuc-day-nghien-cuu-trong-truong-dai-hoc-post1744351.tpo



![[写真] ニャンダン新聞社主催全国卓球選手権団体準決勝の組み合わせ決定](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/21/eacbf7ae6a59497e9ae5da8e63d227bf)












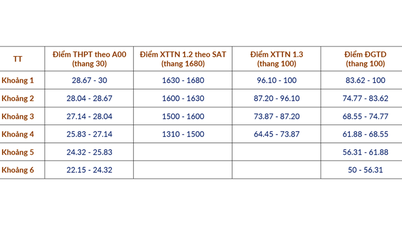

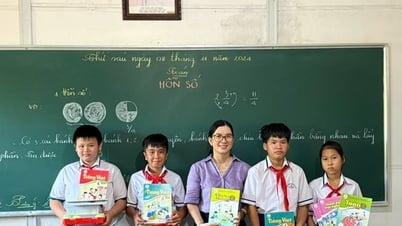










![[写真] ファム・ミン・チン首相が5月に政府の立法に関する特別会議を議長として開催](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/22/1c880aae96fd4e0894abc47a46fe19ba)



































































コメント (0)