ハノイ国家大学経営学部非伝統的安全保障研究所所長、人民警察アカデミー元学長のグエン・スアン・イェム中将教授によると、ベトナムの高等教育システムの再構築と近代化は、専門的な課題であるだけでなく、国の新たな発展過程における政治的かつ戦略的な要件となっている。政治局決議第71号および政府決議第281号は、工業化、近代化、国際統合の要件を満たす、開放的で柔軟性があり、質の高い教育システムを構築し、優秀な人材を育成するという目標を掲げている。
イェム中将は、「40年間のイノベーションを経て、ベトナムの高等教育は規模と質の両面で大きな進歩を遂げてきました」と述べ、「しかし、現在のシステムは、ガバナンスモデル、研修組織、運営方法に至るまで、包括的な再構築が急務となっています」と付け加えた。イェム中将は、強力なイノベーションがなければ、高等教育は知識経済と第四次産業革命の進展に追いつくことが困難になると強調した。
 グエン・スアン・イェム中将教授は、大学教育制度を抜本的に改革すべき時が来たと強調した - 写真:VGP/Thu Trang
グエン・スアン・イェム中将教授は、大学教育制度を抜本的に改革すべき時が来たと強調した - 写真:VGP/Thu Trang
否定できない成果
建国80年、特に40年間の改革と、2013年11月4日付の教育訓練の抜本的かつ包括的な改革に関する決議第29-NQ/TW号の10年以上にわたる実施を経て、ベトナムは多くの重要な成果を達成しました。規模の拡大、訓練の質の向上、国際統合の強化、カリキュラムの革新、そして訓練と労働市場の連携などがその顕著な成果です。
高等教育は、人々の知識の向上、人材育成、才能の育成、そして社会経済の発展への実践的な貢献に重要な貢献を果たしてきました。多くの大学が、特に科学技術、工学、医学、安全保障・防衛の分野において、国際基準を満たす質の高い教育プログラムを実施しています。また、教員や学生の交流、共同研究などを通じて、国際協力も推進されています。
しかし、イエム中将は、現在の教育制度には依然として多くの限界と欠点があり、画期的な革新が必要だと警告した。
ベトナムの高等教育の限界とパラドックス
グエン・スアン・イェム中将教授によると、現在、ベトナムの教育制度は逆ピラミッド型になっているという。就学前教育と一般教育はすべての子どもに普遍的に提供されるべきであり、あらゆる村落に学校網が整備されているにもかかわらず、多くの都市部、工業団地、輸出加工区、さらにはハノイやホーチミン市でさえ、学校、クラス、教師が不足している。それとは対照的に、スリムでコンパクト、そして強固であるべき大学教育は量的に発展しており、多くの学校では優秀な講師が不足し、学生数も少なく、設備も不十分で、教育の質も低いという状況となっている。
現在、国防・安全保障分野の学校を除いて、全国に260以上の高等教育機関があります。このうち、中央省庁・支局管轄の大学は171校、省・市人民委員会管轄の大学は26校、私立は77校です。こうした高等教育機関の拡大は、幅広い層の人々に大学進学の機会を創出し、学校間の競争を促進しました。しかし、教育の質の管理が不十分なため、多くの卒業生が就職できず、一部の大学は合併、解散、あるいは教育方法の変更を余儀なくされています。この状況は、特に教育学、法学、医学の3つの専攻において顕著です。
 教育分野には現在 103 の研修機関があります。
教育分野には現在 103 の研修機関があります。
教育システムの「主力機関」とみなされる教育分野には、現在103の養成機関があり、専門教育大学、学際大学、アカデミー、教育カレッジなどが含まれています。数は多いものの、その分布は分散しており、効果的に連携されていません。入学は困難で、研修内容は実践と結びついておらず、実習時間は限られており、受講生を惹きつける政策も魅力的ではありません。
法曹界も急速に成長しており、学部養成機関は79校に上り、そのうち28校は私立である。多くの多科大学は年間数十人の学生しか養成しておらず、教科書や常勤講師が不足しているため、質の不均衡が生じている。修士課程では、私立の機関が19校が養成に参加しており、修士課程総数の48.7%を占めているものの、規模はわずか1,439人で、学生総数の17.4%に過ぎない。法曹養成プログラムは実務を重視しておらず、学部養成と法曹養成が分離されているため、連携性や標準化が欠如している。
医療分野では、国内に約30校の総合診療医養成学校があり、主に北部・中部(19校)、南部(11校)に分布しています。医師の卒業生数は、2015~2016年の年間約8,000人から、2023年には年間約10,000人に増加すると予想されています。
経済学や経営学を専攻する学生は、主に一つの専攻分野を専門とする一方、社会やビジネスのニーズには、多分野にわたる知識と高度な技術の応用が求められます。卒業生は現実に戸惑い、適応や就職に苦労することがよくあります。これは、プログラムが富を得るためのスキルに重点を置いており、経済的な違反やミスを防ぐことに配慮していないことが一因です。
教育体制に加え、大学運営は依然として脆弱です。学長・学長の権限は不十分で、施設は科学研究と密接に連携しておらず、センター、研究所、強力な国際研究グループも不足しています。学校の安全と秩序は重視されておらず、校内暴力、悪質な文化、法律違反といった非伝統的なリスクは複雑です。施設は依然として不足または劣化しており、教育の社会化は効果的ではなく、財源も限られています。ハノイ国立大学、ホーチミン市国立大学、ハノイ工科大学、FPT大学、人民警察アカデミー、陸軍士官学校など、美しいキャンパスと近代的な設備を備えた大学はごくわずかですが、需要に見合う数はまだごくわずかです。
ベトナムの大学システムは、質の面で非均衡な発展を遂げており、配分も不均衡で、科学研究や社会実践との連携も不十分です。これらの問題は、新時代の質の高い人材の需要に応えるために、大学教育の質を向上させるための喫緊の課題です。
 ホアラックにあるハノイ国立大学のキャンパス。
ホアラックにあるハノイ国立大学のキャンパス。
大学再編における国際的な経験
高等教育機関の合併と再編は、世界において目新しいものではありません。中国では1996年から2001年にかけて、385の高等教育機関が164の高等教育機関に統合されるという大規模な合併の波が起こりました。この合併は2000年にピークを迎え、203の高等教育機関が105の合併を経て79の高等教育機関に統合されました。これにより、国際ブランドを持つ重点大学が誕生し、資源の分散・細分化という課題が解消され、競争力が強化されました。日本と韓国も同様の再編プログラムを実施し、専門性の向上、ガバナンスの改善、資源の有効活用を目指しました。
国際的な経験から、大学の合併には主に3つの利点があることがわかっています。第1に、総合大学を形成し、学際的な教育と研究を促進し、学習と科学研究の質を向上させること。第2に、管理と資金調達における地方自治体の役割を強化し、大学が地域の社会経済発展のニーズにさらに密接に結びつくように支援すること。第3に、国際競争力を高めながら、人材を誘致し、地域の経済発展を促進する能力を向上させることです。
典型的な例は、2000年の上海医学大学と復旦大学の合併です。合併前、復旦大学は多くの分野で国家重点大学でしたが、医学部がありませんでした。合併後、大学院生と学部生の比率は1998年の46%から2001年には62%に増加し、研究生産性と国際資金が大幅に増加し、国際論文数も急増しました。これにより、復旦大学は世界クラスの教育機関になるという目標に一歩近づきました。
ベトナムの高等教育改革案
グエン・スアン・イェム中将は、ベトナムの高等教育は、断片的で分権化されたモデルから、多層的で合理化され効率的なシステムへと大きく転換する必要があると強調した。中将は、エリート層を対象とする大規模大学、地方・地域大学、そして警察、陸軍、検察庁、裁判所といった専門大学の設立が極めて重要だと指摘した。各大学は明確な使命を担う必要がある。エリート大学は博士課程の教育と高度な研究に重点を置き、地方大学は広域の人材育成に、地方大学は主に省・都市の人材育成に、専門大学は各部隊の専門教育に責任を負う。イェム中将は、小規模で弱小な単一専攻の訓練施設を大規模大学に統合することで、資源の集中化と訓練の質の向上が図られると同時に、不適格な学校を廃止し、現在の264校を100~130校程度に削減することを目指していると述べた。
このモデルを実現するために、イェム中将は大学の自治と厳格なガバナンスの重要性を強調した。大学の学長または理事には最高権限が与えられ、学校のあらゆる活動に責任を負う必要がある。人民警察学院は典型的な例であり、理事は党書記を兼任し、活動の決定、社会化資源の促進、国際協力などに関する全権を有している。イェム中将によると、国家管理権と大学の自治権を明確に分離することで、大学は柔軟な教育体制と透明性のあるガバナンスを両立させることができるという。
 大学の近代化と強力な研究機関や研究グループの開発という目標を設定する必要がある。
大学の近代化と強力な研究機関や研究グループの開発という目標を設定する必要がある。
イェム中将は、大学の近代化と強力な研究機関・研究グループの育成という目標も設定しました。プログラム、施設、人材の近代化、国際認証の取得、デジタル技術と人工知能の活用、そして情報技術、サイバーセキュリティ、機械工学、自動車、原子力、食品技術といった主要産業の育成に重点を置くことを提案しました。主要大学は国家の重点研究センターとなり、スマートスクールモデルへと移行し、ネットゼロエミッションの達成に尽力する必要があります。
最後に、イェム中将は高等教育における国際協力の重要性を強調した。ベトナム・ドイツ、ベトナム・日本、ベトナム・フランス、RMITベトナムといった外国と連携した大学モデルの構築、そして国際的な科学者を招き入れ、教育と研究の協力を推進することを提案した。イェム中将は、国際的な大学がベトナムに支部を設立し、共同研究センターを結成するための環境を整備することで、ベトナムの高等教育水準を向上させ、新時代の要求に応える質の高い人材を育成することができると述べた。
全体として、イエム中将は、ベトナムの高等教育は、合理化、近代化、自立、国際統合の方向に「再構築」する必要があり、同時に統治を明確に階層化し強化し、国の開発ニーズを満たすために何世代にもわたるエリート人材を育成する必要があるとのメッセージを送った。
baochinhphu.vnによると
出典: https://baocamau.vn/ve-lai-ban-do-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-yeu-cau-cap-bach-cua-ky-nguyen-moi-a123043.html





![[写真] 第1回世界文化祭でユニークな体験を発見](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760198064937_le-hoi-van-hoa-4199-3623-jpg.webp)






























![[写真] 朝鮮労働党創立80周年記念パレードに書記長が出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760150039564_vna-potal-tong-bi-thu-du-le-duyet-binh-ky-niem-80-nam-thanh-lap-dang-lao-dong-trieu-tien-8331994-jpg.webp)































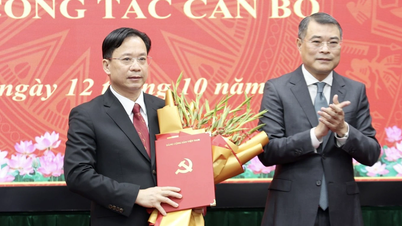







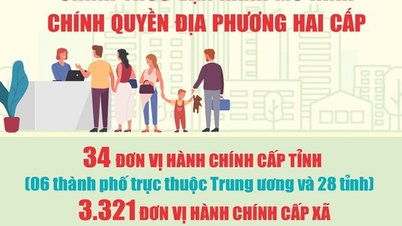


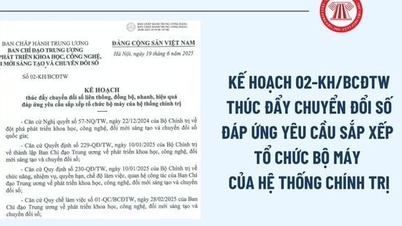


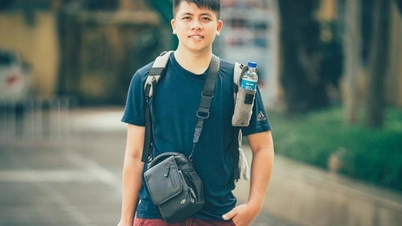


















コメント (0)