学校で英語以外の言語を学ぶ6万人以上の生徒のうち、大多数がフランス語と日本語を選択しています。
教育訓練省は、根本的かつ包括的な教育革新に関する決議29号の10年間の実施(2013~2023年)をまとめた報告書草案の中で、外国語の教育と学習には多くの前向きな変化があったと述べた。
現在までに61の省・市が就学前児童向けの英語導入プログラムを実施しており、すべての省・市で小学校3年生から10年間にわたり英語教育が実施されています。この10年間のプログラムに参加する生徒数は、2013~2014年度と比較して39%増加し、68%に達し、約1,220万人に相当します。
英語に加えて、41の地域では6万人以上の生徒が学ぶ外国語の教育が行われています。中でもフランス語は最も多く教えられ、学習されており、約3万800人の生徒がいます。次いで日本語と中国語が続きます。これらも小学校、中学校、高校の3つのレベルで教えられている外国語です。
ドイツ語、韓国語、ロシア語など残りの外国語は、一部の中学校と高校でのみ教えられています。
以前は、外国語は小学校ではなく、中学校および高等学校で必修科目でした。新しい一般教育計画(2018年度)によると、外国語は3年生から12年生まで必修科目です。外国語のリストには、英語に加えて、中国語、ドイツ語、日本語、韓国語、フランス語、ロシア語も含まれています。
文部科学省のガイダンスによると、学校は実情と生徒・保護者のニーズに基づき、上記の外国語のいずれかを必修科目(外国語1)として選択し、さらに別の外国語(外国語2)を生徒に教えることができます。
実際、ほとんどの学校は英語を第一外国語として選択しています。国境地帯の一部の学校では中国語が選択され、大都市では主にフランス語、日本語、韓国語が教えられています。
ハノイでは、ロモノソフ中等・高等学校のグエン・ティ・ニュン副校長が、一般学校で教えられる英語以外の外国語のほとんどは、保護者のニーズと各学校の状況に応じて、選択科目の「外国語2」となるだろうと語った。
例えば、ロモノーソフ学校では、ドイツ語、日本語、韓国語の3つの外国語2科目が教えられています。このうちドイツ語は、同校がゲーテ・インスティトゥートの提携校であるため、長年教えられてきましたが、韓国語と日本語は2018年度の一般教育課程開始時に導入されました。これらの外国語を教育に導入することは、社会のニーズに応えるためでもあります。
「生徒たちがもっと外国語を学ぶ機会を持ち、世界の知識にもっとアクセスし、グローバル人材となり、多くの分野で働けるようになればと願っています」とニュン氏は語った。

2019年、ホーチミン市にあるトラン・ダイ・ギア高等学校で外国人教師が教える授業。写真:レ・ナム
一般教育における外国語1は全1,155コマの授業時間数です。小学校では420コマ(週4コマ)、中学校では420コマ(週3コマ)、高等学校では315コマ(週3コマ)の授業が行われます。
外国語 2 は選択科目であり、学校は生徒のニーズと教育機関の能力に応じて、6 年生から任意の学年まで教育を編成できます。
[広告2]
ソースリンク




![[写真] バンタック川沿いにある学校の甚大な被害のクローズアップ](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F26%2F1764152130492_ndo_bl_img-8188-8805-jpg.webp&w=3840&q=75)









































































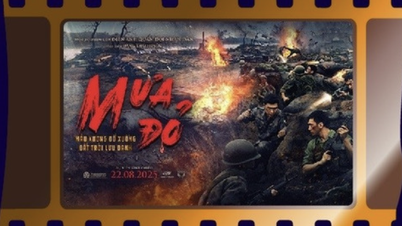




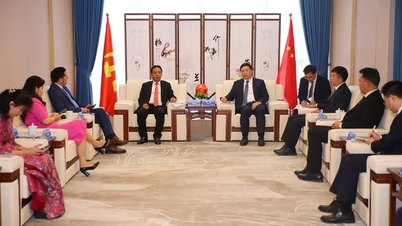





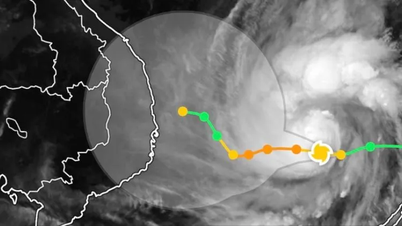



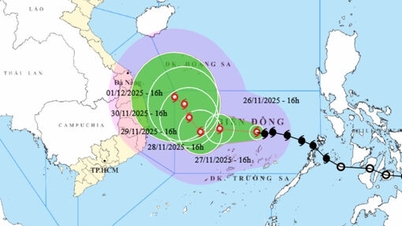




















コメント (0)