(BGĐT) - 母は煮魚の鍋を薪ストーブの上に置き、咳き込みながらかがんで火に息を吹きかけました。我が家はガスコンロになってから随分経ちますが、母は今でも毎日薪ストーブで料理をしています。ガスコンロで焼いた料理は美味しくないと言う母は、籾殻の灰の香りと炭の香りが混ざり合って初めて美味しく感じるのだと言います。
母の言うことは確かに正しいかもしれないが、庭の藁や薪についても、母は不満を抱いているのかもしれない。問題は、母が薪ストーブを設置している場所は、兄夫婦が先月建て終えたばかりの頑丈な3階建てのフランス風ヴィラのキッチンだということだ。兄の妻ハウは母に面と向かっては何も言わないのだが、母が庭の落ち葉掃きに出かけるたびに、ハウは兄のことを小言を言い、批判し始める。
「もし知っていたら、裏庭に木や藁、薪を置かないように、作業員にコンクリートを流し込んでもらっていたでしょう。別荘で、友達が来るたびにガスコンロのすぐ隣に薪ストーブがあるなんて、誰が想像したでしょう? きっと中途半端だって言われるでしょう!」
 |
イラスト:セージ。 |
兄はあえて反論せず、慎重に言葉を選びました。
- まあね、ハニー、来月お母さんはバおじさんの家に泊まるんだよ!
「おいおい、私たち二人が交代で一ヶ月ずつ母の世話をするんだから、ずっとそこにいるわけじゃないんだぞ。私を安心させようとしているのか?嫁とか姑とか思われたくないんだ。お前の好きにしろよ。でも来月にはもう台所で薪を燃やす煙を見たくないんだ」
ハウさんは元気よくバイクを押して出て行き、ハイさんは案山子のように歪んだ表情でそこに立ち尽くしていた。念のため言っておくと、ハウさんは最近全く料理をしていなかった。彼女は高位の公務員で、朝は車で迎えに来てくれるし、夕方にはハイさんがちゃんとした食事を用意してくれていた。とにかく食べなければ気が済まないのだ。
家を建てる前、母は野菜や鶏の世話を自由にできるように裏庭を空けてほしいと頼みました。母はもう年老いていて、長年竹の家に住んでいても、石灰とモルタルの匂いは今でも寒く、口の中が酸っぱいのです。兄はプライドなど全く持っていませんでしたが、母を喜ばせるために裏庭を残したいと考えていました。しかし問題は、姉のハウが、私たちのような教養があり地位の高い人間が、スタイリッシュでモダンではない家に住んでいることを人に言うのを恐れていることです。
母は邪魔になる木を全部切り倒せと言った。兄は反論する勇気がなかった。母は数日間、悲しみに暮れた。フェンスを作っている時、母は外に出て作業員たちを止め、自分が出入りできるように庭から出て行ってほしい、何年もそこにあった木を全部切り倒すな、鶏でも引っ掻いて爪を折ってしまうようなコンクリートを全部詰め込むな、と言った。かつて村を侵略者が破壊するのを防いだ時のように、母は両腕を広げて立っていた。兄は怖くなり、外に出て作業員たちに「わかった、わかった。フェンスは建てるだけ。でも庭からは出て行って」と言った。義姉のハウは2階から顔を曇らせながら見下ろしていたが、何も言わずに我慢していた。毎晩、兄に小言を言うことしかできなかった。
母はちょうど一日、巴おじさんの家に泊まりました。翌朝早く、鶏が鳴く前に、ハウおばさんはハイおじさんをベッドから引きずり出してバルコニーに連れ出し、庭を見渡しながら、力強い声で言いました。
「ところで、お母さんはバおじさんのところに行っていて、あと一ヶ月は帰ってこないの。業者を呼んで裏庭のコンクリートを流し込んで。公務員の家は、国民の模範となるように、モダンで清潔でなきゃいけないのよ。後でお母さんに聞かれたら、新農村開発運動のおかげで庭に生い茂った木を植えてはいけないって言って。もう全部やってるんだから、お母さんはコンクリートを剥がしてバナナや竹を植え直したりしないと思うわ。」
ハイ兄はまだ眠そうだった。庭一面をコンクリートで舗装するのは長い間気が進まなかったものの、近所で有名な妻のことが知られてしまうのではないかと心配だった。母から良い教育を受け、それなりの給料ももらっていた。しかし、妻が高い地位に就いてからは、彼が働く姿を見ることはなくなった。毎日家で料理や掃除をし、二人の子供たちを学校に送り迎えしていた。先祖の祭典の際、母や兄弟姉妹から「男は型破りであってはいけない」と何度も言われ、仕事に戻るよう促された。ハイ兄は、何かを探しているかのように庭の方を指さす妻のハウを見つめた。彼は眉をひそめ、子供たちがもう少し「大きくなる」まで、仕事に戻る前にもう少し世話をしたいと説明するように言った。
まだ高校生なのに、なんて若くて世間知らずなの! 子供たちが二人とも卒業して留学した後も、兄は仕事に復帰しませんでした。誰かが仕事の話を持ち出すと、「もう歳だし、仕事なんてどこに行けばいいの?」と呟くだけでした。ただ家にいて、主夫として家族のために尽くす。それが仕事ですから。その話になると、兄は顔を背けていました。母や兄弟たちは「男なら誰だって重荷に思われたくない」と、兄に仕事に復帰するよう何度も勧めました。でも、兄の心は鉛で重くのしかかっていたように、重く、暗いままでした。
ハウの言葉の後、ハイは何か呟き、それから電話を取り、便利屋に電話をかけた。それを見てハウは安堵し、家の中に入り、真新しい真っ白なドレスに着替えた。彼女は一週間以上出張で留守にするので、戻ったら庭の石畳をドレスの色に合わせた純白の模様にしてほしいと頼んだ。また、石のテーブルと椅子を設置し、水差しを持ったヴィーナス像か、ヨーロッパ風の真鍮ランプを置いて、毎晩庭を明るく照らしてほしいと頼んだ。
彼女は庭の片隅に、鯉のいる池と日本式の石庭を設計した。ここは来客をもてなしたり、バーベキューやシャンパンなどでパーティーを開いたりする場所になる予定だった。来客――役人やビジネスマン――のスタイルに合うものでなければならず、少なくとも現代の公務員のモダンさを反映していなければならなかった。彼女はこれらすべてが自分の地位にふさわしいと感じていた。彼女は夫を軽蔑するどころか、すべてのアイデアを思いついたのは自分だと自己紹介していた。しかし、この完璧な結果に至るまで、夫は多大な努力を払っていたのだ。
彼女は、夫が皆に貢献してくれたことに今でも感謝し、彼の支えがあったからこそ、行儀良く学業成績の良い二人の子供たちと、いつも健康で幸せそうな義母に恵まれたのだ、と認めていた。一体どんな時代を生きているのだろう?彼女は、現代の女性の役割における現代性と柔軟性を、皆に知ってほしいと思っていた。彼女はこの一家の家長であり、男性が長らく当然視してきた権利を持っていた。「成功した女性の背後には必ず男性がいる。恥じる必要はない」。白いドレスが揺れ、ほっそりとした脚で車に乗り込んだ。ドアがバタンと閉まった。この現代女性の出張は、真っ白なコンクリートに長く鋭い黒いタイヤ痕を残して、勢いよく走り去った。
***
ビンロウの実を噛んで口の中が赤く染まった母は、バナナ畑を見つめていた。母鶏が雛たちを連れて、のんびりと地面を掻き回してミミズを探している。目は衰え、足腰も弱っていた。母は慣れ親しんだ庭へと足を踏み入れた。もし転んでも、野菜やサツマイモの苗が支えてくれると分かっていた。清潔さや整頓が嫌いだったわけではない。だが、子や孫たちには、人工物の匂いではなく、故郷の香りを吸ってほしいと願っていた。母はビンロウの実を噛みながら物思いにふけり、それから鶏たちをそっと足元に寄せ、トウモロコシや米を少し撒いた。そして、日差しから身を守るように、しなやかに曲がった竹の茎を見上げ、微笑んだ。
家の前に車のブレーキのきしむ音が響き渡った。ハウさんは白いドレスをなびかせたまま、外に出た。彼女は振り返り、スモークガラス越しに車内の誰かに微笑みながら手を振った。それから、控えめながらも魅惑的な、ヨーロッパ風のキスをした。若い運転手は身をかがめ、彼女にピンクのスーツケースを手渡した。現代風の女性は出張から戻ってきた。ドレスは門の前でまだ楽しそうに揺れていた。
彼女はドアベルを鳴らしたが、誰も応答しなかった。おかしいな、夫はもう家にいるはずなのに。気にせず、自分の鍵でドアを開けた。長くカールしたつけまつげに縁取られた瞳は、夫が出て行く前に指示した通りに変化した庭へと向けられていた。しかし…想像していたほど壮大にも華やかにもなっていない。それどころか、すべてが本来の素朴な姿に戻り、以前よりもカントリーハウスのようだった。
彼女は裏庭へ急いだ。誰かがジャガイモの植え付けの準備のために掘り出したばかりの土塊につまずきそうになった。途中で立ち止まったのは、髪をきちんとまとめた母親が竹のベンチに座り、鶏たちをじっと見つめているのが見えたからだ。さらに遠く、竹林の近くでは、母親が庭から掃き集めた竹の葉でムクロジの湯を沸かしているようだった。その狭い空間には、ムクロジの強い香りが漂っていた。
母はなぜ月末前に帰ってきたのか?夢にまで見た「モダンな」庭はどこへ?夫のハイはどこへ?どうして母の言うことを聞かないのか?この一家の重荷を一人で背負っているのは母なのだと、皆は忘れてはならない…?
妹が戻ってくるのを見て、お母さんは優しく微笑みました。
- ハウ、戻ってきたの?お母さんがソープベリーのお湯を沸かしてあげたよ!こっちへ来て、髪を洗わせてあげる!
「お母さん、どうして帰ってきたの?夫はどこ?」
ハイがお母さんに会いたがってるって言ってたから、迎えに来て連れ戻してくれたんだ!仕事復帰したんだ!今週初めに協同組合の技術者の職に応募したんだ。つまり、私の部下ってことだよね?でも、最近は夫が妻より劣っていても別に問題ないんだよ!
「誰が彼に仕事に行けと言ったんだ?この家に必要なものはすべて私が用意した。何も不足していない。」
...
「お父さんには仕事に行ったって言ったのに!お母さん、この家はコンクリートだらけだと、だんだん家庭的な雰囲気も家庭の味も失われていくわよ!」
家の中から、ハウ夫人の長男の声が聞こえてきた。彼はハウ夫人が苦労して留学させた息子で、この家がモダンスタイルだったらきっと喜んでくれるだろうと彼女は思っていた。しかし、もしかしたら、彼女が思い描いていた通りにはいかないのかもしれない。
「お父さんだけじゃなくて、お母さん、私も仕事で戻ってくるわよ!先進国では、自分の庭を壊して他国の庭を真似しようとする人はいないわ。『文化とは、他の全てを失った後に残るもの』ってお母さん。お父さんは男で、どんな嵐の中でも家族の柱であり続ける。もしこの庭を壊したら、私たち家族の文化と愛情を自分の手で壊してしまうことになるわ。あなたがこの庭をコンクリートで舗装したいと言った後に、お父さんが今週かけた電話は、実は私宛だったのよ!お父さんの事情はよくわかるわ。お母さんもお父さんのことをもっと理解してほしいわ。」
ハウさんは凍りつき、それから視線を娘に落とした。白いドレスの裾が揺れを止めたようで、この場に場違いに見えた。まるで長い間何かを怠っていたかのようだった。いつか自分も、今の地位を誰かに譲らなければならない日が来る。もう長い出張はなくなる。高級車で送迎されることもなくなる。その時が来る。この庭が本来の姿でなくなったら、一体誰を迎えるというのだろう?
鶏の鳴き声が聞こえ、それから兄のバイクが仕事から帰るかすかな音が門のところから聞こえてきた。薪ストーブからはムクロジの香りがまだ残っていて、風に乗って庭を漂っていた。母は水差しのそばで私を待っていた。こんなにもこの庭に愛着を感じたことはなかった。今夜の夕食には、母がすでに煮魚をストーブにかけてくれていた…!
トラン・ゴック・ドゥックの短編小説

(BGĐT) - 池にかかる橋は、グアバの木の横に長年そのまま残っています。実は、木や竹が腐ったため、何度か架け替えられ、今では丈夫なコンクリート板に交換されています。この池は、ンガンさんの幼少期から60歳を超えた今も、生活の一部となっています。池は広く、三方が庭に面し、残りの一面は村の畑に続く道に面しています。
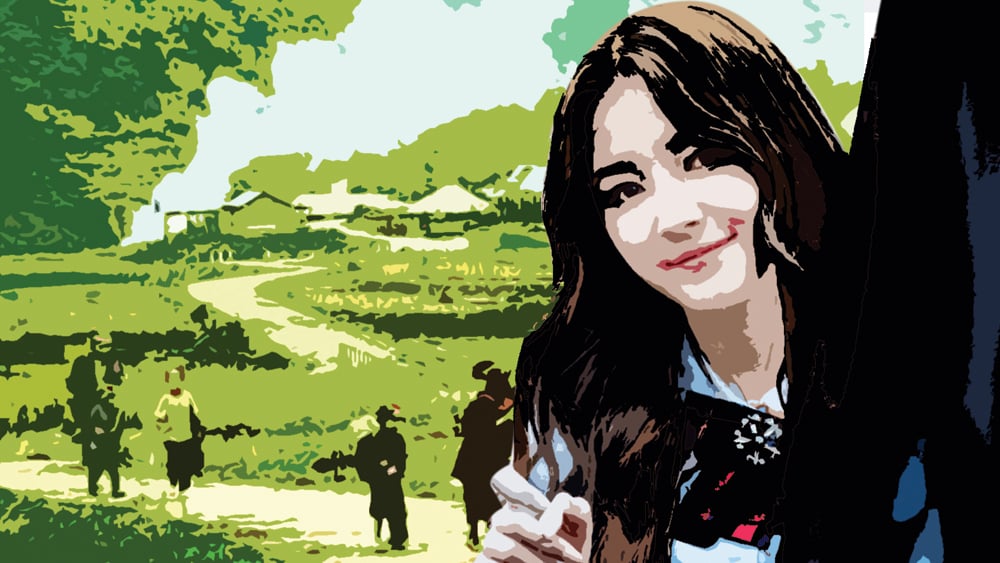
(BGĐT) - マイが薪の束を置いて、階段の最初の段にさえ乗らないうちに、祖父の低い声が聞こえました。

(BGĐT) - ニさんは、息子のトゥさんが賭博で警察に逮捕されたと隣人から知らされた時、庭でつまずいて転びそうになりました。幸いにも、ちょうどその時、孫でトゥさんの息子であるサンさんが駆け寄り、両手でニさんを支えてくれました。

(BGĐT) - ミンさんが車から降りるとすぐに、バイクタクシーや普通のタクシーの群れが彼女を取り囲み、乗せようとした。機知に富んだ一人の若い男性が、しきりに話しかけてきた。
バクザン省、庭、薪ストーブ、ガスストーブ、料理、嫁と姑、身分、家族、食事
[広告2]
ソースリンク










































































































コメント (0)