まず最初に、中国語の「囚 (qiú)」という言葉に由来する、漢越語の「刑務所」という言葉について議論しましょう。
「囚」という文字は、曹魏の時代に刻まれた古代文献『三身石経』に初めて登場します。 『正水石経』あるいは『魏石経』とも呼ばれるこの文献は、 『書経』と『春秋』を小篆書と隷書で記した石碑です。
今日の「監獄」 (囚)という文字は、囲む( vi )と囲まない( nhan)という2つの文字を組み合わせた表意文字である楷書から書かれています。
(人:人)。囗(ヴィ)という字は、人(ひと)を閉じ込めている牢獄のように見えます。この字には「𡆥」という異体字があります。
李雪芹・趙平安の原典によれば、牢獄の本来の意味は監禁することであり、これは『詩経』に明確に述べられている。名詞として用いられる場合、この字は囚人、拘留されている人を指す(『礼記』月令) 。後にその意味は「罪人の罪」 (『韓武物語』)へと拡大された。また、牢獄は「捕らえられた敵」 (『左伝』玄公12年) 、「包囲」( 『漢書』梅成伝) 、「制限、制約」(唐の孟嘗『董潘』)といった意味も持つ。
さて、時間を遡って「刑務所での 1 日は外での 1,000 年の価値がある」ということわざを学びましょう。
20世紀前半、 ホー・チミン主席の詩「Tu ca nguyet lieu(もう4ヶ月だ)」には、次のような2つの冒頭の行があります。 「Nhat nhat tu thien thu tai ngoai(獄中で1日、外で1000年。古人の言葉は間違っていない)」 (獄中日記より抜粋)。つまり、ホー・チミンおじさんは「 Nhat nhat tu thien thu tai ngoai 」は古人の言葉であり、彼が作ったものではないと述べています。
1914年から1915年にかけて、詩人ファン・チャウ・チンはフランス植民地主義者によってパリのサンテ刑務所に約10ヶ月間投獄されました。獄中生活の間、彼はクオック・グー文字で詩集『サンテ・ティ・タプ』を著しました。その中には「Nhat nhat tai tu thien thu tai ngoai」という詩が含まれています。しかし、この詩はファン・チャウ・チンの作ではありません。なぜなら、37年前の1877年に、タバード・コンスタンス著、JSテウレル編纂・補遺の『アナミティコ・ラテン語辞典』に「Nhat nhat tai tu thien thu tai ngoai」 (「刑務所」の項、508ページ)が掲載されていたからです。
現時点では、 「Nhất nhật tại tửn thiên thu hàng ô ô 」という文が中国語の「一日在囚千秋在外」という文に対応することは分かっていますが、この文の由来や作者を示す文献は存在しません。 「nhat nhat」 (一日)と「thiên thu」 (千年)という概念は物理的な時間を表す言葉であり、囚人の精神状態における心理的な時間を表すために使われているということだけが分かっています。
日本語には「一日三秋」(いちにちさんしゅう)という慣用句があり、これも心理的な時間について言及しています。しかし、この慣用句は囚人とは異なり、「一日三秋」という恋人のノスタルジックな気分を表現しています。
最後に、日本人が使う慣用句「一日三秋」は中国から来たもので、具体的には「一日不見、如三秋兮」というフレーズから来ており、「一日会わなければ三秋と同じ」という意味で、 『王風』(詩経)の「太猫」という詩から取られている。
出典: https://thanhnien.vn/lat-leo-chu-nghia-nhat-nhat-tai-tu-thien-thu-tai-ngoai-18525041821071343.htm


![[写真] ファム・ミン・チン首相がタイグエン省の嵐後の洪水被害の克服作業を視察し、指導する](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/08/1759930075451_dsc-9441-jpg.webp)
![[写真] ファム・ミン・チン首相が国際貨物運送協会連盟(FIATA)の世界大会に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/08/1759936077106_dsc-0434-jpg.webp)




















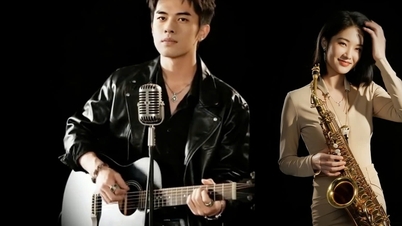








































































コメント (0)