「お茶」と「ワイン」という言葉は 19 世紀にベトナム語で登場し、フイン・ティン・パウルス・クア著「Dai Nam Quoc Am Tu Vi」 (1895 年)に記録されています。しかし、 「お茶とワインのあと」という慣用句が徐々に普及したのは 20 世紀前半になってからであり、具体的にはハ・ヌー・チのベトナムの詩と文学の講義の中で次のように述べられています。 「…中国学に精通した人々のお茶とワインのあとのひととき」 (Tan Viet Publishing House 1951、p.14)。
お茶を飲んだ後のティータイム(茶余酒后)は中国語に由来し、お茶を飲んだ後の自由時間を指します。語源的には、この慣用句は、元代の劇作家クアン・ハン・カン(1241年 - 1320年)の著書『ドウ・アム・トゥアン・ヌ・ヒエウ・ウイ』に初めて登場します。これは、山東省タオトラン市ティエットタン地区に由来する古代の民俗芸能活動を扱った作品です。
昔、旧正月が終わると、農民たちは自由時間(お茶やワインを飲んだ後など)に「ウズラと闘う」ことで楽しむことが多かった。このゲームの起源は唐代の玄宗皇帝の時代にまで遡ります。晩秋から初冬にかけてウズラが闘われることから、斗岩浄水場は東紅とも呼ばれています。そして、それぞれのマッチがサークル(圈:円形)と呼ばれることから、このゲームはアムトゥアンクェン(ウズラの輪)とも呼ばれ、タオトラン市の市級無形文化遺産に登録されている民俗ゲームです。
ベトナムでは「お茶を飲んだ後」という慣用句が非常に人気がありますが、同じ意味の中国語の慣用句が他に 2 つあり、ベトナム人はほとんど使いません。
1.食後の茶食(茶余饭后)は、食べたり飲んだりした後の自由時間を指します。ここでは、「酒」という単語の代わりに「米」という単語が使われています。一般的に、 「パン」は「米」を意味することが多く、 「バイミーパン」 (白米)などですが、 「ヒーパン」はお粥を意味します。また、 「phan」という言葉には、朝の食事(朝食)、夜の食事(夕食)など、一日の中で定期的に食べる主な食事という意味もあります。
2.午後のお茶と食事(茶馀饭饱)は、通常は食事の後に満腹になってからくつろぐ自由時間を指します(水は満腹を意味します)。たとえば、「お腹いっぱい食べた後は、自由におしゃべりする時間があります」 (お腹いっぱい食べた後は、自由におしゃべりする時間があります) 。この慣用句も、関寒卿の『斗槐湯女娜』に由来する。「夕食とお茶のあと、退屈しのぎに旧友を秦楼に招く」 (夕食とお茶のあと、退屈しのぎに旧友を秦楼に招く)
茶残りは、「お腹いっぱい食べた後は、散歩して食べ物を消化する」 (茶残り、散歩して食べ物を消化する)のように、「お茶を飲んで酔いを覚まし、食べ物を消化する」という意味もあります。
「茶と食物が豊富」という慣用句に関連する古代の文献には、1598年に書かれた明代の唐献祖による戯曲『牡丹亭・歓女』(還魂記とも呼ばれる)などがあります。
また、お茶と食べ物に関係があっても意味が全く異なる慣用句やことわざもあります。例えば、 「茶饭无心」は曹雪芹の『紅楼夢』に由来する慣用句で、飲食に興味がなく、憂鬱な気分を表している。 「茶は手に、食物は口に運ぶ」とは、召使いと共に幸せな生活を送ることを意味します。
[広告2]
出典: https://thanhnien.vn/lat-leo-chu-nghia-tra-du-tuu-hau-18524101822243389.htm







![[写真] ファム・ミン・チン首相が密輸、貿易詐欺、偽造品対策会議を議長として開催](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/14/6cd67667e99e4248b7d4f587fd21e37c)











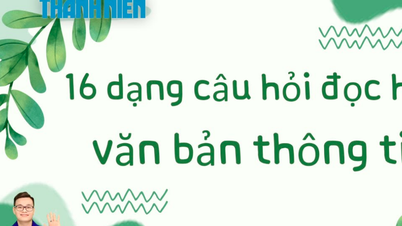






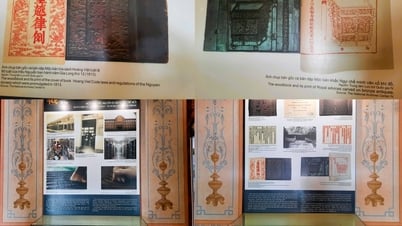





































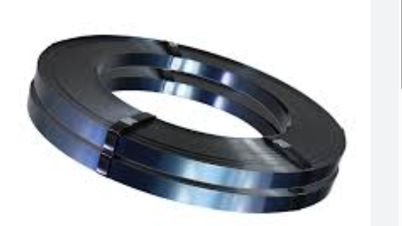

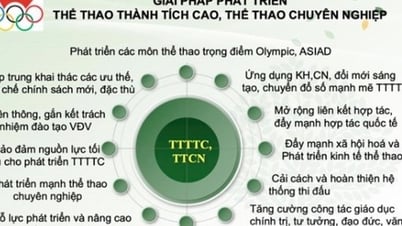






















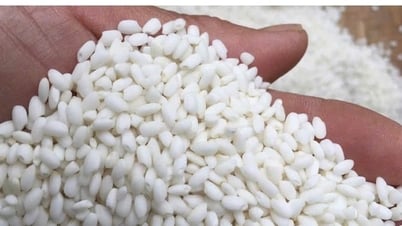
コメント (0)