この政策は現状では合理的な決定であると考えられており、国民に広く賛同されている。深く考えてみると、これは単なる教育政策ではなく、国家の発展の中心に知性を据える長期戦略の始まりなのです。
長年にわたり、一般教育、特に初等・中等教育は、カリキュラムが過密で設備が劣悪、時間割が短く、ほとんどの農村地域では生徒が1日1コマしか勉強しないなどの理由で、苦難の最前線にありました。授業のない午後、子どもたちは仕事、スマホの画面、あるいは目的もなく歩き回るといった重荷を何とかこなさなければなりません。多くの貧しい家庭は集中講座の授業料を払う余裕がないため、「質を犠牲にする」ことを選択せざるを得ない。
その文脈において、授業料なしで1日2コマの学習を受ける権利を普遍的な基準として国が確立したことは、制度上の転換点となる。学生たちは初めて「学校に通う」だけでなく、知識から技術、文化から芸術まであらゆることを学ぶことができるようになります。授業料の無償化は単なる福祉政策ではなく、学校正義への取り組みであり、平等な条件で成長する権利の保証です。そして、さらに重要なのは、これはこれ以上遅らせることのできない未来への投資だということです。
現代の教育は、成績や卒業率だけでなく、国民の質によっても評価されます。生徒が 1 日に 2 回勉強すると、音楽、美術、体育、生活技能など、しばしば「副次的」とみなされる科目に価値ある位置が与えられます。
試験にはでてこないけれど、人生に大切な、察する力、責任感、そして未来の世代に向けた総合的な健康を育む方法です。子どもたちは、よく勉強するだけでなく、健康で、自信に満ち、思いやりを持って生きる必要もあります。 1 日に 2 回のセッションを教えるということは、ただ十分に生きるのではなく、美しく生きることを世代に教えるということです。
1日2回の授業を普遍化する政策のほかに、 事務総長は国境地帯に対する教育政策も特に強調した。国境の町の生徒のために寄宿学校や半寄宿学校を建設するという要件は、単に地理的な困難に対する解決策ではなく、戦略的な選択です。なぜなら、国境地域には安全柵だけでなく、知識の「柵」も必要だからです。
国境地帯に住む少数民族やキン族の子どもが、清潔なトイレ、栄養のある昼食、熱心な教師、近隣の言語を教えるクラスがある学校で勉強することは、国境地帯の平和的発展と協力の最初の細胞です。国境地域の学生に外国語を教えることは、「楽しみのために教える」ことではありません。それは、国家のアイデンティティを守り、垣根ではなく知性で地域とつながり、国民同士の外交の架け橋となる世代のための準備です。
事務総長はまた、2025~2026年度から陸上国境地域から手続きを避け、ロードマップに従って実施する必要があると指摘した。条件のある地方自治体は指示を待たずに直ちに実施してください。そして特に、学生への食事の配給を削減することは厳しく禁止する必要がある。これは些細なことだが、政策実施の倫理に関する大きなメッセージを含んでいる。
教育費を節約して発展した国はありません。子どもたちが知識と人格の両面で十分な教育を受けなければ、創造的な社会はあり得ません。授業料の無償化、1日2コマの授業、国境地域の学校への投資は、国民を国家の発展の中心に据える同期政策思考のパッケージです。
出典: https://www.sggp.org.vn/mien-hoc-phi-tu-tam-nhin-tuong-lai-quoc-gia-post794384.html



![[写真] 党と国家の指導者が特別芸術プログラム「あなたはホーチミンです」に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/18/6895913f94fd4c51aa4564ab14c3f250)



![[写真] ベトナム卓球のトップ大会に向けて準備万端](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/18/9c547c497c5a4ade8f98c8e7d44f5a41)




































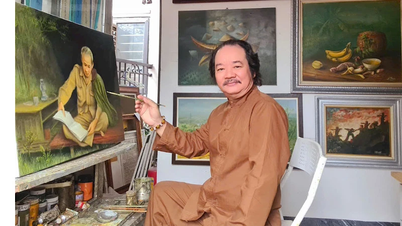





































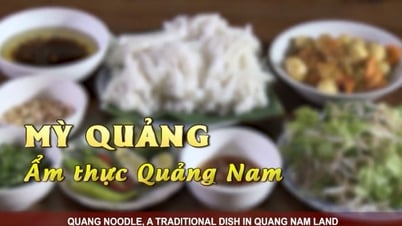






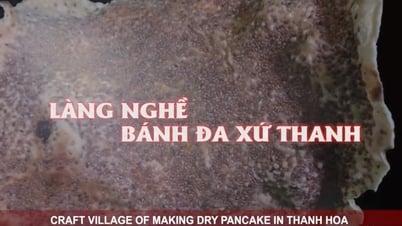


コメント (0)