 |
| 全国幹部会議は、党中央委員会の党建設・整流活動に関する結論と規定を徹底的に理解し、実行した。写真提供: dangcongsan.vn |
隙間が...
結論14の実施から2年以上が経ち、振り返ってみると、職場の雰囲気は変化したものの、はっきりとは変わっておらず、依然としてギャップが存在します。幹部がミスを恐れ、責任を回避し、逃げるという状況は依然として蔓延しており、果敢に考え、果敢に行動する姿勢は言うまでもなく、世論を懐疑的にさせ、失望させています。「創造性」と「突破」は義務的なレベルにとどまっており、幹部、特に指導者の責任感の基礎を築くような、真の突破的な変化は未だに見られません。多くの幹部が「敢えて考え」ましたが、「敢えて考える」から「敢えて行動する」へ、そして困難な課題に果敢に立ち向かう姿は依然として少数であり、現実からは程遠いものです。敢えて考え、果敢に行動しなければ、革新や創造性は生まれず、責任を回避する方法を探そうとするのは当然の理であり、多くの人々の思考の中に暗黙のうちに理解されています。そしてそれは、「6つの挑戦」と現在の役人や指導者の公共責任感との間のギャップでもある。
「懲戒会に立つよりは裁判会に立つ方が良い」「多くやればミスが増え、少なくやればミスが少なくなり、何もしなければミスがない」といった暗黙の「モットー」は、多くの幹部や党員の思考に静かに根付いており、一朝一夕で払拭できるものではありません。意図しない違反で次々と幹部が法に触れたことで、多くの幹部が中途半端な仕事ぶりと回避姿勢を身につけてしまいました。腐敗した上司が私利私欲で部下に規則違反を強要する事例が相次ぎ、多くの人々が法違反に直面するかもしれないという恐怖と恥ずかしさを感じています。これらの兆候と原因は、先日行われた第8回中央会議の閉会式で、グエン・フー・チョン 書記長が排除すべき現状として指摘しました。
「国民にとって有益なことであれば、全力を尽くさなければならない」
ミスを恐れるというのは、一部の役人による責任回避と責任放棄の控えめな表現に過ぎない。彼らは利益になることはすべて自分のものにし、困難が生じると、責任を取らなくても済む限り、組織、国民、企業に押し付ける。実際には、3つのタイプがある。低いレベルの役人は、資格がない、能力が低い、知り合いから昇進した、あるいは「場違いな場所」に座っている…といった理由で、あえて責任を取らない。より一般的なレベルの役人は、能力、資格、経験は豊富だが、利益になる場合にのみ責任を取り、自分や利益団体に「利益」がない場合は、やらない方が良い、あるいは中途半端な態度でやる。最も非難されるべきは、このようなタイプの役人である。 3 番目のグループは、仕事の内容を知っていて、それを実行できるものの、責任に対する恐怖の雰囲気に「囲まれている」ため、それに「対峙」しない、つまり「そのために仕事をしない」のが最善だと考える人々です。
結論14は「良薬」のようなものだが、多くの官僚の心理を重く圧迫する深刻な病を治すには依然として不十分であるように思われる。多くの官僚や公務員が職務遂行において責任を回避し、責任を欠き、ミスを恐れる状況は、孤立した現象ではなく、多くの分野や地域で発生している。公共投資プロジェクト、資産競売、医療用品調達などにおいて、責任を回避し「手探り」でいることは、上司の指示を待つという理由だけで、大きな無駄を生み出している。
幹部がミスを恐れ、大胆に行動できないのは、仕組みや政策が現実に追いついていないからだと言う人もいます。今の時点では仕組みが正しいかもしれませんが、別の時点では間違っているかもしれません。それは部分的には真実かもしれません。しかし、大胆に考えること、大胆に行動すること、そして責任を回避することという両極端を明確に区別することも必要です。結局のところ、腐敗がなく、明確な倫理観と自尊心を持ち、名誉を守ることを知り、高い責任感を持って仕事をする幹部は、ミスを犯す可能性は低いのです。上記の意見は、責任逃れと責任回避の正当化に過ぎず、早急に排除しなければなりません。
幹部が人民のために全力を尽くし、社会の進歩に高い効率をもたらすならば、たとえ「垣根を越える」ことや「壁を壊す」ことがあっても、党、国家、人民は必ず彼らを支持してくれるでしょう。元ビンフー省党委員会書記のハ・キム・ゴック同志が得た「垣根を越える」「違法な請負」という教訓は、後に我が党が農業請負に関する決議を採択する政策を研究し、策定する上での基盤と前提となっています。
ソース









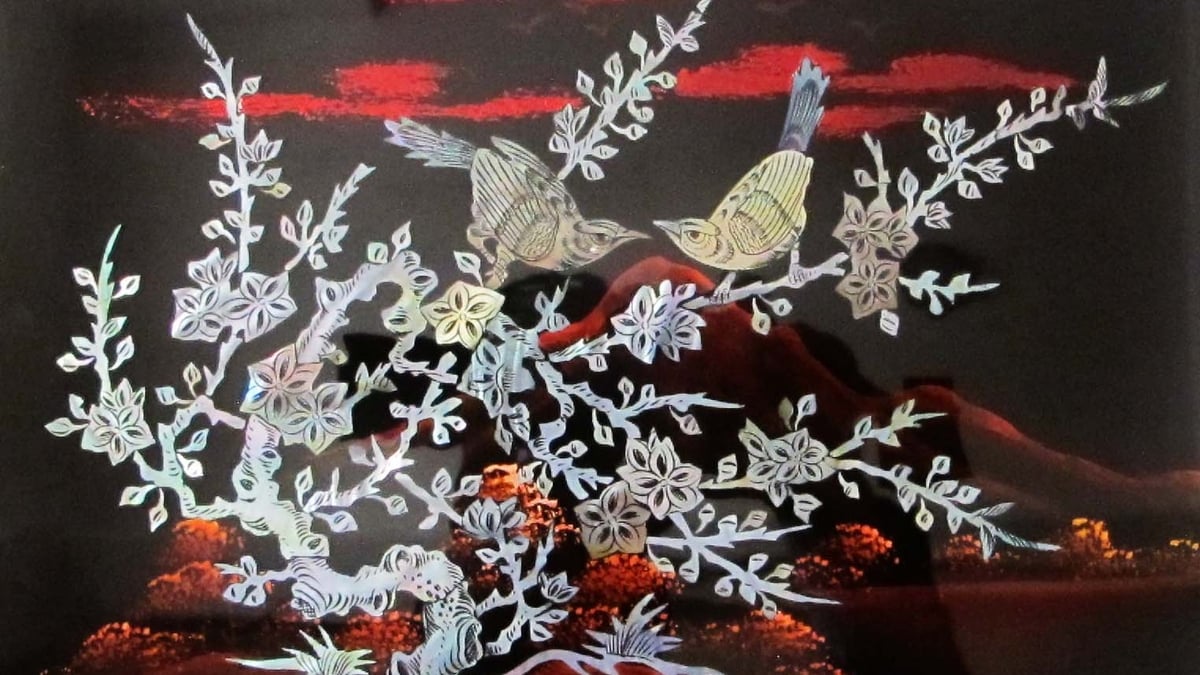

























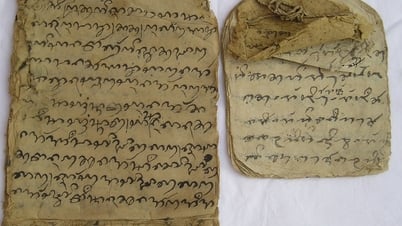





























































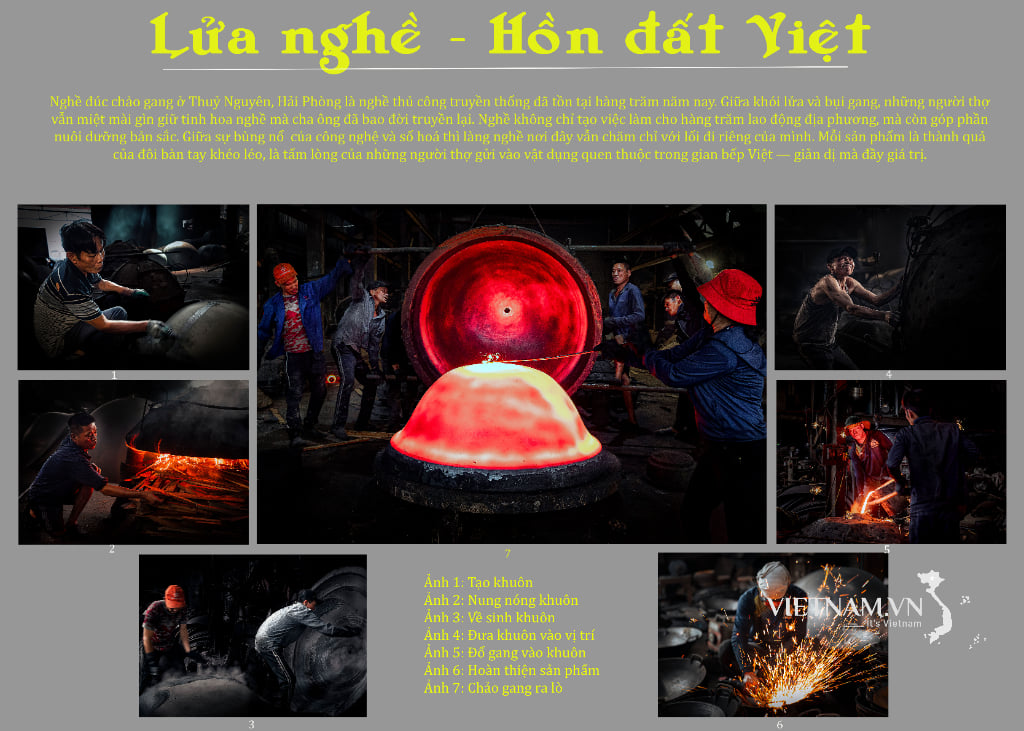


コメント (0)