2024年度版の「デジタル社会実現のための重点政策計画」では、ソフトウェアライセンス、クラウドストレージ、オンライン広告のコスト上昇による問題の深刻化を反映して、日本の「デジタル赤字」が初めて言及された。
日本銀行の国際収支データによると、デジタル関連サービス分野の赤字は2015年以降2倍以上に拡大し、昨年は5兆3500億円(337億ドル)に達した。観光業が回復したにもかかわらず、このことが日本のサービス収支全体の不均衡を招いている要因となっている。

デジタルサービスの需要は人工知能(AI)の幅広い発展とともに拡大し続けており、その多くはグーグル、アマゾン、マイクロソフトなど米国のテクノロジー大手によって満たされている。
外国企業と競争し、その依存度を下げることは容易ではありません。日本が直面する課題としては、付加価値の高い製品・サービスの創出が遅れていること、そして企業構造の再構築が課題となっています。
調査報告書では、日本企業は「生産性の向上や新規事業の創出に成果を示す必要がある」と指摘した。
先週、河野太郎デジタル変革大臣は、日本のIT・デジタル産業が競争力を高めるにはまだ長い道のりがあることを認めた。
東京都は、デジタル産業構築の基盤整備として、データ統合を推進する枠組みの構築や、デジタル変革に必要な人材の育成などを推進していく考えだ。
多くの企業のデジタル化を阻んでいるのは、レガシーシステムです。日本は「2025年のデジタルクリフ」と呼ばれる危機に直面しています。これは、レガシーシステムの運用経験と知識を持つ人材がいなくなる時期です。経済産業省は、システム障害のリスクによって年間最大12兆円の経済損失が発生する可能性があると推計しています。
専門家らは、課題に対処するには多部門のチームが計画を策定する必要があり、政府は比較的安価でビジネス環境の変化に容易に適応できるクラウド技術の活用を推進すべきだと述べている。
この計画の目標には、サイバー攻撃が頻発するにつれて重要性が増しているサイバーセキュリティ分野の専門家の育成も含まれている。
日本は、2023年4月時点で約2万人である国家資格の情報セキュリティ専門家を、2030年度までに5万人に増やすことを目指している。政府は、地域のサプライヤーや中小企業がサイバーセキュリティの基礎的な知識とスキルを習得しやすくしたいと考えている。
(日経アジアによると)
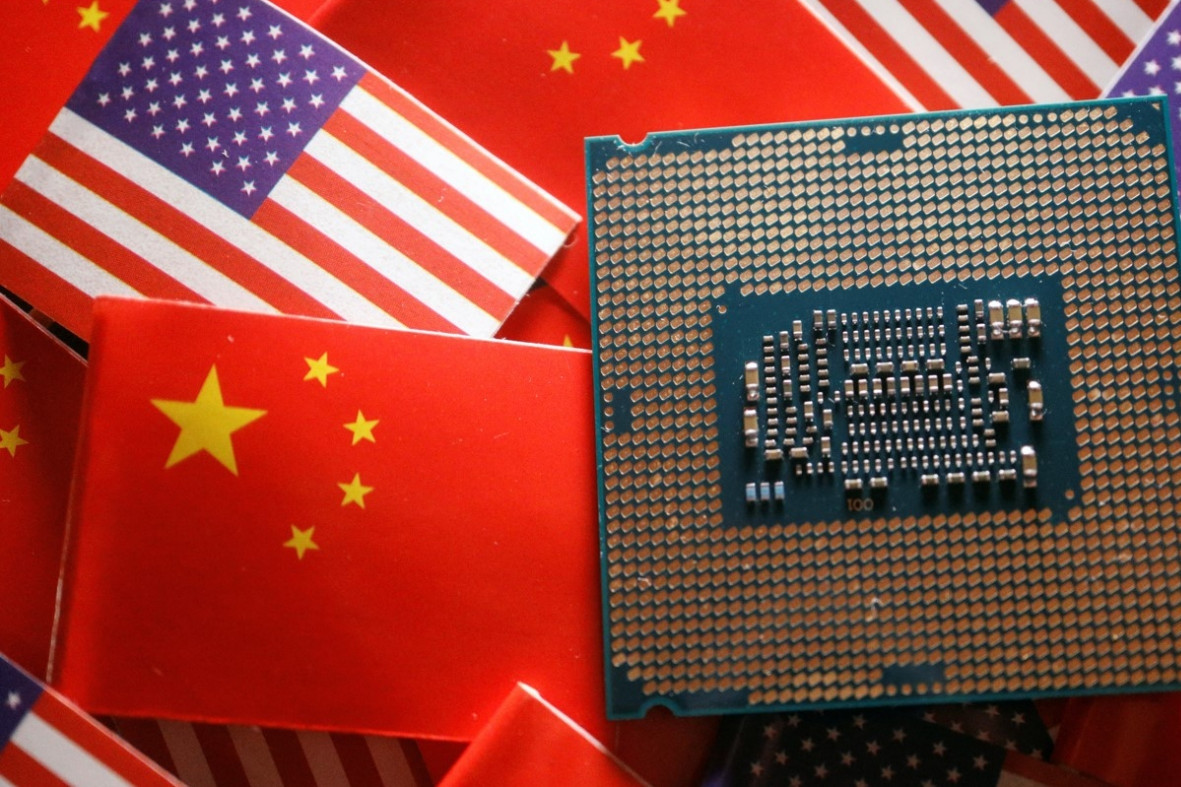
[広告2]
出典: https://vietnamnet.vn/nhat-ban-tham-hut-thuong-mai-ky-thuat-so-33-ty-usd-2294523.html




























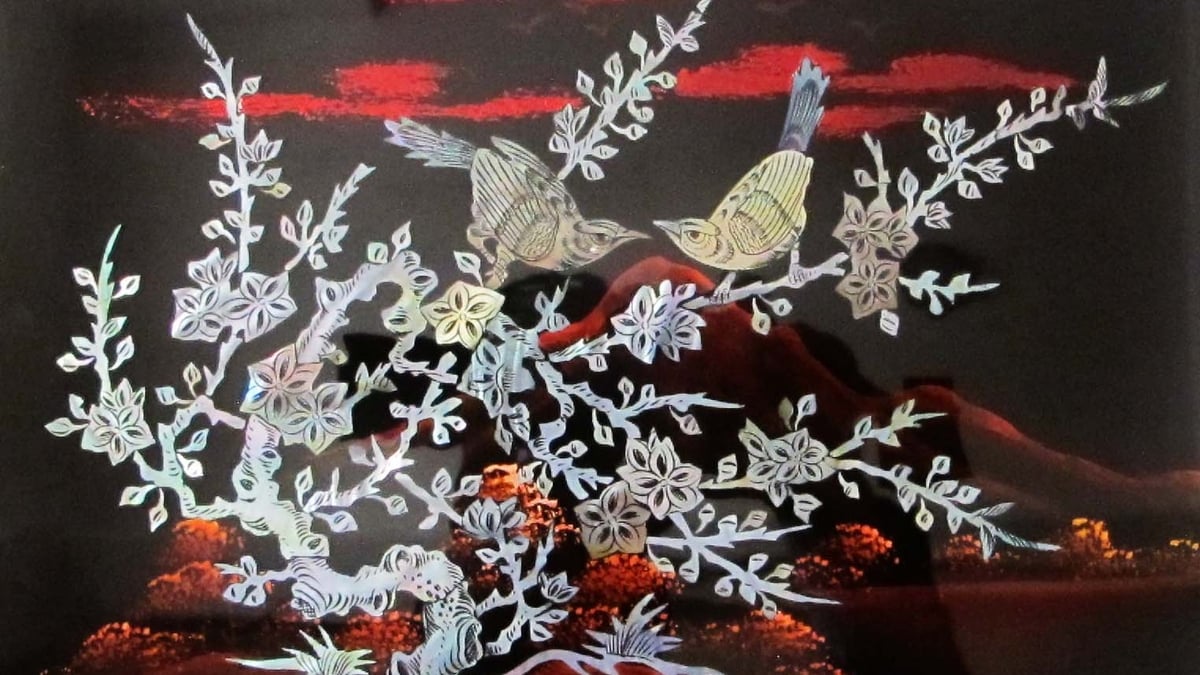









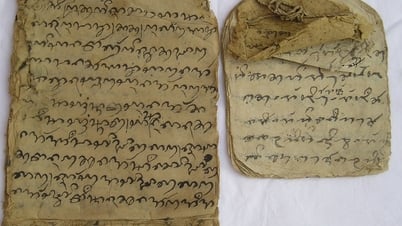





























































コメント (0)