この状況は、学習に対する社会の態度の変化と現在の教育支援システムの限界を反映しています。
文部科学省の最新の調査によると、2024年度に病気や経済的な理由以外の理由で30日以上学校を欠席した小中学生は約35万4千人に上りました。これは統計開始以来最多で、12年連続の増加となっています。
特に注目すべきは、学校を定期的に欠席する日本の生徒数がわずか5年間でほぼ倍増していることです。欠席率は全国の小中学生総数の3.9%に達し、そのうち90日以上欠席している生徒数は約19万2千人に達しており、この現象の深刻さを物語っています。
同省学生課の担当者は、適切なカウンセリングや心理的サポートを受けていない児童の数も増加しており、13万5,700件のケースが教育専門家や医療専門家に繋がれていないことから、状況は「極めて憂慮すべき」と述べた。これは、困難を抱える学生への支援体制が依然として限られていることを示している。
まず第一に、学習に対する社会の意識は変化しました。2017年に教育機会保障法が制定されて以来、オルタナティブスクールやホームスクールなど、従来の学校制度にとらわれない学習形態がより広く受け入れられるようになりました。同時に、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、多くの家庭が子どもたちが毎日学校に通わなくても学習できることに気づき、従来の学習モデルに固執するプレッシャーが軽減されました。
行きたくない子どもを無理やり学校に行かせるのは、心理的なストレスを増やすだけだと考える親もいます。しかし、こうした考え方こそが、学校が介入して支援を提供することを難しくしています。学校からオンライン学習やカウンセリングの依頼を受けても、多くの親は「子どもが学校に行きたくない」という言い訳をして拒否し、家庭と学校の間の溝が拡大してしまうのです。
二つ目の理由は、日本の教育制度が生徒の特別な支援ニーズに対応できていないことです。多くの生徒は日常生活への適応に困難を抱えていたり、発達障害に関連した特別な支援ニーズを抱えています。しかし、学校には専門的な支援スタッフや支援体制が不足しています。日常生活の不調による欠席が急増するとともに、特別な教育ニーズに関連するケースも増加しています。
欠席の増加を受け、一部の自治体では新たな支援モデルを導入しています。愛知県岡崎市では、学校内に支援学習センターを開設し、授業への出席が難しい生徒が柔軟なスケジュールで学習し、専門の教員からのサポートを受けられるようにしています。生徒の中には、センターのおかげで学習の軌道に戻れたと感じている人もいます。
「欠席が長期化すると、子どもたちは学習で遅れを取り、大人になって社会に適応するのが難しくなる可能性があります。学校は、欠席を支援することが長期的な解決策ではないことを理解する必要があります」と、東北大学で教鞭をとる後藤武敏准教授は述べています。
山口県光市では、メンタルヘルスの専門家と退職教員が週1~2回、生徒の自宅を訪問しています。このプログラムに参加した生徒の半数は、学校に復学したり、地域活動に参加したりできるようになりました。
出典: https://giaoducthoidai.vn/ty-le-hoc-sinh-nghi-hoc-tang-ky-luc-tai-nhat-ban-post755363.html



![[写真] ファム・ミン・チン首相が国際半導体製造協会(SEMI)の代表団を歓迎](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/06/1762434628831_dsc-0219-jpg.webp)









































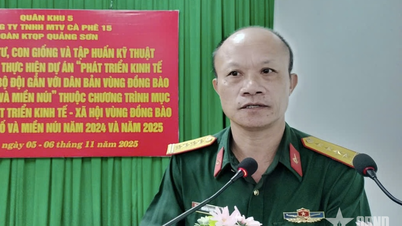







































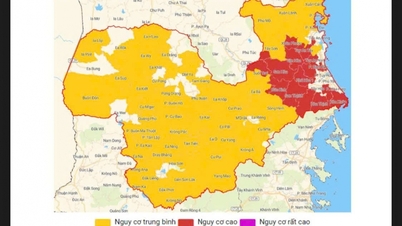





















コメント (0)