国家統計局のデータによると、2010年から2022年にかけて都市部の人口は継続的に増加している一方、農村部の人口増加率は長年にわたりマイナスかわずかな増加となっている。2010年には、都市部の人口は3.42%増加し、農村部の人口は0.28%増加した。2014年には、都市部の人口は4.88%と急増したのに対し、農村部の人口はマイナス0.64%の増加となった。2022年には、都市部の人口は2.15%増加したのに対し、農村部の人口はわずか0.3%の増加にとどまった。それに伴い、都市部の人口構成は2010年の30.4%から2022年には37.6%に増加した。これら2つの動向は、基本的に建設と都市化のプロセスによるものである(都市部の出生率は農村部ほど高くない)。
さらに、宮沢流経済人口動態モデルを用いると、注目すべき点がいくつか観察される。すなわち、農村住民の最終消費が都市所得に及ぼすスピルオーバー効果は、都市住民の最終消費が農村所得に及ぼすスピルオーバー効果よりも大きい(0.093対0.079)。政府消費支出(経常支出)も基本的に都市所得にスピルオーバー効果を示しており、この要因が都市所得に及ぼすスピルオーバー効果は、農村所得に及ぼすスピルオーバー効果の3.09倍である。
それに伴い、都市部と農村部の両方において、商品輸出単位が所得に及ぼす影響は非常に小さい。都市部では、基礎サービス輸出の所得への波及効果が農村部よりも大きいことが記録されている。都市部への商品輸出の波及効果が低いのは、農林水産物が加工産業の製品のように十分に加工されていないためである。これはまた、輸出農産物の高度加工率が非常に低いことも意味している。
全体として、農村部からの最終需要1単位の一般所得への波及効果の平均は、都市部からの最終需要1単位の波及効果の平均よりも高い(0.236対0.152)。農林水産業および農産物加工・製造業からの最終需要の大半は、農村所得への波及効果が平均を上回っている。
一般的に、農村部の最終消費の波及効果は都市部の最終消費よりも強く、農村部自身の生産額、付加価値、所得への波及効果をもたらすだけでなく、都市部の生産額、付加価値、所得にも非常に強い波及効果をもたらします。
したがって、都市化は経済の産業構造と連携して進める必要があることが分かります。本研究が、経営者が開発政策全般、特に経済政策を策定する際に、選択肢を検討する上で少しでも役立ち、ひいては国が速やかに包摂的な繁栄を達成できるよう願っています。
[広告2]
ソース












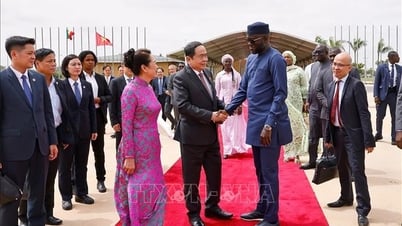






















































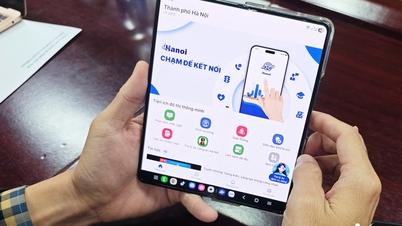























![ドンナイ省一村一品制への移行:[第3条] 観光と一村一品制製品の消費の連携](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762739199309_1324-2740-7_n-162543_981.jpeg)











コメント (0)