これは、資産価格の上昇が、米国GDPの70%を占める消費者の支出を刺激したためです。この富裕効果は過去15年間で著しく強まっています。

オックスフォード・エコノミクスの米国チーフエコノミスト、バーナード・ヤロス氏によると、株式資産が1%増加するごとに消費は0.05%増加するが、2010年にはわずか0.02%だった。同時に、住宅価格が1ドル増加するごとに消費は0.04ドル増加するが、これは以前の0.03ドルから増加している。
「家計は資産の増加を実感すると、個人財務への自信を深め、支出を増やす傾向があります。また、資産の増加は、住宅から資金を引き出したり、値上がりした株式を売却して現在の支出を賄うよう促す要因にもなります」とヤロス氏は報告書に記している。
労働収入がなくなった後も支出を維持するために蓄えた富に頼る退職者が増え、純資産額が増すにつれ、今後数年間は資産効果がさらに増大すると彼は予測している。
さらに、デジタルメディアの普及により、消費者心理は市場の変動に対してより敏感になり、「資産効果」がさらに強化されます。
この効果は、ドナルド・トランプ大統領が開始した貿易戦争によってインフレが高止まりし、企業が雇用に消極的になっているにもかかわらず、米国の消費が依然として底堅い理由を部分的に説明しています。一方、人工知能(AI)は、引き続き株式市場を史上最高値へと押し上げる主な原動力となっています。
同時に、Nvidia、Microsoft、GoogleなどのAI関連テクノロジー株が市場の柱となりつつあります。
ヤロス氏は自身のモデルに基づき、過去12カ月間のハイテク株の急騰により消費者支出が約2,500億ドル増加したと推定している。これは消費者支出全体の増加額の20%以上に相当する。
「株式市場は経済そのものではないが、経済はこれまで以上に市場の変動の影響を受けやすくなっている」と彼は警告した。
JPモルガンのアナリストも同意見だ。彼らの推計では、過去1年間で30銘柄のAI関連銘柄が米国の家計資産を5兆ドル以上増加させ、年間支出を約1,800億ドル(総消費の0.9%に相当)押し上げた。AIが他の株式や不動産などの資産にも浸透し続ければ、この数字はさらに上昇する可能性がある。
注目すべきは、株式投資がもはや富裕層だけのものではなくなったことです。ブラックロックとコモンウェルス・ファンズの調査によると、年収3万ドルから7万9999ドルのアメリカ人の54%以上が個人投資家であり、その半数は過去5年以内に投資を始めたばかりです。
しかし、依然として富裕層の支出が最も多い。ムーディーズの調査によると、2025年第2四半期の総支出の半分を所得上位10%の層が占めており、これは過去最高となる。
ペッパーストーンのシニアストラテジスト、マイケル・ブラウン氏は、これは株や不動産による資産効果と所得格差の結果だと述べた。
「これら全てを合わせると、高所得者層の裁量的支出への依存度が高まり、一方で高所得者層はリスク資産の安定性に依存する経済となっている」と同氏は述べた。
これは、金融政策を司る連邦準備制度理事会と財政政策を決定する米国議会の両方が、株式市場を支援するより強いインセンティブを持っていることを意味します。
なぜなら、「資産効果」は双方向に作用するからです。資産価格が下落すると、支出と成長も減速します。
「経済はますます株式市場との結びつきを強め、株式市場はますます個人消費への依存度を高めています。これら2つの要因が相まって、財政政策が引き続き支援的であり、金融政策がより緩和的になることで、リスク資産にとっての『安全クッション』が生まれています」とブラウン氏は結論付けました。
出典: https://thoibaonganhang.vn/fed-co-nhieu-dong-luc-hon-de-ho-tro-pho-wall-172942.html














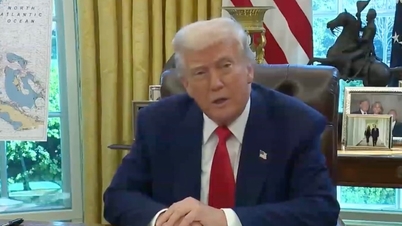
























![[写真] 2025年から2030年までのニャンダン新聞愛国模範大会のパノラマ](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762252775462_ndo_br_dhthiduayeuncbaond-6125-jpg.webp)
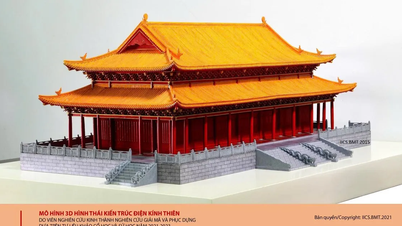











































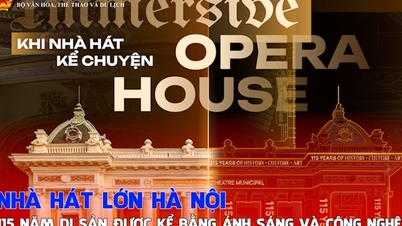



























コメント (0)