新学期を目前に控え、教科書を1セットにするか複数セットにするかという問題が再び論争を巻き起こしている。
ティエン・フォン記者は、この問題をより深く理解するために、リバプール大学(英国)、シンガポール国立大学で研究と研究を行ってきたウィーン工科大学(オーストリア)の工学物理学博士、ジャップ・ヴァン・ドゥオン博士にインタビューを行った。

残った教科書は、選ばれないため、遅かれ早かれ「残り物」となってしまいます。
親愛なるザップ・ヴァン・ドゥオン博士、国会決議第88号では、なぜ、教科書の多様性を確保しつつ、他の教科書は社会化され、基礎として国定教科書の作成が義務付けられているのでしょうか。
これは、「国家はあらゆる分野において主導的な役割を果たすべきである」という考え方を継承したものだと私は考えています。かつて国家は経済、文化、芸術、科学、教育などにおいて主導的な役割を果たしてきました。しかし、現在に至るまで、経済や文化芸術分野など、多くの分野で国家は主導的な役割を放棄し、国家による管理の役割を担ってきました。なぜなら、国家が管理に重点を置く方が、すべてを直接行うよりも効果的であることが現実に証明されているからです。
教育分野では、単に運営上の都合か、教科書編集の業務を出版部門に委託することの不安からか、「国家が主導的な役割を果たすべきだ」という意見が依然として多く支持されており、 教育訓練省に国定教科書の作成を担ってほしいという要望もある。
したがって、国定教科書作成の背後には、より大きな問題が潜んでいます。それは、国が教科書を直接作成する主導的な役割を果たすべきか、それとも教科書の評価や発行といった国家管理に重点を置くべきか、という問題です。これは単なる教育問題ではなく、国の統治政策に関わる非常に大きな問題です。
最近、「全国統一教科書の確保」という政策は「一教多教」の精神に反し、教師の自主性や創造性を損なうという意見があります。現行の3つの教科書のうち1つだけを統一的に使用すれば、私たちが懸念しているように、教師の「自主性」や「創造性」が損なわれるのでしょうか。
イメージしやすいように、例えば本を選ぶことをレストランで料理を注文することに例えてみましょう。一方は物理的な食事、もう一方は精神的な食事です。選択肢が多ければ多いほど、当然ながら自律性は高まります。また、どんな料理を選ぶにしても、意思決定においてより創造的な思考が求められます。レストラン側では、客に多くの料理を選ばせなければならない場合、創造性も高まります。
教育訓練省が標準教科書を制定した場合、他の教科書が「重複」してしまうのではないかという懸念はありませんか? そうなると、教師や生徒が教育訓練省の教科書を選ぶようになり、教科書編纂の社会化という目標が損なわれてしまうのではないでしょうか? 教科書の数はイノベーションの尺度となるべきでしょうか?
教育訓練省が国定教科書を制定する際、地方自治体は安全だと考えて国定の「教科書」を選ぶだろうと予測できます。残りの教科書は、選定も再版もされず、遅かれ早かれ「不要」と化します。やがて、私たちが選べる教科書は一つだけになるでしょう。
教科書の発行部数がイノベーションの尺度となるかどうかについては、比較対象がないため議論が難しい。言うまでもなく、イノベーションの尺度を議論する前に、どのような方向のイノベーションなのかを明確にする必要がある。
しかし現実は、どんな分野でも選択肢が多ければ、つまり競争があれば、すべてがより良くなるということです。例えば、航空会社が多ければ航空券が安くなる、電話サービスプロバイダーが多ければ料金が下がる、といったことは誰もが経験しているでしょう。プロバイダーが多ければ、製品やサービスの質は向上します。これは、私たちが日々目にし、経験している法則です。
現時点では教科書の再編集は必要ありません。
仮に教科書を単一セットに戻したいとしたら、どのようなプラス面とマイナス面があると思いますか?価格の独占、思考の独占、そして様々な地域や生徒グループに対する多様な指導法の導入などでしょうか?
教科書を1セットだけ使用することの利点は、教科書の評価と管理が容易になることです。また、地方自治体にとっても、教科書を選ぶ際に何も考えなくて済むため便利です。教師にとっても、その教科書セットに従って授業や試験対策を行えるため便利です。試験作成者にとっても、その教科書セットの内容と教材に従って問題を作成できるため、教科書以外の内容を探す手間が省けます。家庭にとっても、コース修了後に弟や妹に引き継いで再び学習させることができるため、新しい教科書を購入する必要がなくなります。つまり、あらゆる面で便利なのです!
しかし、これは個人が責任を負う必要がないという利便性であり、すべては国家が面倒を見てくれる。良いか悪いかは国家の責任だ。問題は、私たちはその利便性を選ぶべきなのか、ということだ。
教科書が1セットしかないことの最大のデメリットは、暗記と試験対策の傾向がすぐに再燃してしまうことです。観察してみると、今年の高校卒業試験の得点分布は非常に「美しい」分布で、正規分布に近づいています。なぜでしょうか?それは、高校3年生が初めて複数の教科書を学習する年であるため、試験問題は教科書以外の教材も活用する方向に作られているからです。そうすることで初めて、生徒が複数の異なる教科書を学習する際の公平性が確保されます。これにより、例年のような教科書に沿った暗記と試験対策が抑制され、生徒のレベル評価がより適切になり、前述の「美しい」得点分布につながっています。
価格、思考、教授法の独占については、懸念すべき理由があります。なぜなら、独占の前提条件は、選択肢、解決策、供給者がそれぞれ一つしかない場合だからです。実際に使用される教科書が一式しかない場合、教科書が複数ある場合よりも独占に陥る可能性がはるかに高くなります。
教科書の統一化を議論することが、現時点で最も重要な課題なのでしょうか?教育分野が現在解決すべき重要かつ緊急な課題は何だとお考えですか?
現行の教科書が本格的に使用されてからわずか1年で、すぐに教科書を作り直す必要はないと私は考えています。教科書は、結局のところ、2018年度の一般教育課程の表現形式に過ぎません。ですから、2018年度の教育課程をしっかりと実践し、特にAIが登場し、生活のあらゆる側面に浸透していく中で、実務上の進展に合わせてカリキュラムをアップデートしていくことに焦点を当てる方が効果的でしょう。
ありがとう!
ジャップ・ヴァン・ドゥオン博士は教育の専門家であり、ハノイ工科大学で工学の学位(1999年)、全福国立大学(韓国、2002年)で修士号、ウィーン工科大学(オーストリア、2006年)で工学物理学の博士号を取得し、リバプール大学(英国、2007~2010年)で博士研究員として研究を行った後、2010~2012年までシンガポールに戻り、シンガポール国立大学のテマセク研究所で研究を行いました。
2013年以降、ベトナムに戻り、教育・研修分野に専念しています。2015年には、アジア協会よりアジア21ヤングリーダーに選出されました。

IELTS Halo: 教育における不平等な競争?

一連の大学が標準スコアを発表:最高30/30ポイント
出典: https://tienphong.vn/nen-giu-nhieu-bo-sgk-de-tao-canh-tranh-guc-nhin-tu-chuyen-gia-giao-duc-ts-giap-van-duong-post1771391.tpo




![[写真] キンバックの土地への自然からの貴重な贈り物、ダン山人参](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F30%2F1764493588163_ndo_br_anh-longform-jpg.webp&w=3840&q=75)














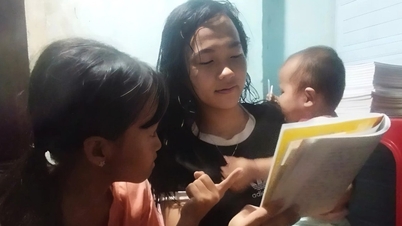















































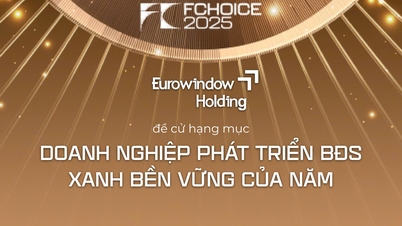




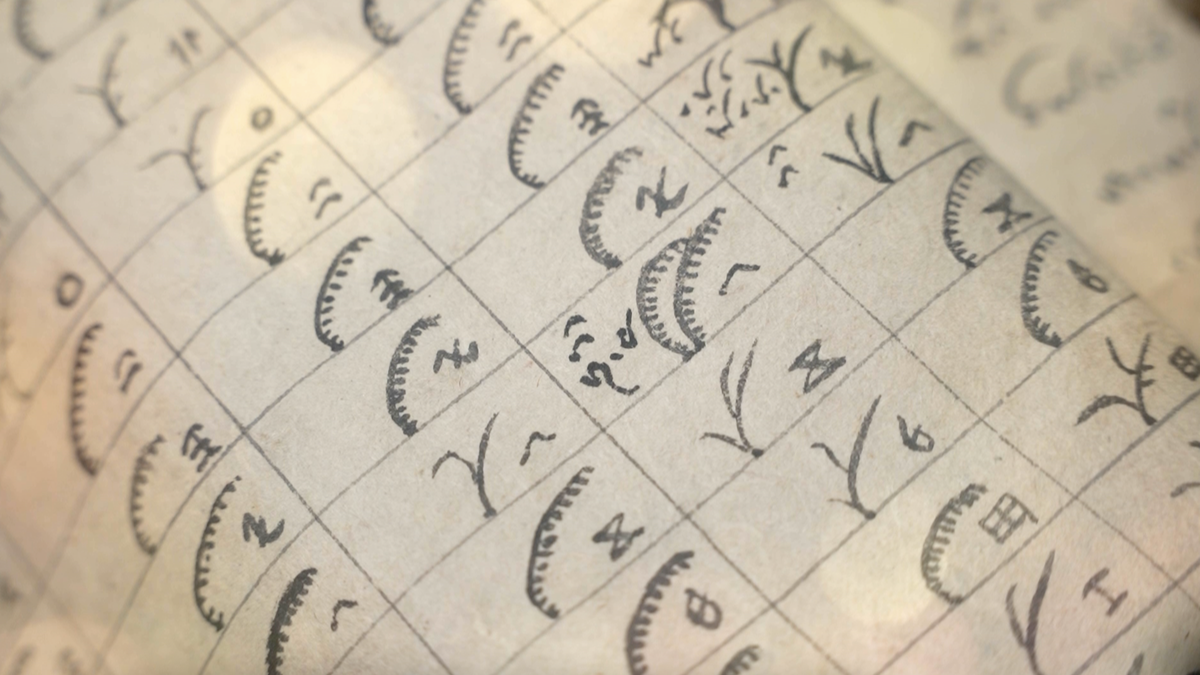


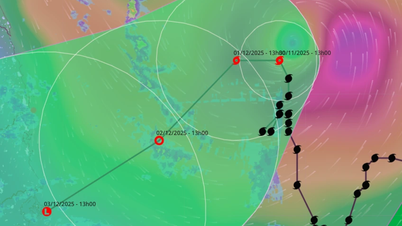






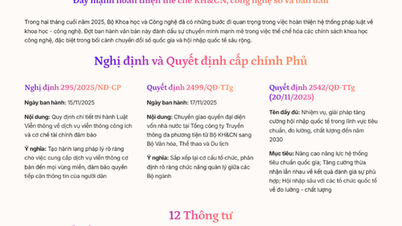



























コメント (0)