 |
| 中国は2023年に日本を抜いて世界最大の自動車輸出国となる。 |
具体的には、2023年に中国は490万台から520万台の自動車を輸出しており(統計による)、ライバルである日本の440万台を大幅に上回っています。
2017年以来、日本は世界の自動車製造業において一貫して「王座」を維持してきました。しかし、2023年には、電気自動車をはじめとする競争力のある自動車輸出によって、日本は中国にその座を奪われました。
日本を「超える」
日本自動車工業会(JAMA)が発表したデータによると、2023年の日本の自動車メーカーの輸出台数は、乗用車、トラック、バスを含めて前年比16%増の442万台と大幅に増加した。しかし、中国の自動車輸出台数と比較すると、この数字はまだ低い。
中国汽車工業協会(CAAM)によると、中国の自動車輸出台数は2023年に実際には491万台(57.9%増)に達し、1月初めに中国税関が発表したデータに基づくと522万台に達するという。
日本が世界最大の対中自動車輸出国としての地位を失うことは以前から予想されていたとされている。しかし、この問題は冷静に捉える必要がある。実際、日本企業の海外生産台数は国内生産台数の2倍(2022年には1,700万台)に達している。一方、中国メーカーは海外に工場を持つ数が非常に少なく、製品は現地販売よりも輸出が中心となっている。
そのため、販売面では、2023年は日本が4年連続で世界トップの自動車メーカーの地位を維持し、1月30日に発表された公式データによると、自動車の総販売台数は1120万台に達し、新記録を樹立することになる。
しかし、中国自動車メーカーの急速な拡大は、電気自動車で国内メーカーが遅れている日本と西側諸国の双方にとって依然として懸念事項となっている。
どの自動車会社にとっても手強い競争相手
アジア最大の電力大国である中国では、電気自動車が主要産業となっています。電気自動車のパイオニアであるテスラをはじめ、中国の電気自動車メーカーは、あらゆる自動車メーカーにとって最も重要な競争相手として台頭しています。
しかし、一部の批評家は、中国の電気自動車メーカーは10年以上にわたる継続的な政府補助金の恩恵を受けてきたと主張している。
欧州企業と中国の電気自動車メーカーの競争力への懸念が高まる中、欧州委員会(EC)は2023年9月、中国の電気自動車補助金に関する調査を発表し、調査で補助金が見つかった場合は高関税を課すと警告した。
2023年秋、欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長はためらうことなくこう宣言した。「現在、世界市場は安価な中国製電気自動車で溢れている。その価格は巨額の政府補助金によって人為的に低く抑えられているのだ。」
証券会社CLSAのアナリスト、クリストファー・リヒター氏はかつて、1980年代の西側諸国と日本の間の緊張に言及し、中国の自動車輸出の劇的な増加が「貿易摩擦を招いた」とコメントした。
この専門家によると、中国の自動車産業の現状は中期的には持続不可能な発展を示している。そのため、中国メーカーは、1980年代の日本の自動車メーカーのように、生産能力の増強と海外市場への輸出を迫られている。
例えば、中国最大の電気自動車メーカーであり、米国のテスラさえも追い抜いて世界一の電気自動車メーカーとなったBYDの場合。
2023年12月下旬、BYDグループは欧州市場をターゲットにハンガリーに工場を建設する計画を発表しました。さらに、BYDはブラジルにも工場を建設中で、最初の製品は2024年末までに市場に投入される予定です。さらに、近いうちに欧州に2番目の工場を建設する可能性があると発表しました。
フランスを含め、いくつかの国が中国の投資を誘致しようとしているが、スペインがターゲットとなっているようだ。
ロシアとの良好な関係のおかげで
中国の自動車輸出は、日本や欧米諸国に比べて明確な優位性、すなわちロシアとの良好な関係から恩恵を受けていることも特筆に値します。2023年には、ロシアとメキシコが中国車の輸入量が最も多い2つの市場となります。
ロシア・ウクライナ紛争が勃発し、西側諸国がロシアに厳しい制裁を課して以来、中国車のロシアへの輸出は急増し、西側諸国と日本の自動車メーカーはこの重要な市場から撤退を余儀なくされた。
さらに、中国の自動車輸出のすべてが国内ブランドというわけではありません。例えば、アメリカの電気自動車ブランドであるテスラは上海に「ギガファクトリー」を保有しており、そこでは製品は中国市場で販売されるだけでなく、輸出も行われています。しかし、輸出台数を計算する際には、これらの車も中国向けとしてカウントされます。
つまり、中国は世界の自動車市場、特に電気自動車市場において「支配的」な地位を築きつつあるのです。中国で生産される自動車は価格が安く、モデルも多様化しているため、顧客の注目を集めやすいでしょう。
[広告2]
ソース





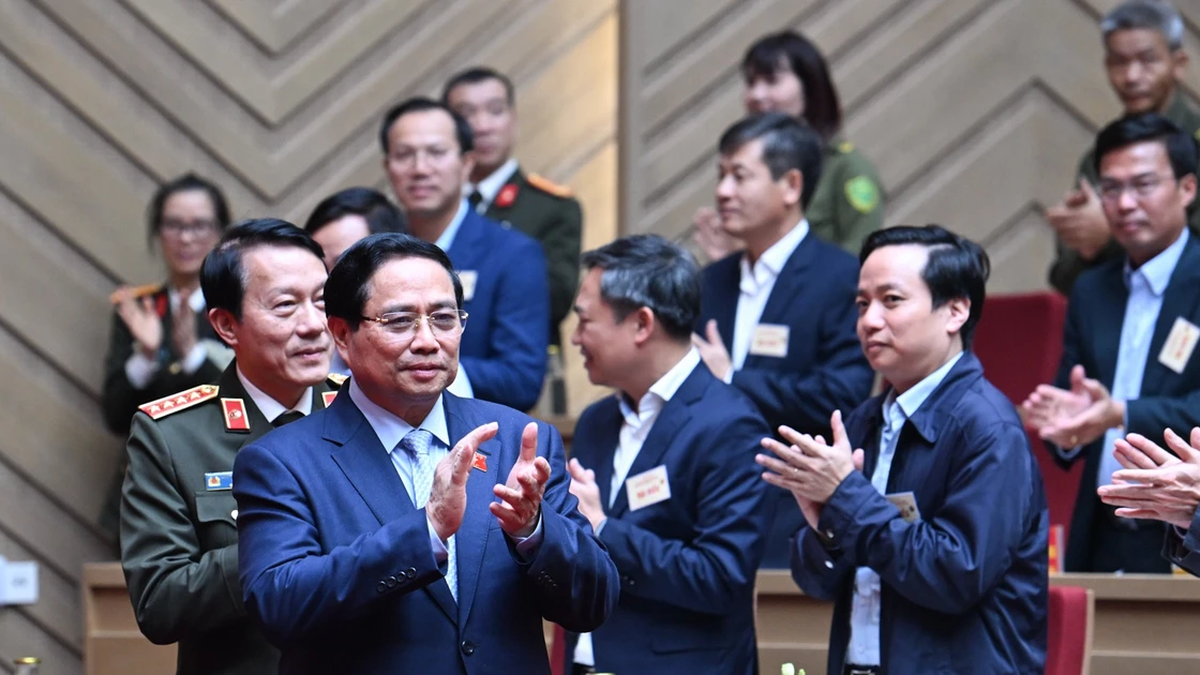
![[写真] 嵐と洪水後のダナンの山と森の「傷跡」](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/13/1762996564834_sl8-jpg.webp)















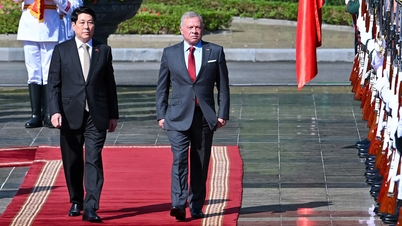













![[写真] ドンナイ省を通過する高速道路](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/12/1762940149627_ndo_br_1-resize-5756-jpg.webp)





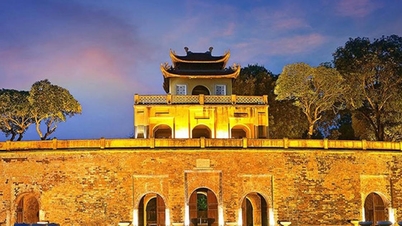


















































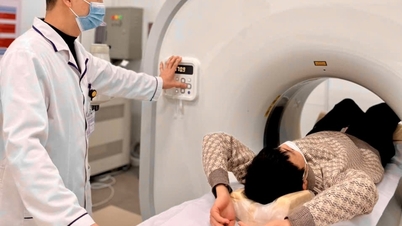












![ドンナイ省一村一品制への移行:[第3条] 観光と一村一品制製品の消費の連携](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762739199309_1324-2740-7_n-162543_981.jpeg)








コメント (0)