当時はまだ幼かったが、逆境によって同年代の若者よりも早く成長した。たくましい青年となった今でも、彼はこう問い続けている。「神はいつになったら私を試さなくなるのだろう?」
両親は貧しく、結婚した当時は愛情しか持っていませんでした。祖父は彼らを哀れみ、田んぼの端に小さな土地を与え、仮の家を建てさせました。幸いにも両親は働き者だったので、畑仕事で裕福ではなかったものの、食べるもの着るものには事欠きませんでした。3歳の10月のある午後、彼女はたくさんの人が家に来るのを見ました。皆、悲しそうな顔をしていました。祖母は何度も気を失い、祖父は深く生気のない目で彼女を強く抱きしめました。それから人々は彼女の母と妹を家に連れてきました。その朝、父は彼女に、母を出産に連れて行くように言いました…
それ以来、彼は祖母と暮らした。父は、まるで大きな苦しみを忘れるかのように、仕事に打ち込んだ。祖父母と父は彼を心から愛していたが、それでも彼は何か神聖なものが欠けていると感じていた。歳を重ねるにつれ、喪失感と悲しみは増していった。
母の命日が幾度となく過ぎ、ある日叔母は父の元へ帰ってきた。祖父母から幾度となく囁かれる言葉を聞いていた叔母は、誰も一生一人で生きられないことを、特に父がまだ幼かった頃はよく分かっていた。しかし、市場の叔母やおばあちゃんたちの何気ない言葉が、叔母を少し怖がらせた。「お餅に骨なんてないよ…」
叔母はいつも彼を引き寄せようとしていたが、彼はいつも叔母と距離を置いていた。市場へ行くために叔母の自転車に油を塗るのに苦労している父親の姿、叔母が父親に油を塗っている姿、夜に耕作から帰ってくる父親を待ちながらご飯とスープを温めるのに苦労している姿を見ると、彼は何度も叔母にひどい嫌悪感を抱いた。彼は叔母を「叔母」と呼び、自分の心の中で叔母がどんな存在なのかを優しく思い出させようとした。時には叔母の世話に無関心になり、父親に厳しい声で叱られることもあったが、叔母はいつも彼を擁護した。「やめなさいよ、弟よ。あの子はまだ小さいのよ…」。そんな時、彼は叔母を、母親の温もりを切望して眠れない時に祖母が読んでくれた童話の継母と何ら変わらない存在だと考えていた。

イラスト:AI
叔母の妊娠を知って以来、彼の心の中の恐怖と憤りは募るばかりだった。叔母と妹にしがみつく父の姿を見て、彼は果てしなく自分を憐れんだ。父は何度も父を探しに行き、母と妹の墓のそばに横たわる父を見つけた。
- なぜ私を受け入れてくれないの?本当にあなたを愛しているのに。
お父さんの声は低く、自分の無力さを隠しきれなかった。
- …
彼は黙ったままだった。なぜなら彼自身が父親に自分の気持ちを説明できなかったからだ。
父は予期せぬ時に病に倒れ、学校を中退して南部へ仕事を探しに行くことを決意した。知人の紹介で塗装の仕事を学び、自力で最初の収入を稼ぎ始めた。その後数年間、父が家に帰ったのは母の命日と旧正月の二度だけだった。母と離れて暮らすようになってからは、母以外の女性が父と一緒にいることをそれほど気にしなくなったようだった。
彼女は、彼が家に電話するたびに父親にメッセージを送って、いつも彼を気遣っていました。
- 何か食べたいものはないかと聞いたので、作って送ります。
- お子さんに薬を買ってくるように言いなさい。病気だって言ってたのに。
- もう家にお金を送るのはやめて、誰かと一緒に仕事に行くために車を買うお金を貯めなさいと言ったでしょう。
- …
何でも聞いて、何でも知っている、ただ…幼いころから築き上げてきた見えない壁を、まだ越えられない。
- タイガー、今すぐ家に帰りなさい。お父さんが病院にいるんだ!
電話で祖父の切迫した声が聞こえたので、彼はすぐにやっていたことを中断し、急いで荷物をまとめて、帰りの切符を買うためにバス停へ行きました。
病室の窓から中に入ると、叔母が座って父の顔を拭いているのが見えた。彼女はひどく痩せ衰え、やつれていた。叔母に会ってから随分経っていた。一度も目の前に立って、まっすぐに目を見つめたことがなかったのだ。
父は数日後に亡くなりました。父と過ごした最後の数日間、彼女は叔母との間にあった壁が崩れ去ったように感じました。心の中に、叔母への愛と憐れみが突然湧き上がりました。しかし同時に、かつてないほど孤独で孤立しているように感じました。今、彼女は野生の木と何ら変わりなく、この世界でたった一人ぼっちになっていました。
リュックサックを背負って南へ帰る日、彼は叔母と食事をする代わりに、祖母の家へ別れを告げに行く口実を作った。実は、叔母を避けようとしていたのだ。叔母の深く悲しげな瞳を見つめる勇気が、同じ父を持つ妹に別れを告げる強さが、父の肖像画に映る遠い目を前にして、自分をコントロールできないのではないかと恐れていた。自分は男の子なんだから、強くならなきゃ!と自分に言い聞かせた。風の音の中、叔母の声がかすかに聞こえた。「息子よ、自分のことは自分でやりなさい。私と妹のことは心配しなくていいのよ。」
まだ暗いうちにバスが駅に停まった。彼はゆっくりと職場へ向かい、門の外に座って待った。この時間はまだ皆寝ているので、邪魔したくなかった。ふと、叔母のことを思い出した。きっと夕食を作り、市場に持っていく野菜の準備のために朝早く起きているのだろう。バイクの乗り方も知らない叔母は、市場までどれくらい時間がかかるのだろう。父がいなくなったら、叔母と弟はあの家の空虚な空間をどう乗り越えるのだろう。叔母がかわいそうに思えた。
幼い頃に母親を亡くし、成人してから父親を亡くしたため、これまで何に対しても涙を流したことのない少年だったが(母親は彼があまりにも早く亡くなり、父親は彼がすでに成人してから亡くなったため、彼は涙を無理やりこらえなければならなかった)、今は幼い頃から憎んでいた女性のために涙を流していた。叔母の愛情を受けるために心を開いていなかったことを後悔し、熱があるときに叔母がそっと濡れタオルを当ててくれたときに不用意にその手を払いのけたことを後悔し、市場に行くのが叔母にとって楽になるようにバイクの乗り方を教える時間がなかったことを後悔した…。彼は携帯電話を取り出し、今までしたことのないことをした。叔母の番号にダイヤルし、無事に到着したことを伝えるため電話をかけたのだ。電話越しに叔母の安堵のため息を聞き、彼は急に幸せで安心した気持ちになった。
- タイガー、来週はお父さんの命日だけど、帰って来れる?
「ええ、今年は早く帰ってきます。帰ってきてから市場に連れて行って、買い物させてください!」
田舎へ帰るバスの窓から、彼は小さな家族が散歩に出かけるのを見た。小さな子供は真ん中に座り、父親の腰に腕を回していたが、顔を向けて母親に何かを伝えようとしているようだった。すると家族全員が大声で笑った。小さな家の台所から煙が上がっているのが見えた。その家は田舎の自分の家に似ていたが、確かにもっと暖かく、より充実したものだった。突然、叔母のことを思い出し、彼の心は沈んだ。父親が亡くなってから何年も経ち、叔母は弟を育てるために一人で暮らし、彼の帰りを待っていたのだ。
今年も雨季が近づいてきた。今年は貯金を全て使い、叔母と弟のために、もっと広くて頑丈な新しい家を建てるつもりだった。もちろん、叔母のためにできる最も近いことは、約束通り、父の命日の準備のために市場へ連れて行くことだった。叔母に愛の言葉を伝える勇気はまだなかったが、叔母は自分がどれほど愛しているかを知っているはずだと信じていた。耳元で誰かが子守唄を歌っているのが聞こえた。「骨付き餅の代々は…」。彼はふと微笑んだ。

出典: https://thanhnien.vn/xuong-banh-duc-truyen-ngan-du-thi-cua-ha-my-185251026220022318.htm




















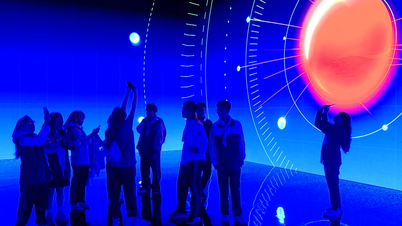













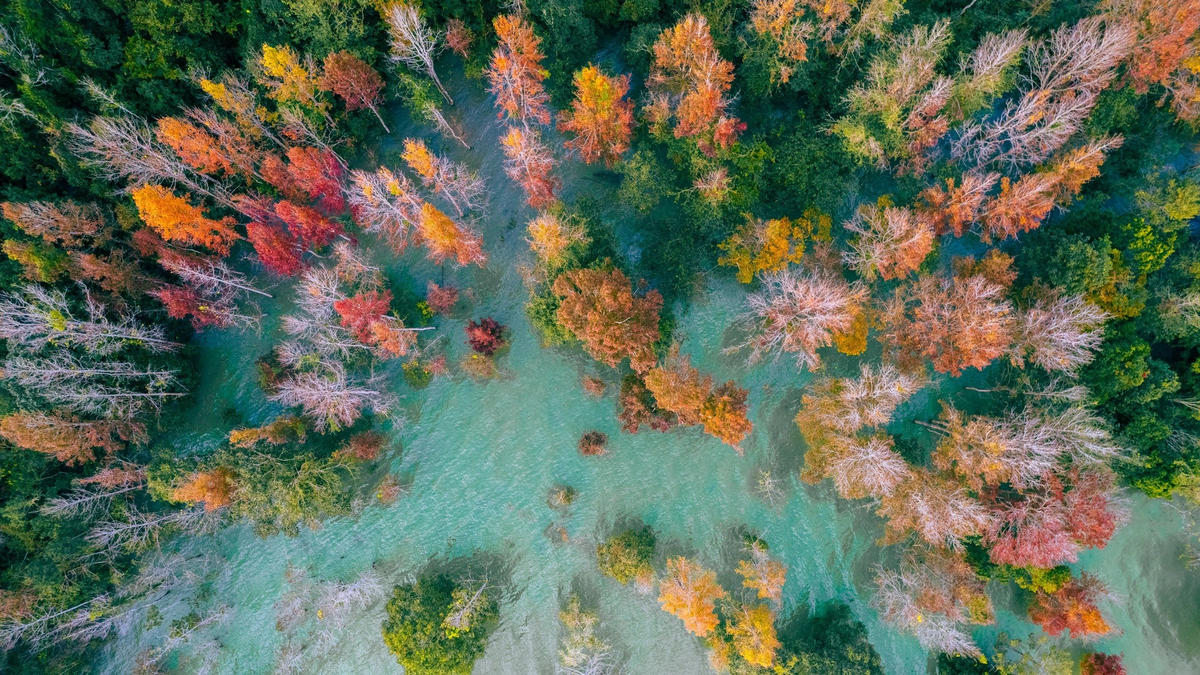

























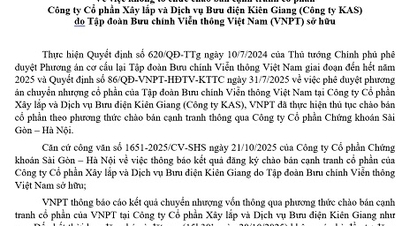















































コメント (0)