
柔軟な家族控除は適切でしょうか?
ハノイ在住のフリーランス、ミンさんはこう語りました。「現在の扶養家族控除は月額わずか440万ドンで、高校生の子供3人と高齢の両親を育てなければなりません。しかし、私の収入は最低限の生活費を賄う程度で、さらに税金も支払う必要があるため、生活が非常に苦しく感じています。扶養家族控除が増額されれば、経済的な負担が軽減され、仕事にもっと集中できるようになります。」
ミン氏の事例は珍しくありません。ハノイやホーチミン市のような大都市では生活水準が高い一方、 バクニン省やラオカイ省といった地域では、家族控除が生活費の上昇に追いつかず、税制の運用に不平等が生じています。
国民経済大学銀行金融研究所副所長のファン・ヒュー・ギ准教授はラオ・ドン氏に対し、収入と生活費が急速に変化している状況では家族控除額の調整が必要だが、提案されている1,330万~1,550万ドンという額は実際の収入と生活費を完全に反映していないと語った。
ギ氏はさらに、ベトナムは中所得国であるため、個人所得税を全国民に拡大することは不可能だが、平均所得以上の層に重点的に課税する必要があると付け加えた。したがって、控除額の決定は、一人当たりの平均所得や生活費だけでなく、現在、大多数の賃金労働者が抱える最も一般的な所得水準という重要な要素も考慮する必要がある。
グエンチャイ大学金融銀行学部長のグエン・クアン・フイ氏は、「現在の控除額は時代遅れです。都市部における教育、医療、住宅、エネルギーなどの実際の費用は消費者物価指数(CPI)よりも大幅に上昇しており、1,330万~1,550万ドンという水準ではこの上昇率に追いついていません」とコメントしました。
フイ氏は、法改正を待つのではなく、控除額の調整を消費者物価指数(CPI)と国民所得の中央値に連動させ、毎年自動的に調整できるようにする必要性を強調した。「さらに、現行の地域最低賃金規制のように、例えばホーチミン市とハノイの控除額は地方よりも高いといったゾーニングの仕組みも検討すべきだ」とフイ氏は述べた。
専門家によると、過去5年間で生活費は大幅に上昇しており、特にハノイ、ホーチミン市、ダナンなどの大都市で顕著です。都市部と農村部の生活費の差はますます顕著になっており、住宅費、教育費、医療費、光熱費といった生活必需品の支出が急増しています。
例えば、ホーチミン市やハノイに住む家族は、生活費が山岳地帯の何倍も高く、基本的な生活費だけでも平均で月約4,000万ドンを支出する必要があります。一方、最大1,550万ドン/月の家族控除では、これらの家族の税負担を軽減するには不十分です。
国家統計局の最近の報告書によると、2024年の空間生活費指数(SCOLI)は、一定期間における省と中央直轄都市、社会経済地域間の人々の日常生活を支える商品や消費者サービスの価格差を反映している。この報告書によると、合併前は南東部地域が2024年のSCOLI指数が100.37%で、国内で最も物価が高い地域であった。2位は紅河デルタ地域で100%、次いで北部ミッドランド・山岳地帯が99.98%、北中部・中央海岸が99.05%、中央高地が97.69%、メコンデルタが97.11%であった。
この指標は、同じ所得水準でも支出や経済的負担が異なることを示しています。したがって、地域別の家族控除の適用にも、それなりの合理性があると考えられます。
専門家は、全国一律の控除額を適用するのではなく、各地域の実際の収入と支出に応じて世帯控除額を調整することを提案している。これは、現行の地域最低賃金政策が適用されているため、地域最低賃金を基準とすることができる。ハノイ市やホーチミン市などの大都市の納税者と扶養家族の世帯控除額は、山岳地帯や遠隔地よりも高くなる。
財務省はどう説明するのか?
国会常任委員会の家族控除に関する決議案提出において、財務省は次のように述べた。「個人所得税法(PIT)は、納税者本人に対する控除と、納税者が扶養しなければならない扶養家族に対する控除を規定している。この規定は、納税者の具体的な状況を考慮した「公平性」と「納税能力」の原則を反映している。すなわち、高所得者はより多くの税金を納め、同様の状況でも扶養家族が多い者はより少ない税金を納め、低所得者は税金を納める必要がない。」
財務省は、「最近、家族控除額がまだ低いとの意見があり、また、地域最低賃金に応じて家族控除額を規制する必要があるとの意見もある。都市部や大都市の家族控除額は、物価が高いため、農村部や山間部よりも高くする必要があるとの意見もある。また、大都市への移住を制限するために、都市部や大都市で税制を高く規制しているという意見もある。」と述べた。
これらの意見を踏まえ、財務省は次のように見解を表明した。「納税者の個人所得税率は、所得の高低、消費ニーズの相違、居住地域の違いを問わず、社会全体のレベルに応じた特定の税率である。先進国、発展途上国を含む各国の個人所得税法は、地域や人口階層による区別なく、一律に適用される一般的な個人所得税率のみを規定している。」
個人所得税法では、困難な地域で働く個人に対し、当該地域への就労支援や就労者の誘致を目的として支給される地域補助金、誘致補助金、移転補助金等について、所得税の課税対象とならない旨が規定されています。また、自然災害、火災、事故、重篤な疾病等により就労に困難をきたした個人に対しては、所得税の減免措置が規定されています。
財務省は、「付加価値税率は、一人当たりの平均GDP、地域の最低賃金、一定期間の一人当たりの平均支出よりも高くなるように、慎重に調査・計算する必要がある」と述べた。
グエン・ゴック・トゥ博士は、草案にあるように2026年まで待つのではなく、家族控除を月額1,800万ドンに引き上げ、2025年から適用することを提案した。 ラオドン紙のインタビューで、ビジネス・テクノロジー大学のグエン・ゴック・トゥ講師は、家族控除を納税者本人は月額1,800万ドン、扶養家族1人につき月額900万ドンに引き上げるべきだと提案した。この水準は、特に2020年以前と比べて生活費が大幅に上昇している都市部において、労働者の実際の支出に近いため、多くの専門家から支持されている。 杜博士が強調したもう一つの重要な点は、適用時期です。草案によると、新しい家族控除制度は2026年度から適用される予定ですが、杜博士はそれよりも早い2025年から適用すべきだと考えています。 「技術的には、2025年の個人所得税は2026年4月まで確定しません。したがって、2025年に適用される控除額を調整することは、実施に何の障害もなく、完全に実行可能です」と彼は分析した。 |
出典: https://baoquangninh.vn/bo-tai-chinh-ly-giai-viec-khong-giam-tru-gia-canh-theo-khu-vuc-nhu-luong-toi-thieu-vung-3368445.html





![[写真] Action for the Communityは、親密で壮大でありながら、静かで決意に満ちた永続的な旅の物語を伝えています](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763179022035_ai-dai-dieu-5828-jpg.webp)






























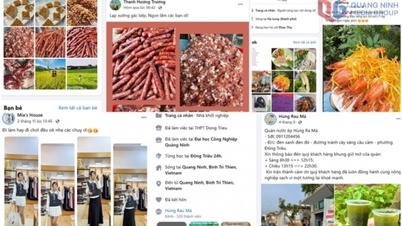

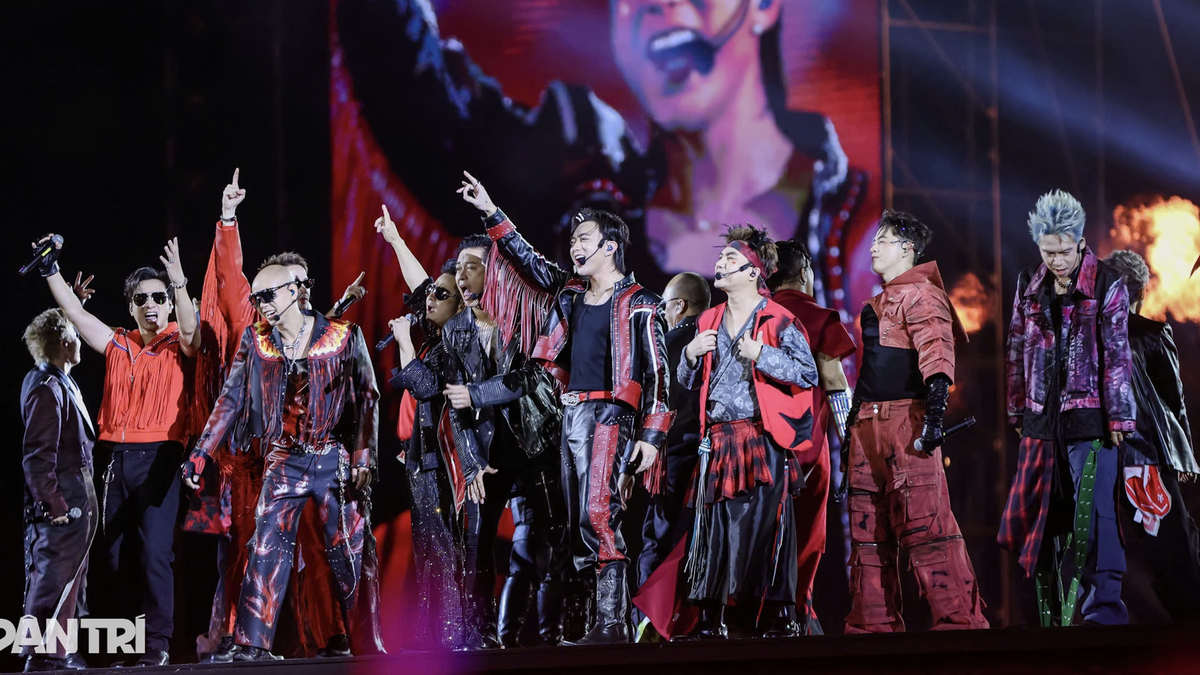









































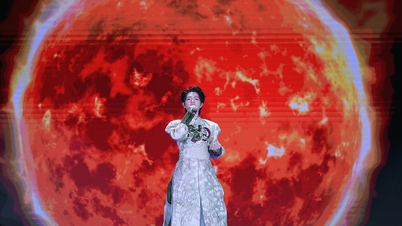
































コメント (0)