「カレー」の語源には2つの説があります。1つは、ヒンディー語の「カダヒ」または「カラヒ」(कड़ाही)に由来するという説です。これはパキスタンやインドで、肉、ジャガイモ、お菓子、サモサやシチューなどの軽食を炒めるのによく使われる深い円形の鍋です。もう1つは、英語の「カリー」の翻訳で、インドのタミル・ナードゥ州と連邦直轄領のプドゥチェリーで話されているドラヴィダ語族のタミル語の「カリ」(கறி)に由来するという説です。
我々の見解では、カレーはヒンディー語の「カラヒ」(कड़ाही)に由来するものではない。なぜなら、「カレー」という言葉は通常、カレー粉(スパイスの混合物)を使った料理を指し、料理を調理する鍋を指すものではないからだ。さらに、ベトナム語では、「カレー」という言葉は英語の「curry」ではなく、フランス語の「curry」または「cari」に由来する。例えば、19世紀末以降、「カレー」という言葉は、1889年にImprimerie de la Mission社から出版された、ボン(Co Ban)とドロネ(Co An)という二人の宣教師による『 Manuel de conversation Franco - Tonkinois(ファランサ語とアンナム語の会話集)』の135ページに登場している。
しかし、フランス語の「curry」または「cari」という単語は英語からの借用語であり、英語の「curry」は「ソース」または「ご飯にかける調味料」という意味で、カレーノキ(Bergera koenigii、別名Murraya koenigii)の葉から作られる。この用語は17世紀半ばにイギリス人によって造られ、インドのタミル人と貿易を行っていた東インド会社のメンバーによって生まれた。
英語の「カレー」という言葉は、タミル語の「カリ(கறி)」に由来するという説があります。カリ(கறி)は多義語で、「魚、肉、または野菜を混ぜたスパイスで、ご飯と一緒に食べる」という意味を持つほか、タミル語のサンガ(சங்கநூல்களி)の聖典では「コショウ」という意味も持ちます。動詞として使われるカリ(கறி)には、a. 噛む、かむ、b. 生または茹でた野菜、c. 茹でたまたは生の肉、という3つの意味があります。
タミル語では、カレーリーフの名前はカリヴェンプ (கறிவேம்பு) で、カリヴェッピライ (கறிவேப்பிலை) およびカルヴェッピライとも呼ばれます。 (கருவேப்பிலை);木の名前はムラヤ・コエニギイ(முறயா கொயிங்கீ)です。
インドにはカレーと呼ばれる料理が数多くあり、通常はベジタリアン(野菜、植物、蔓などから作られる)とノンベジタリアン(肉、魚から作られる)の2つのカテゴリーに分けられます。タミル語では、カレーの名称は調理方法によって異なります。例えば、油で調理した場合はヴァタカル(வதக்கல்)、茹でたレンズ豆で調理した場合はポリヤル(பொறியல்)、タマリンドで調理した場合はプチカリ(புளிக்கறி)、同量のナッツ類とレンズ豆の粉で調理した場合はウジリ(உசிலி)などです。茹でたレンズ豆をタマリンドと混ぜたものは、マチヤル (மசியல்) とも呼ばれます…
世界には様々なスパイスを使った様々なカレー(ドライカレーとウェットカレー)があります。ベトナムでは、ココナッツミルク、ジャガイモ、野菜、イモ類、肉などからカレーを作ることが多いです。ベトナム人はパン、麺類、ご飯と一緒に食べることが多いです。
今日では、英語の「curry(カレー)」という言葉は世界中で広く使われており、日本人はそれを借用して「karē(カレー)」、韓国人は「keoli(ケオリ)」、中国人は「gālí(ガリ)」と呼んでいます。この言葉は南アジア諸国にも逆輸入され、イギリス人と同じように理解されています。しかし、インドでは「kari(カリ)」という言葉は、グレービーソース、プレッツェル、ダル(特にレンズ豆)、ほうれん草、フィッシュカレーなど、様々なサイドディッシュを指すようになり、ご飯と一緒に食べることもよくあります。
[広告2]
ソースリンク


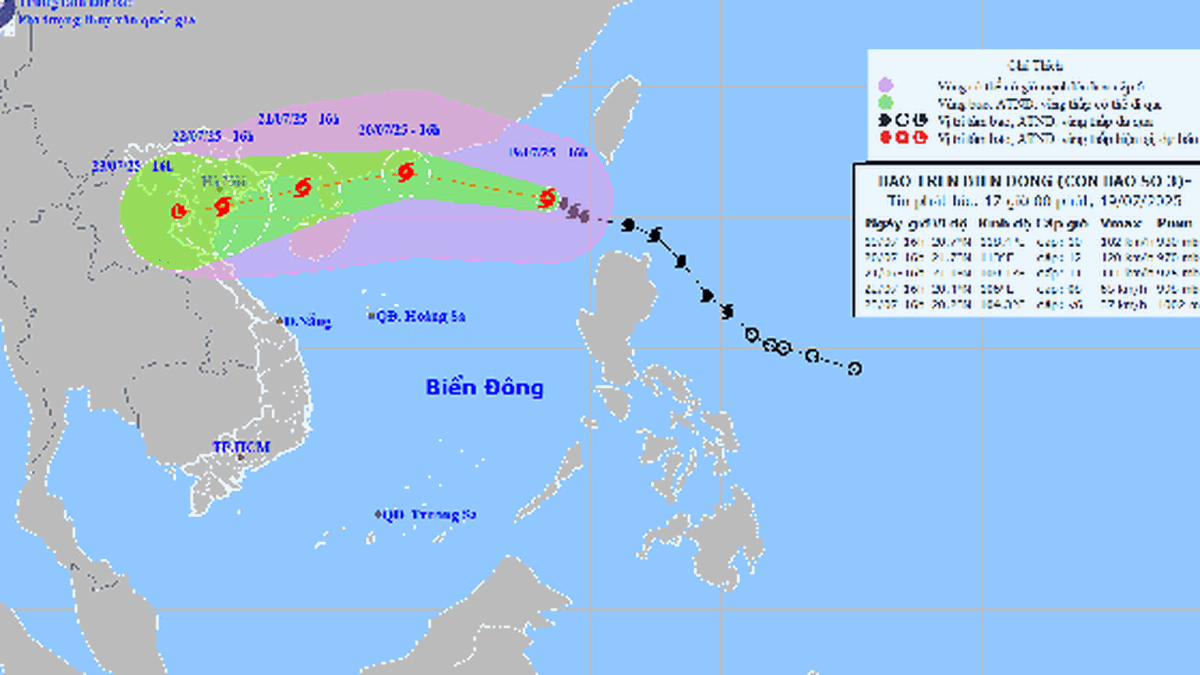


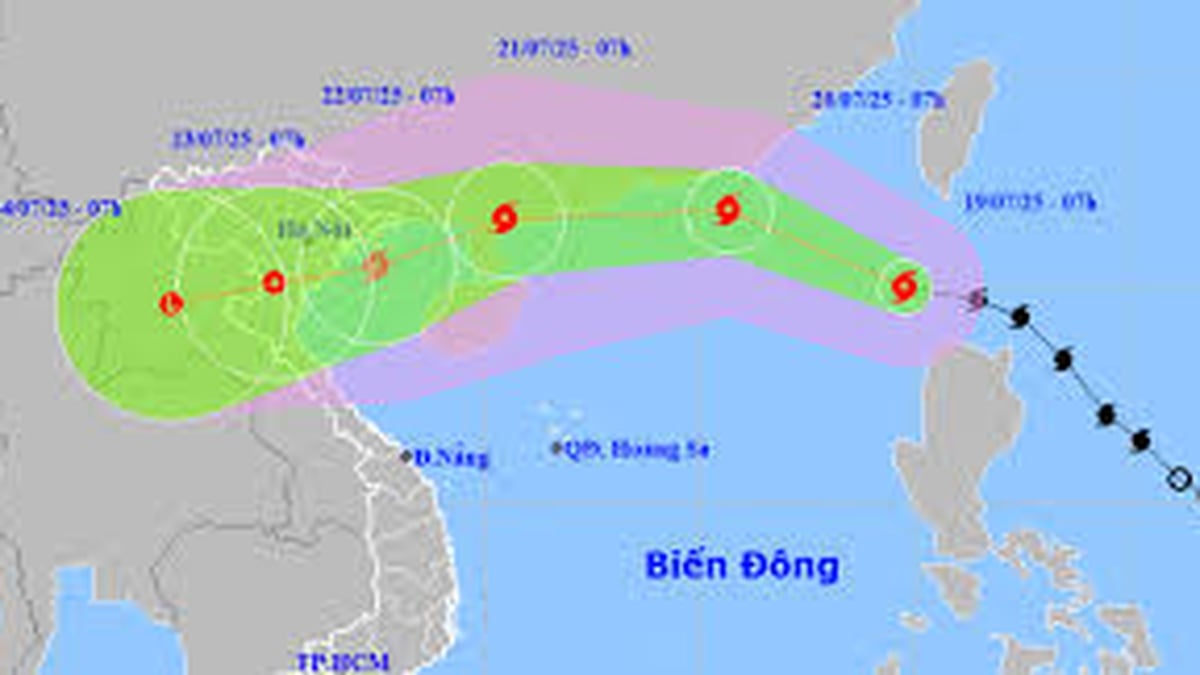
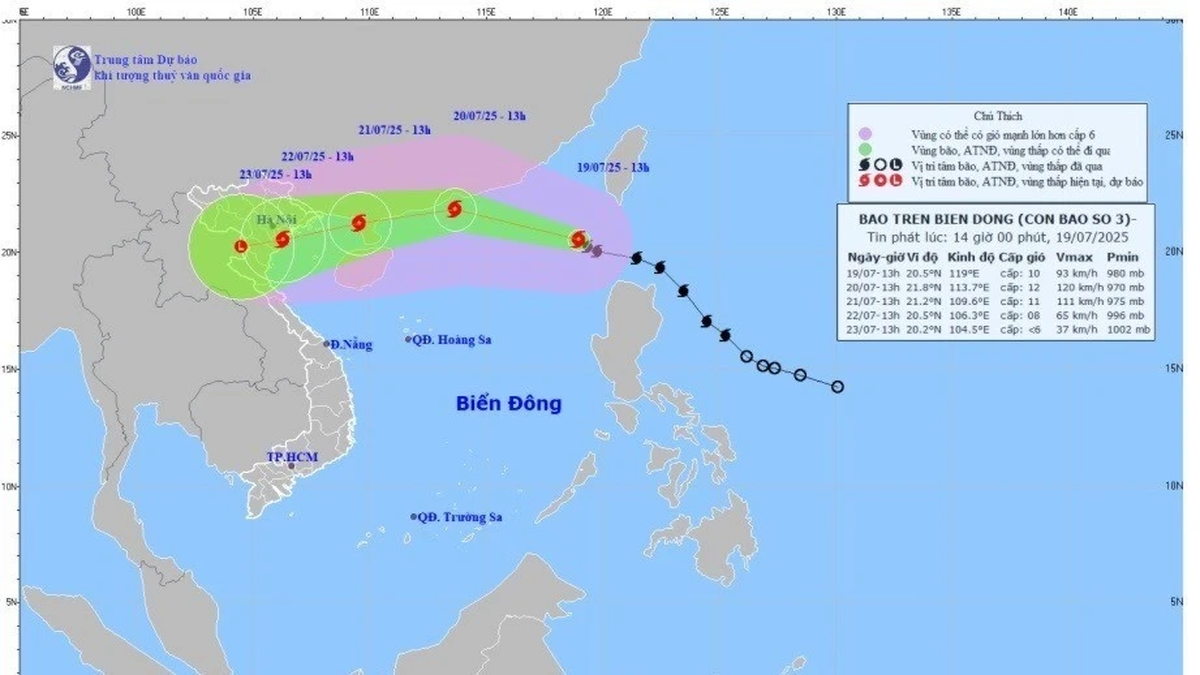










































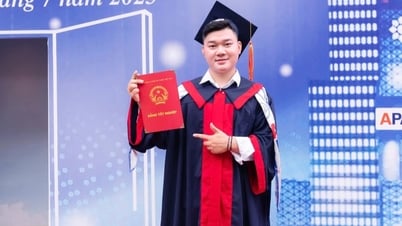
















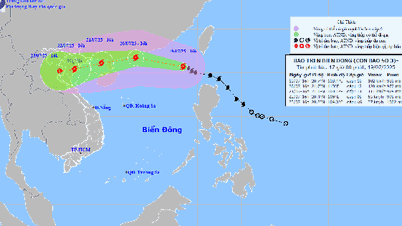































コメント (0)