すべての人のためのルール
2018年ノーベル文学賞を受賞したポーランドの作家オルガ・トカルチュクは、小説『ビエグニ 動き続ける人々』の中で、 bieg (走る)とucieczka (逃げる)を組み合わせた架空の宗教「ビエグニ」について書いています。彼らは動くことで悪を征服する人々です。彼らは、静止している時でさえ常に動いています。なぜなら、「 世界の支配者は動きを制御できず、私たちの体は動くことで神聖になり、動くことでのみ彼から逃れることができることを知っているからです。そして彼は、動かず麻痺したもの、受動的で停滞したものを支配するでしょう」。

作家グエン・ゴック・トゥと短編集『漂流』
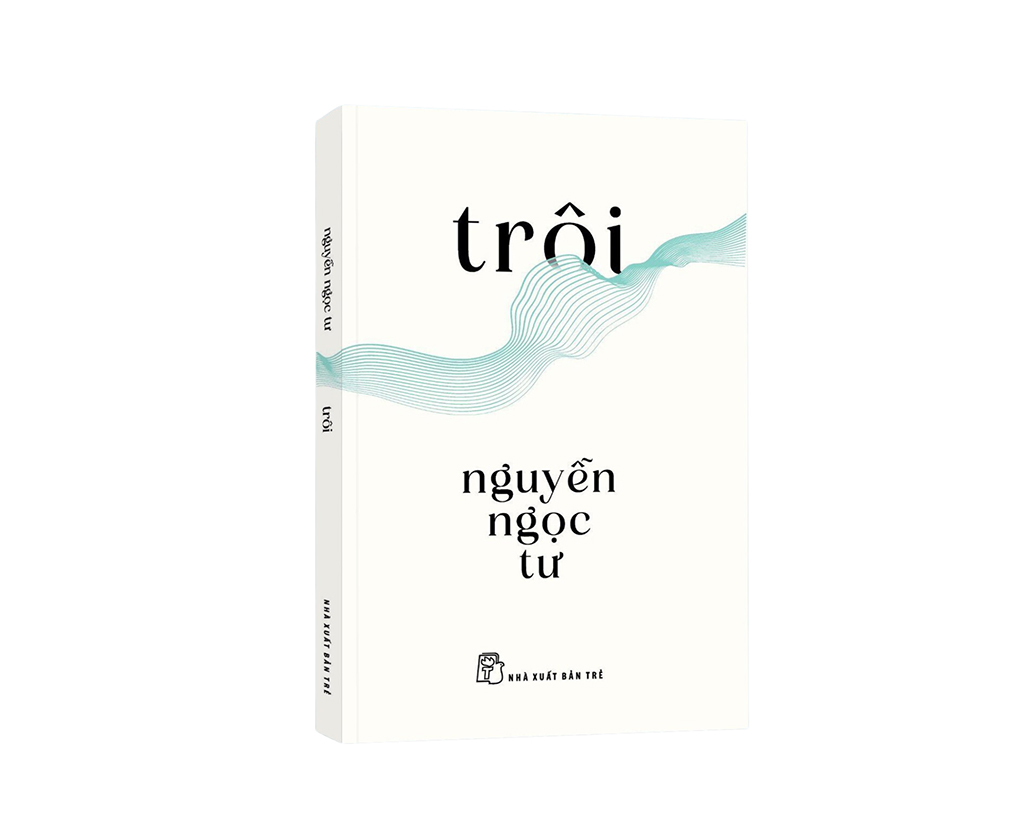
そこから彼女は問いかけました。現代の人々は、ビエグニの信奉者たちと何の共通点を持っているのでしょうか?そして、グエン・ゴック・トゥの『トロイ』は、まさにその問いへの答えとなるでしょう。南西部の人々、物語、方言を通して読者に親しまれてきたこの作品には、人間世界の開放性とともに、文学をグローバル化し、普遍化したグエン・ゴック・トゥの姿が描かれています。この短編集の登場人物たちは、様々な場所からやってきて、様々な職業に就き、それぞれに運命を背負っています。しかし、ある瞬間に彼らの運命は交差し、そこから物語が始まります。
人間の漂流は、内省の微視的な変化(げっぷ)であることもあれば、巨視的な変化(歴史)であることもある。目に見えないもの(記憶)であることもあれば、触れられるもの(ホテイアオイ)であることもある。説明できるもの(地質学的分離)であることもあれば、説明できないこともある…。グエン・ゴック・トゥは短編小説というジャンルの特性を活かし、多様な断片を提示することで、人生におけるあらゆるものの集積と分離を解き明かしている。この短編集において、著者は「交差点」に細心の注意を払っており、それ自体も法則に従って漂流していることがわかる。
例えば、 「夢見る人」「あちらこちら」 「扉のそば」という三つの作品は、登場人物に連続性があり、内容は完全に独立しているにもかかわらず、共通の物語を辿っているように見えます。また、 「風の始まり」には、前作「雲を繋ぐ」に登場したルートという人物が登場します。こうした飛び石によって連続性が生まれ、読み進めていくにつれて、繋がりがさらに深まっていくのです。
漂流は、グエン・ゴック・トゥの短編小説の解釈の源泉とも言えるでしょう。彼の作品には、ほとんど不条理で滑稽とも言える物語がしばしば登場します。例えば、この短編集には、飛行機内でパンケーキをこぼしたために思いもよらぬ理由で逮捕されたカップルが登場します( 『空の冷たい火』)。また、高周波の音は聞こえるものの、日常に近い音には苛立ちを覚える、ほとんど非現実的な人物も登場します( 『遠い飢餓』 )。すべてはこの漂流から始まるのです。だからこそ、「漂流は偶然ではなく、漂流そのものがメッセージであり、合図であり、地平線からの招待状なのだ」と理解できるのです。
現実の認識
この作品の登場人物の多くは、自らの動きを内包している。それは、彼ら自身が潜在意識に抗えない記憶の動きから生み出されるエネルギーなのだ。例えば、 『クロロフィル・レイン』に登場する「記憶修復士」は、どんなに努力しても孫から亡き母の面影を消すことができない。あるいは、 『この事件の渦中』に登場する男は、生涯一度も家から出たことがないにもかかわらず、記憶と自らの出自に関する疑問が常に彼を苦しめ、それが内発的な動きとなり、彼自身も時間の流れの中、別の空間へと漂流していく……。
記憶に加えて、血統の継承もまた、人々に自己暗示を抱かせるものです。それは幼少期、つまり私たちを構成する物質に由来し、徐々に原始的な、すでに存在する本能へと変化していきます。例えば、胎児の頃、母親がハンモックに寝て揺らしてくれたため、生涯をハンモックに縛り付けられて過ごした男(繭の中で揺らされる)がそうです。あるいは別の話では、それは遺言のみに基づく三世代にわたる負債(負債)です。また、人生の影響によって形成されることもあり、血縁関係が多少異なる三人の男には、奇妙な習慣が共通しています。「深く眠っている人を長い間観察していると、彼らの夢が見える」…
上記の2つのことから、たとえ物理的に静止しているときでも、私たちの内側では常に何かが動いていることがわかります。しかし、結局のところ、私たちは(響き渡るように)静止したままでいるべきでしょうか、それとも(たとえ遠く離れていても)動きに従うべきでしょうか?イタリアの作家イタロ・カルヴィーノは、イラン旅行に触発されて書いたエッセイ『彫刻と遊牧民』の中で、遊牧民の隊商と石板が同時に現れるのを見て、この問題について深く考えました。
彼はこう書いている。「もし二つの生き方を選ばなければならないとしたら、私は長い間、その長所と短所を天秤にかけなければならないだろう。消えることのない痕跡を残すためだけに生き、石のページに刻まれたシルエットとなるか、それとも季節の巡り、草や茂みの成長、太陽や月や星の巡りに従って止めることのできない歳月のリズムに身を委ねて生きるかだ。[…] いずれにせよ、何かが私を阻んでいる。この群衆の中に入り込む場所が見つからない。ただ一つの考えが私を安心させる。それは絨毯だ。」
カルヴィーノが言ったように、最も重要なことは、今あるものを理解することです。なぜなら、どんなに努力しても全体像を見ることはできず、私たち自身も常に流れの中の小さな点に過ぎないからです。短編集『どこにも向かわず』の最後で、グエン・ゴック・トゥもまたこう断言しています。「信仰が戻ってきた。そして、改めて確信した。確かに、他に道はない。私はどこにも属していない」。それを理解することで、彼らは自分自身を見つめ直す機会を得るでしょう。グエン・ゴック・トゥの作風の変化を示す、印象的で、内省の余地に満ちた短編集です。
グエン・ゴック・トゥは1976年生まれで、現在はカマウに在住し、執筆活動を行っています。彼女は数多くのエッセイ、散文、短編集、小説を執筆しており、『消えることのない光』『果てしない野原』『山の給仕を愛する』『グエン・ゴック・トゥのエッセイ集』『大晦日』『孤独な風と9つの物語』『川、島』『心を測る』『誰も川を渡らない』『冷たい首』『華麗なる空煙』『空の荷物』『手についた冷たい煙』『漂流』など、多くの作品を執筆しています。
[広告2]
ソースリンク


![[写真] 朝鮮労働党創立80周年記念パレードに書記長が出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760150039564_vna-potal-tong-bi-thu-du-le-duyet-binh-ky-niem-80-nam-thanh-lap-dang-lao-dong-trieu-tien-8331994-jpg.webp)




![[写真] 第1回世界文化祭でユニークな体験を発見](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760198064937_le-hoi-van-hoa-4199-3623-jpg.webp)


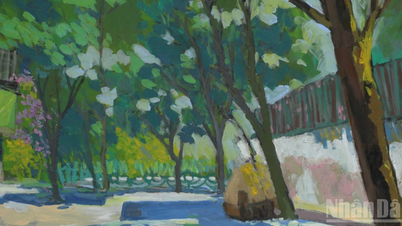



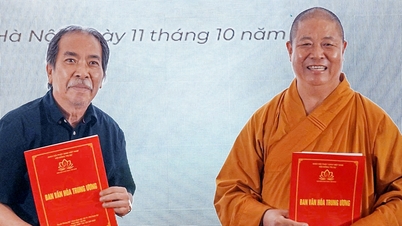













![[写真] ホーチミン市は2025~2030年任期の第1回党大会前夜、国旗や花で華やかに彩られている](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760102923219_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-43-png.webp)































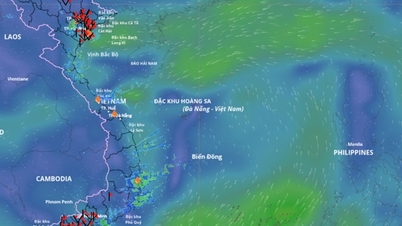

































コメント (0)