
平和の街ハノイから、世界は歴史的な節目を目撃しました。2025年10月25日と26日に行われた国連サイバー犯罪防止条約の署名式は、サイバー犯罪に関する世界的な多国間条約であり、デジタル時代におけるサイバーセキュリティ、正義、そして人権を確保するための国際的な法的枠組みの構築に向けた重要な節目となります。
ハノイ条約は、テクノロジーブームとサイバー犯罪の脅威の巧妙化が世界経済に圧力をかけている状況下で誕生しました。データ攻撃、電子詐欺、ランサムウェア、あるいは暗号通貨を用いたマネーロンダリングは、毎年数兆ドルもの損失をもたらしています。サイバー空間は、発展のプラットフォームから、非伝統的な紛争の「新たな前線」へと徐々に変化しつつあります。したがって、国連によるハノイ条約の採択と署名の組織化は、法的前進であるだけでなく、安全で人道的なデジタル環境を守るための連帯と国際協力の精神の象徴でもあります。
ハノイの国立コンベンションセンターで開催された署名式には、アントニオ・グテーレス国連事務総長やベトナムのルオン・クオン大統領を含む110カ国以上が出席しました。「サイバー犯罪との闘い – 責任の共有 – 未来の確保」をテーマに掲げたこの式典では、ベトナムが東南アジアで初めて国連の国際条約の命名・署名地として選ばれ、前例のない出来事となりました。式典終了までに65カ国が署名し、条約発効に必要な最低40カ国を大きく上回りました。

「ハノイ条約」という名称には、平和都市ハノイへの敬意を表するだけでなく、世界のサイバーセキュリティ分野におけるベトナムのリーダーシップ、責任、そして勇気を称える、深い象徴的な意味があります。ベトナムは2019年以来、交渉プロセスに積極的に参加し、サイバー空間における技術支援、技術移転、人権保護に関する実践的な提案を行ってきました。署名式典の開催地としてハノイが選ばれたことは、協力、法の支配、そして持続可能な開発という価値観を常に堅持してきた発展途上国の努力を認めるものです。
ハノイ条約は9章71条から構成され、サイバー犯罪の刑事罰化、捜査管轄権、国際協力、犯罪人引渡し、司法共助、個人情報保護といった事項を包括的に規定しています。この文書はサイバー犯罪の概念を標準化するだけでなく、各国が情報を共有し、犯罪をより効果的に追跡・処理できるよう、国境を越えた調整メカニズムも構築しています。不正アクセス、データ窃盗、電子詐欺、重要インフラへの攻撃、サイバー空間を利用したテロ活動、暗号通貨を用いたマネーロンダリングといった行為が具体的に特定されています。これは、これまで多くの国際サイバー攻撃の訴追を不可能にしてきた「法的グレーゾーン」を打破する画期的な一歩です。
ハノイ条約は、安全保障と人権のバランスがとれている点で特筆すべきものです。サイバー犯罪に関する最初の国際条約であるブダペスト条約(2001年)は、プライバシー保護の欠如が批判され、当初は主に欧州諸国を対象としていました。しかし、ハノイ条約は、あらゆる捜査およびデータ収集措置において、法の支配、比例性、透明性の原則を遵守することを義務付けることで、この問題を完全に克服しました。当局は、正当な司法命令があり、かつ必要な範囲内でのみ、個人データへのアクセスや情報の監視が認められています。これは、サイバーセキュリティを人権と不可分と捉え、国際法の支配への信頼を強化するという、人道的なアプローチを示しています。
法的観点から見ると、ハノイ条約はサイバー犯罪に関する初の国際的な法的枠組みとみなされており、加盟国は条約の条項を自国の法制度に取り入れ、整合性と一貫性を確保することが求められています。条約が正式に発効すると、各国は刑法の改正、犯罪人引渡しメカニズムの確立、相互司法援助などを含む実施段階に入ります。国連薬物犯罪事務所(UNODC)は、各国、特に開発途上国が十分な執行能力を備えるよう、監視、技術支援、研修、技術移転において中心的な役割を果たします。

ベトナムにとって、ハノイ条約はサイバーセキュリティに関する法的枠組みの改善、個人データの保護、そしてハイテク犯罪への対応能力の向上に向けた大きな機会となります。公安省と関係機関は、実施計画の策定に着手し、条項の見直しと国内化、そして実施プロセスのための技術・人的資源の整備のための部門横断的な作業部会を設置しました。ホスト国としての役割を担うベトナムは、2026年から2030年にかけてUNODCが調整するサイバーセキュリティに関する地域協力拠点の一つとなります。
ハノイ条約は、多国間主義のビジョンと国家間の平等な協力の精神を体現しています。世界が大国間の技術基準の隔たりを目の当たりにしている今、60カ国以上がハノイに集まり共通条約に署名したことは、対話と国際法への信念を力強く証明するものです。ここからハノイは、サイバー空間における共通の未来を守る責任を各国が共有するデジタル協力の象徴となるのです。
ハノイ条約は法的意義だけでなく、深い人道的価値も有しています。同条約は、技術は人々に害を与えるものではなく、人々に奉仕するものでなければならないと定めています。サイバー犯罪の被害者を保護するための条項が盛り込まれたことで、包括的かつ人間中心のアプローチが実現しました。ハノイ条約は、各国が技術を共有し、人材を育成し、恵まれない国の能力を強化することを奨励することで、格差を縮小し、デジタル変革の時代に誰も取り残されないよう貢献してきました。
このプロセスにおけるベトナムの役割は、ホスト国としてだけでなく、ファシリテーターとしての役割も担っています。ベトナムは、各国間の対話を積極的に促進し、技術支援、データ保護、開発と安全保障の利益のバランスに関する規定の構築にアイデアを提供してきました。「積極的、前向き、責任ある」という精神に基づき、ベトナムはグローバルなデジタル秩序の構築において、信頼できるパートナー、先進国と発展途上国の架け橋としての立場を改めて確固たるものにしています。
アントニオ・グテーレス国連事務総長は署名式で、「ハノイ条約は国境を越えた協力の精神の証であり、各国が平和とデジタルセキュリティという共通の目標に向けて協力すれば、世界はあらゆる分断を乗り越えられることを示しています」と述べた。ルオン・クオン大統領は、「ベトナムは、サイバー空間の保護、人々、そして持続可能な開発のための世界的な取り組みに貢献できることを誇りに思います」と強調した。
長期的には、ハノイ条約はグローバルなサイバー空間における新たな法秩序を形成し、国際法がデジタル世界における平和と正義を守る「盾」となるでしょう。ハノイから、そのメッセージは五大陸に発信されます。サイバーセキュリティは人権と結びついていなければならず、国際協力こそが安全で公正かつ人道的なデジタルの未来を確保する鍵となるのです。ハノイ条約は、平和と責任の国であるベトナムから生まれた、世界的な信頼の象徴です。
国連サイバー犯罪防止条約(ハノイ条約)の開会式およびハイレベル会合の成功には、VietinBank、PVN、EVN、MB Bank、Agribank、SSI、FPT、VPBank、Gelex、ベトナム航空、VIX、BIDV、Viettel、OKXといったスポンサー企業の責任ある献身的な支援なくしては語れません。これらの企業の協力は、権威ある国際イベントにおける官民連携の精神を示すとともに、安全で信頼性が高く持続可能なサイバー空間の構築という目標の実現におけるベトナム経済界の役割と社会的責任を反映しています。こうした支援のおかげで、ハノイ条約の開会式は国際協力の模範的なシンボルとなり、国際舞台におけるベトナムの威信、地位、そしてイメージの向上に貢献しました。
出典: https://nhandan.vn/cong-uoc-ha-noi-dau-moc-lich-su-kien-tao-trat-tu-phap-ly-toan-cau-ve-an-ninh-mang-post920731.html














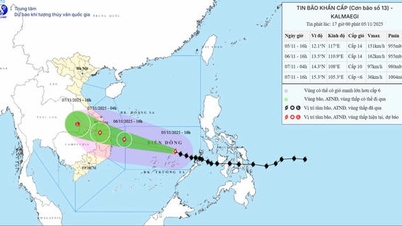












![[写真] 2025年から2030年までのニャンダン新聞愛国模範大会のパノラマ](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762252775462_ndo_br_dhthiduayeuncbaond-6125-jpg.webp)
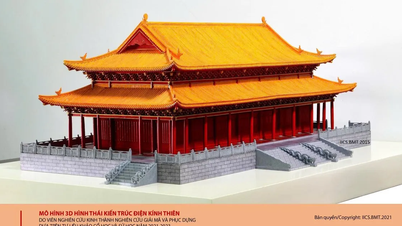

































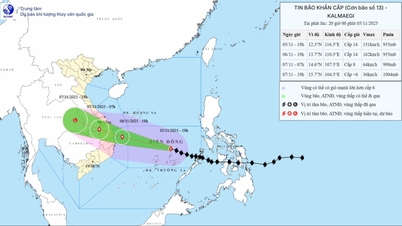











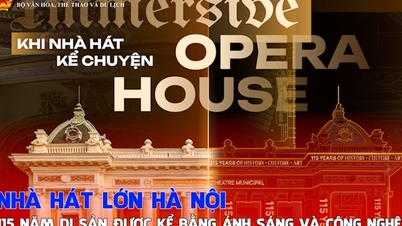

























コメント (0)