日本は現在、多くの人にとって魅力的な渡航先です。近年、日本への留学や就労を希望するベトナム人の数は増加傾向にあります。しかし、ベトナム人労働者は日本への就労に高額な費用を支払わなければなりません。
コスト負担
日本で働くベトナム人労働者は勤勉で働き者であり、日本の社会経済発展に積極的に貢献していると評価されています。ベトナム労働傷病兵社会省海外労働管理局のファム・ビエット・フオン副局長によると、ベトナムと日本の間の労働・人材育成分野における協力は近年ますます重視され、目覚ましい発展を遂げています。ベトナム労働傷病兵社会省は日本側と連携し、技能実習制度、特定技能外国人材制度、日越経済連携協定(VJEPA)に基づくベトナム人看護師・介護士の日本への派遣プログラムなど、多くのプログラムやプロジェクトを実施しており、効果を上げています。
近年、日本で働くベトナム人労働者の数は、毎年海外で働く労働者数の50%以上を占めています。日本がベトナム人研修生の受け入れを開始して以来、過去30年間で35万人以上のベトナムの若者が技能実習のために日本に来ています。
 |
| 日本に滞在するベトナム人研修生。写真提供:海外労働管理部 |
しかし、これまで達成された成果の一方で、ベトナム人研修生や労働者を日本に派遣・受け入れしてきたプログラムには、契約を破り日本の法律に違反する研修生や労働者がいるなど、依然としていくつかの問題が残っている。
このような状況の原因としては、ベトナムの一部派遣会社が、研修生の選考、外国語研修、出発前のオリエンテーション教育を適切に実施していないこと、規定よりも高いサービス料を請求していること、研修生が仲介業者やブローカーに損害を与えていることなどが挙げられます。また、一部の日系パートナーは、研修生の受け入れ時に派遣会社に手数料を要求したり、ベトナム到着時に過剰な接待を要求したりして、研修生に経済的負担をかけたり、合意された管理費や派遣料を支払っていないことなどが挙げられます。
国際協力機構(JICA)の宍戸健一理事長特別顧問によると、日本へ出稼ぎに行くベトナム人労働者の数は急増している。現在、日本に研修生を送り出している15カ国のうち、ベトナムは年間の入国者数、実習生数ともにトップとなっている。
しかし、ベトナム人労働者が日本で働くために支払う平均費用は、中国やカンボジアよりも高く、フィリピンの4倍にも上ります。宍戸健一氏によると、日本の関係機関は2022年末から、外国人労働者が費用を負担することなく日本に渡航し、安心して就労・滞在し、持続的に発展できるよう、新たな仕組みの検討を開始しています。
労働者への公平性
国際労働機関(ILO)ベトナム事務所長のイングリッド・クリステンセン氏は、日本で働く外国人労働者の中でベトナム人が最も多く、総数182万人の外国人労働者の25.4%を占めていると述べた。しかし、イングリッド氏によると、日本で働くベトナム人労働者は非常に高いコストに直面しているという。
国際労働機関(ILO)の支援を受けて統計総局が最近行った、海外でのベトナム人労働者の採用コストに関する調査によると、実際にはベトナム人移民労働者は日本での最初の仕事に採用されるために最大1億9,200万ベトナムドン(8,000米ドル相当)を支払わなければならないことが明らかになった。
これは労働コストに関する国際基準に反する。イングリッド・クリステンセン氏は、労働者が募集手数料を支払うことで強制労働のリスクが高まり、採用された仕事が終了した後も数ヶ月、時には数年間にわたって借金を返済しなければならないという労働者の脆弱性が高まると強調した。そのため、イングリッド・クリステンセン氏は、ベトナムと日本は労働協力に関連するコストを削減するための努力をする必要があると述べた。
ベトナムは、料金制の採用制度を早急に廃止し、労働者の権利と公平性を確保し、国際基準に沿って労働組合の役割を促進する必要がある。
ファム・ベト・フオン氏は、海外で働く労働者のコストを削減するために、「契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者に関する法律」(法律第69/2020/QH14号)に、海外で働く労働者を選抜し、資源の準備活動を利用して労働者から不法に金銭を徴収すること、労働者から仲介手数料を徴収すること、法律の規定に従わずに労働者からサービス料を徴収することなど、いくつかの禁止行為が追加されたと述べた。
日本への労働者派遣コストの改善の必要性を支持する、元労働・傷病兵・社会問題省副大臣でベトナム労働者派遣協会(VAMAS)会長のドアン・マウ・ディエップ氏は、「日本で働く労働者が0ドンで就労できるようになるまでの道のりは長いが、募集機関、企業、当局が協力し、労働者が高すぎるコストによる不利益を被らないようあらゆる方面から努力すれば、その道のりは短くなるだろう。一方で、日本側も参加し、0ドンのコストに参加する意思のある企業がどれだけあるか、労働者に手数料を支払う意思のある企業がどれだけあるかを把握する必要がある。労働者の出国コストが0ドンに引き下げられた場合、日本に就労し手数料を支払う労働者の賃金と福利厚生に差別が生じないよう、労働者間の公平性を確保する仕組みが必要だ」と述べた。
ディープ・チャウ
*関連ニュースや記事をご覧になるには経済セクションをご覧ください。
[広告2]
ソース






































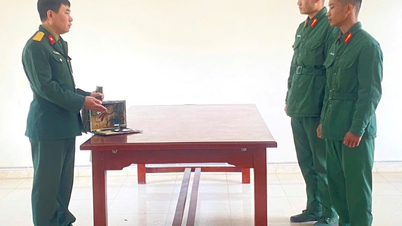



































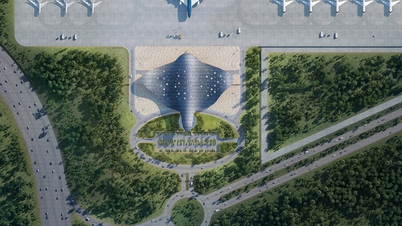



















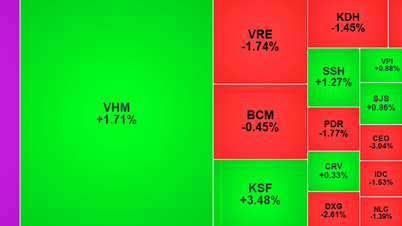

















コメント (0)