
11月8日付日経アジアによると、日本の三大銀行である三菱UFJ銀行(MUFG)、三井住友銀行、みずほ銀行は、11月に円建てステーブルコインの発行試験を開始する。これは、世界中で米ドル建てステーブルコインの波が広がる中、東京独自のデジタル決済システム構築に向けた取り組みにおいて大きな前進となる。ステーブルコインとは、法定通貨や貴金属などの実物資産に連動することで価格の安定を維持するように設計された仮想通貨である。
発表された計画によると、3行は企業取引で利用可能な標準化された相互運用可能なステーブルコインを共同で発行する。MUFGは各行の預金をエスクロー資産として管理し、技術プラットフォームは3つの金融グループが出資するProgmat社によって運営される。
ステーブルコインとは、法定通貨やその他の資産にペッグされた暗号通貨であり、時間や場所の制約なしに低コストで送金できます。日本では、ステーブルコインは国債または銀行預金によって裏付けられていることが義務付けられています。
三菱商事は、この実証実験において、国内本社と海外子会社間のクロスボーダー決済にステーブルコインを活用し、手数料と事務手続きの削減を目指します。グループの担当者は、ステーブルコインの利便性、成長性、そしてコーポレートファイナンスへの適用性を評価することが目的だと述べています。
専門家は、日本の三大銀行の連携が、国内におけるステーブルコインの普及を大きく後押しする可能性があると指摘している。三大銀行は現在、30万社以上の大企業顧客にサービスを提供しており、この種のデジタル資産の利用範囲を大幅に拡大している。
フィンテック企業JPYCは以前、同名のステーブルコインをリリースしました。このコインは円に1:1でペッグされており、10月末までに約1億3000万枚のコインが流通していました。また、JPYCを使ったクレジットカード決済を可能にするNudgeプラットフォームなど、JPYCを利用した決済サービスも登場し始めています。
帝京大学の宿輪純一教授は、ステーブルコインは相互互換性のない国内仮想通貨に比べて利便性が高く、消費者に普及すればキャッシュフローの改善や経済の下支えになると指摘した。しかし、法人顧客向けには、銀行が外部機関との連携を含め、発行に向けて慎重な準備を進める必要があると指摘した。
政府の支援にもかかわらず、この取り組みはマネーロンダリング対策規制と利用者の身元確認という課題に直面している。さらに、3行のステーブルコインは外国のステーブルコインと交換される予定はない。
日本の計画は、米ドルに連動するステーブルコインが世界市場シェアの90%以上を占める中で発表された。ドナルド・トランプ米大統領は7月にGENIUS法に署名し、ステーブルコインの法的枠組みを確立した。これにより、ステーブルコインの流通量は前年比70%増の約3,000億ドルに増加した。
国際決済銀行(BIS)によると、米国のステーブルコイン発行者は2024年に約400億ドルの短期債を購入しており、これはほとんどの国の購入額を上回っています。日本政府は、米ドルに連動するステーブルコインが国内で普及すれば、安全資産である米ドルへの投資のために円や日本国債が売られる可能性があることを懸念しています。
日本の金融庁(FSA)は、決済、ブロックチェーン、国際法の分野の専門家を派遣することでこのパイロットプログラムを支援しており、これはデジタル金融時代における円の役割を守るための戦略的な動きである。
出典: https://baotintuc.vn/thi-truong-tien-te/nhat-ban-thuc-day-phat-trien-dong-stablecoin-noi-dia-de-bao-ve-vai-tro-dong-yen-20251109094716356.htm










































































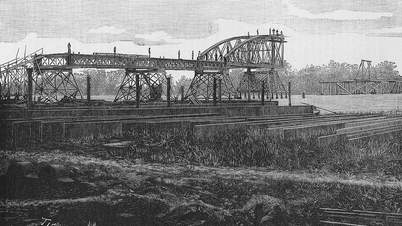




































コメント (0)