2024年の国際調査の結果によると、日本の教師の労働時間は、 経済協力開発機構(OECD)加盟国・地域の中で依然として最も長い。
OECDは2025年10月7日、国際教員教育調査(TALIS)2024の結果を発表した。データによると、日本の教員は長年にわたり労働条件の改善を求められているにもかかわらず、依然として他国の教員に比べて不釣り合いに高い仕事量に直面していることが明らかになった。
日本の小学校教員の週平均労働時間は52.1時間、中学校教員は55.1時間で、2018年の調査に引き続きトップとなった。
以前より労働時間は減ったが、それでも世界平均より10時間以上長い
前回の調査と比較すると、日本の常勤教員の週平均労働時間は、両レベルで約4時間減少しました。しかし、国際平均は小学校教員で週40.4時間、中学校教員で週41時間となっており、日本の教員は依然として世界の教員よりも週11~14時間多く働いていることになります。

TALIS調査は5~6年ごとに実施されます。2024年版では、16の国と地域の小学校約200校と、55の国の中学校約200校が調査対象となりました。校長と教師に、勤務時間と職務上の課題について質問しました。勤務時間には、宿題の採点、授業計画の作成、夜間や週末の課題への対応など、自宅で行う残業時間も含まれます。
理由:課外活動と事務作業
日本では残業時間の制限や課外活動の一部外部委託などの対策が取られているものの、知識、道徳、体力のバランスのとれた発達を重視する総合的な教育モデルも、教師の長時間労働につながっていると専門家は認めている。
調査によると、日本の教師が課外活動や事務作業に費やす時間は国際平均よりも大幅に長い。
日本の中学校教師は、課外活動に週平均5.6時間を費やしているが、国際平均はわずか1.7時間である。
小学校教師は週4.5時間を事務作業に費やしており、中学校教師は5.2時間を事務作業に費やしている。世界平均はそれぞれ2.7時間と3.0時間である。
それでも、これらの数字は2018年の調査以来0.9~2.5時間減少している。
さらに、教師不足により教育業務の負担も増大しています。
質の高い教育を確保するために欠けている要素について尋ねたところ、日本の校長から最も多く寄せられた答えは「教師」でした。
小学校の校長の40.7%が、自校の教師が不足していると回答しており、これは2018年の19.2%の2倍です。同様に、中学校の校長の35.6%も、教師不足が教育の質の向上の障壁になっていると回答しており、前回調査から8.1ポイント増加しています。どちらの割合も国際平均を10ポイント以上上回っています。
毎日新聞によると、文部科学省の担当者は「課題はまだ多いものの、正しい方向に進んでいる」と語った。
教師不足については、「これは深刻な問題であり、今後最優先事項として考えられるだろう」と強調した。
出典: https://vietnamnet.vn/noi-kho-cua-giao-vien-o-dat-nuoc-co-nen-giao-duc-hang-dau-chau-a-2451380.html



![[写真] 第1回世界文化祭でユニークな体験を発見](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760198064937_le-hoi-van-hoa-4199-3623-jpg.webp)

![[写真] 朝鮮労働党創立80周年記念パレードに書記長が出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760150039564_vna-potal-tong-bi-thu-du-le-duyet-binh-ky-niem-80-nam-thanh-lap-dang-lao-dong-trieu-tien-8331994-jpg.webp)



























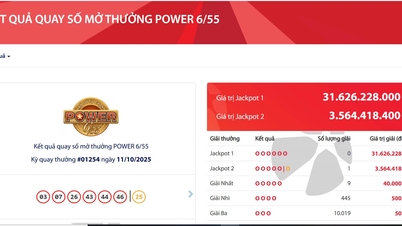



![[写真] ホーチミン市は2025~2030年任期の第1回党大会前夜、国旗や花で華やかに彩られている](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760102923219_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-43-png.webp)





























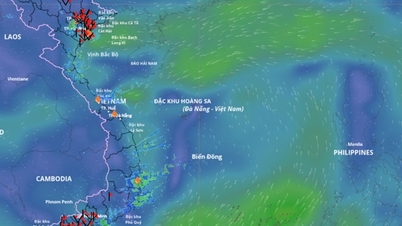

































コメント (0)