米国は、ヨーロッパやラテンアメリカに拡大し、世界的なメンテナンスネットワークの構築を目指している
日経アジアによると、米国防総省は日本、韓国、オーストラリア、シンガポール、フィリピンのインド太平洋地域の5カ国に軍事修理センターを設置する予定だ。
国防総省の新しい地域支援枠組み(RSF)では、同盟国やパートナー国の既存の産業能力を活用して、船舶、航空機、車両を米国に返還するのではなく、それぞれの作戦地域に近い場所でメンテナンス、修理、オーバーホールを行うことを規定しています。
この展開は今年5カ国で試験的に実施され、その後2025年に欧州司令部地域のNATO加盟国に、2026年には南方司令部の管轄下にあるラテンアメリカの加盟国に拡大される予定だ。
 |
| 青森県三沢基地に駐留する米空軍隊員が、インドネシアのサム・ラトゥランギ国際空港での訓練中にF-16Cファイティング・ファルコンの飛行後点検を行っている。(米空軍) |
上記の5カ国のうち4カ国は条約同盟国です。シンガポールは同盟国ではありませんが、米軍艦を交代で受け入れる伝統があります。
日経アジアによると、この計画は、工業力において中国に太刀打ちできないという米国自身の認識に端を発している。2023年7月、ウェブサイト「The War Zone」は、世界最大の造船国である中国の造船能力が米国の232倍であることを示す米海軍の要約スライドを公開した。
国防総省のプロジェクトリーダーで当時国防次官補だったクリストファー・ロウマン氏は、2月に開催されたWest 2024会議において、 軍事ロジスティクスは従来の「事後対応型」の姿勢から解決策を提供する姿勢へと移行しつつあると述べた。ロウマン氏は、修理センターを複数箇所に設置することで抑止力を高めると述べた。整備、修理、オーバーホール能力を地域全体に分散させ、同盟国やパートナー諸国の能力と統合することで、米国は敵対国の計画策定プロセスに更なる複雑さを加えることになるだろう。2024年3月、ロウマン氏はこの問題について議論するため、上級ロジスティクス専門家の代表団を率いてオーストラリア、日本、フィリピンを訪問した。
国防総省は5月にRSF構想を発表した際、同盟国やパートナー諸国と産業基盤を統合することで「予測可能な需要」に貢献し、防衛関連請負業者が能力への投資を決定しやすくなると述べた。
ローマン氏は7月の記者会見で、修理は「消耗」だけでなく「戦闘で損傷した装備」にも対処すると述べた。
同氏は、作戦地域司令官に機能不全のプラットフォームを修復するための複数の選択肢を提供することで、「敵の計画サイクルに高いレベルの不確実性を生み出し、抑止力と抑止価値を高める」と述べた。
一方、アジアの同盟国はこのビジネスチャンスに備えている。8月には、韓国の造船会社ハンファ・オーシャンが、朝鮮半島南部の巨済造船所で4万トンの米軍補給支援艦を整備する契約を米海軍と締結したと発表した。
このニュースは、同社がそのような作業を行うために米海軍とマスターシップ修理協定を締結したと発表したわずか数週間後に発表された。
ハンファは6月、ペンシルベニア州にある旧フィラデルフィア海軍造船所の一部であるフィラデルフィア造船所を1億ドルで買収する契約を発表した。
一方、ラーム・エマニュエル駐日米国大使は、日本に配備された米軍艦の修理に日本の民間造船所を活用する取り組みを主導している。
[広告2]
出典: https://baoquocte.vn/bo-quoc-phong-hoa-ky-lua-chon-5-quoc-gia-thanh-lap-cac-trung-tam-sua-chua-quan-su-285076.html



![[写真] カットバ島 - 緑の楽園の島](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F04%2F1764821844074_ndo_br_1-dcbthienduongxanh638-jpg.webp&w=3840&q=75)

































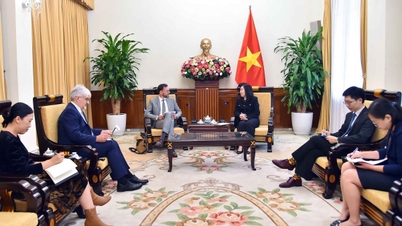









































































コメント (0)