Nguoi Lao Dong紙の報道によると、 財務省は累進税率を7段階から5段階に短縮する新たな個人所得税(PIT)法案について意見を募っている。しかし、専門家や国民が懸念しているのは、調整されたにもかかわらず、課税所得の基準額が依然として時代遅れであり、家族控除や現在の経済状況に適していないという点だ。
35% の税率を撤廃すると、個人所得税の課税対象額にどのような影響がありますか?
第15期国会議員であり、国家教授評議会副議長であるホアン・ヴァン・クオン教授は、税率表における税率の数を減らすことは税制の簡素化に非常に重要であり、税制の簡素化に寄与すると強調した。しかし、現実に即し、個人所得税の目的に沿った税制を実現するためには、起草機関は税率間の所得格差と、各税率に適用される税率を慎重に検討・計算する必要がある。

専門家は皆、現在の経済状況に合わせて、家族控除額と課税最低額を引き上げることを推奨している。写真:HOANG TRIEU
ホアン・ヴァン・クオン教授によると、今回の個人所得税法改正案の策定においては、税率の段階数を減らすだけでなく、他の多くの要素も同時に考慮する包括的なアプローチが必要だという。目標は、税制が国民の納税能力を真に反映し、労働力を奨励し、特に優秀な人材を引き付けることだ。クオン教授は、税率段階と各段階の税率を策定する際には、段階を総合的に考慮し、国民の生活水準を確保するためのコストを十分に計算した上で、適切な税率を提案する必要があると述べた。
ホーチミン市税務コンサルタント・代理人協会会員の弁護士グエン・ドゥック・ギア氏は、10年以上「凍結」された現在の個人所得税政策はもはや人々の実際の生活に適していないとコメントした。
同氏は、家族控除が最後に大きく調整されたのは2013年で、個人控除が月額400万ドンから900万ドンに、そして2020年には1100万ドンに増加した。それ以来、労働者の生活水準は急速に向上しているが、税制はそれに応じて変更されていない。
彼によると、食料、住宅、医療、教育といった基本的なニーズの実際の費用は2020年と比較して少なくとも50%増加しているのに対し、消費者物価指数(CPI)は約21%しか上昇していない。したがって、法案が最高税率区分を8,000万ドンから1億ドンに引き上げるだけであれば、それは低すぎ、現在の実際の支出圧力を正確に反映していない。
この分析に基づき、ギア氏は、過去10年間のインフレ率に合わせるため、最高課税所得の基準額(税率35%を適用)を月額約1億2,000万ドンに引き上げることを提案した。同時に、累進課税原則に基づく税額計算の公平性を確保するため、課税所得の基準額をレベル2からレベル5に同期的に調整し、現行比40%相当の引き上げを行うことを推奨する。
ミン・ダン・クアン法律事務所の所長であるトラン・ソア弁護士は、現行の税制は7段階に分かれており、各段階間の距離が近すぎるため、納税者が収入が大幅に増加していないにもかかわらず「段階的に上がる」ことが容易になっていると強調した。草案にあるように5段階に削減することは前向きな一歩だが、それでもまだ不十分だと同氏は指摘する。
彼は、税率を4に引き下げ、35%の税率を完全に撤廃することを提案しました。これは、税率が高すぎて給与所得者に多大な負担をかけているためです。具体的には、レベル1は、月収2,000万ドンまでの所得に対して5%の税率が適用されます。レベル2は、2,000万ドンから4,000万ドンまでは10%、レベル3は、4,000万ドンから8,000万ドンまでは20%、レベル4は8,000万ドンを超えると30%となります。彼によると、この税制はシンプルで計算も容易であり、納税者の理解を深め、より前向きな姿勢につながるとのことです。
税率の引き下げと課税最低額の引き上げを組み合わせれば、この政策は労働者を支援すると同時に、安定した財政収入源を確保することになる。「個人所得税の引き下げは、出産促進政策を促進する間接的な解決策の一つでもある。余剰所得が増えれば、人々は支出計画に積極的になり、家計を安定させ、子供を持つようになるだろう」と弁護士のトラン・ソア氏は述べた。
不当な控除額
一方、フルブライト公共政策・経営大学院の講師であるド・ティエン・アン・トゥアン博士も、家族控除の増額だけでは明確な効果は得られないと述べた。トゥアン博士は、月収1500万ドンの人が現在納税しているのは20万ドンだけだと説明した。控除額が1550万ドンに引き上げられれば、この人はもはや税金を払う必要がなくなるが、減額されるのは20万ドンだけだと説明した。
一方、公平性を確保し、インフレに対応するため、課税対象となる最高所得は、現在の月額8,000万ドンから1億7,000万ドン以上に引き上げられることになりました。彼によると、この水準は、中国、タイ、インドネシア、マレーシアなど、同じく35%の税率を適用しているものの、所得基準が非常に高く、月額3億ドンから10億ドン以上とされている地域内の多くの国と比べると、まだ低い水準です。
弁護士のトラン・ソア氏も同様の見解を示し、財務省が個人所得税の課税最低額の調整基準として消費者物価指数(CPI)を用いていることは、現行の法規制には合致しているものの、労働者の生活実態には必ずしも合致していないと指摘した。同氏は、CPIは主にマクロ経済運営を目的として752品目の平均価格に基づいて算出されており、人々の生活必需品支出を正確に反映していないと分析した。
一方、労働者は食料、生活必需品、医療、教育など、消費者物価指数(CPI)よりもはるかに高い価格上昇が見込まれる生活必需品を少量しか利用しないことが多い。そのため、国会はCPIを課税最低額の調整基準とすることを定めているものの、生活費の上昇圧力により、この考え方は時代遅れになりつつあると同氏は指摘する。
Xoa弁護士は、2007年に個人所得税法が公布された当時、消費者物価指数(CPI)は年間10%以上上昇し、わずか2年で20%に達した状況を例に挙げました。現在、インフレ抑制が功を奏し、CPIの上昇は緩やかになっているものの、国民の実際の支出は急増しています。そのため、財務省が提案した控除額を月額1,100万ドンから1,330万ドンに引き上げるという提案は低すぎます。また、1,550万ドンという水準は(GDPを基準としているため)現実に近いとはいえ、最低生活水準を満たすには依然として不十分であり、明確な法的根拠を欠いています。
この現実を踏まえ、彼は、納税者が生活に十分な余裕を持つだけでなく、長期的に積極的に財政的に行動する能力を身に付けるために、合理的な控除額を月額1,800万~2,000万ドンに調整し、2026年から2031年にかけて安定的に適用することを提案した。彼によると、課税所得の上限を引き上げる際に財政が減少するリスクを財務省が懸念しているという主張は根拠がないという。現実は正反対であり、2009年、2013年、そして2020年に家族控除額が引き上げられた際、予算収入は減少するどころか、むしろ着実に増加した。
ハノイ国立経済大学のグエン・クオック・ヴィエット博士も、平均所得は増加しているものの、課税所得が真の生活費を反映していないため、若い世帯や中流世帯は依然として大きな負担を抱えていると述べた。同博士によると、世帯控除の仕組みは消費者物価指数(CPI)のみに基づくべきではない。なぜなら、この指数は近年急増している住宅費、医療費、教育費といった生活必需品費の増加を十分に反映していないからだ。
ヴィエット博士によると、消費者物価指数(CPI)が20%変動した時点で調整するという提案は遅すぎるため、実際の変動を迅速に反映させるには、この水準を10%程度に引き下げる必要がある。さらに、ベトナムは、住宅ローン、家賃、生活必需品投資といった高額な支出を控除制度の対象に加え、適切な対象者、特に支出額の多い若年世帯を支援するという点で、地域諸国から学ぶことができるだろう。
累進課税制度について、彼は、現行の7段階の累進課税制度は税率が近すぎるため、多くの人々が苦しむという心理を生み出していると指摘した。これは、特に若い労働者の貯蓄・再投資意欲を減退させている。したがって、個人所得税法の改正は、真の公平性、意欲の喚起、そして適切な対象者への支援を目指し、より包括的なものとなる必要がある。
電子商取引税に焦点を当てる
グエン・ドゥック・ギア弁護士は、予算徴収の観点から、政府が公共投資のために多くの資源を動員する必要がある状況において、税基盤の改革と拡大に重点を置くべきであり、例えば電子商取引など、大きな潜在力を持つ分野を優先すべきだと指摘した。電子商取引は取引規模が拡大し、急速に発展している分野だが、固定収入の労働者への負担を増やし続けるよりも、経営を強化し、より効果的に活用する余地がまだ大きい。
納税者への圧力を軽減する
タイグエン省税務局(旧)は、累進税率の見直しに関する意見交換の過程で、低所得納税者の経済的負担を軽減し、生活の質の向上を支援するため、最初の3段階の税率を引き下げることを提案しました。具体的には、レベル1の税率を5%から2.5%に、レベル2を10%から5%に、レベル3を15%から10%に半減させることを提案しました。
同様に、ニントゥアン省(旧)人民委員会も、所得がわずかに増加した際に突然の「税金の急騰」を避けるため、階層間の税金格差を調整することを提案した。
出典: https://nld.com.vn/can-xem-xet-toan-dien-nguong-chiu-thue-196250723205604327.htm



![[写真] 土砂崩れに見舞われた国道14E号線で、通行可能な道路を確保するために丘陵を切り開く](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/08/1762599969318_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2025-11-08t154639923-png.webp)










































![[動画] フエのモニュメントが再開し、観光客を歓迎](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/05/1762301089171_dung01-05-43-09still013-jpg.webp)



































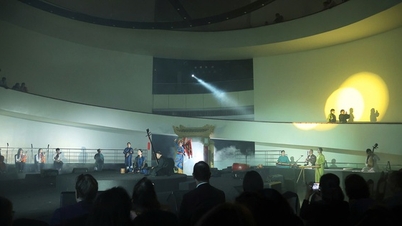





























コメント (0)