農業農村開発省(現農業環境省)堤防管理・暴風雨対策部の元副部長、ブイ・グエン・ホン博士は、自然災害防止および管理に関する法律第4条第3項に規定されている「現場」のモットーの誕生について語りました。
彼は、「4つの現場主義」の実践は、自然災害の予防・管理サイクル、特に対応と復旧段階において極めて重要な任務であると強調した。自然災害の予防・管理において、この主義はあらゆる機関、組織、個人、世帯、そして地域社会に適用される。
防災段階から各レベル、各分野、コミュニティ、各家庭において「4つの現場主義」を積極的に実践することは、自然災害への対応と復旧段階において極めて重要な成果をもたらすでしょう。「4つの現場主義」には、現場指揮、現場兵力、現場資材、現場物流が含まれます。

クアンナム省タンビン郡ビンハイ村における「暴風雨洪水予測に基づく早期行動」訓練。写真:防災管理局。
「4オンサイト」のモットーはいつ生まれたのですか?
この標語は1967年に制定され、 「遠くの水は近くの火を消せない」という諺に由来しています。これは、灌漑大臣ハ・ケタンが堤防局長グエン・ヴァン・ニエンに、タック・タット郡(旧ハ・タイ)のティック・ザン川を堰き止める訓練を組織するよう指示した事件に端を発しています。しかし、資材と労働力の不足により、堰き止め作業は失敗に終わりました。当時、一部の人々は「生半可な作業で、藁も残っていない」と評しました。
1971年8月の歴史的な洪水で、ハノイ市ジャーラム県のドゥオン川左岸のトーン水門と、ハバック市ジャールオン県のタイビン川右岸のニャットチャイ水門で決壊した堤防を緊急時に修復するために必要な資材が十分に動員されなかったときに、同じことが再び起こった。
現実には、洪水期の堤防建設事故は早期発見が遅れると、急速に拡大します。事故が検知されても現場にリソース(人員、資材、手段)が不足し、指揮・対応が抜本的でなく、タイムリーでない場合、当初は小さな事故だったものが、あっという間に大きな事故、ひいては大惨事へと発展する可能性があります。
この要請に応えるため、「4オンサイト」というモットーは、洪水・暴風雨対策の実務から生まれました。当初、このモットーは主に堤防の保全業務に重点を置いていました。
実際、1971年8月の洪水における堤防事故処理の組織化に関しては、自然災害や敵の攻撃による影響から堤防の安全を確保する必要性に応え、1973年に水資源省に就任したグエン・タン・ビン大臣は、洪水・暴風雨対策のための物資を保管するための倉庫システムの緊急構築を要請しました。これらの倉庫は、地域倉庫を含め、多くの地域への物資の輸送を容易にするために便利な場所に設置する必要があり、ルート倉庫は堤防ルート上に設置されました。

洪水と暴風雨の予防と制御においては、雨季と暴風雨期の前に、技術計画、資材、設備、人員、そして対応に必要な条件を整備しておく必要があります。写真:タン・トゥオン/ベトナム通信社
洪水や暴風雨の防止と制御のために確保されている資材の中には、鋼鉄製のバスケット、鋼鉄製のワイヤー、袋、鋼鉄製の杭、鍬、シャベル、防風灯など屋内に保管されているものもあれば、砕石、黄砂、砂利など屋根のない壁のある場所に保管されているものや、岩石など堤防沿いの屋外に置かれるものもあります。
これらの資材は予算から購入されます。毎年、堤防補修計画において、予算の一部が地方自治体に備蓄地の整備に割り当てられます。備蓄地は、堤防護工事に備えて、現地の堤防のたもとに造成されます。
堤防保護作業のための資源を動員するため、地方自治体は堤防沿いの世帯に竹や柵を用意するよう求めている。コミューンは数量を確認し、数え、各世帯に庭でそれらを保存するよう割り当てる責任がある。
洪水および暴風雨対策のための資材および設備の国家管理を担う機関は、堤防局傘下の資材部です。この部署は1974年に設立され、20世紀後半の1970年代まで活動を続けていました。1980年以降、洪水および暴風雨対策のための資材は地方自治体に直接管理されるようになりました。当時、堤防局には資材部はなく、計画局傘下の資材監視職員のみが配置されていました。
発足以来、風水害予防管理(現在の自然災害予防管理)における「4つの現場」のモットーの実施は各段階で異なり、次のようにまとめることができます。
「4つの現場」堤防保護から
この時期の防災対策は、我が国で頻繁に発生する最も危険な自然災害である洪水と風水害の防止に重点が置かれています。しかし、堤防のない地域や未整備地域における風水害対策における「4つの現場主義」は明確に定義されていません。
堤防防衛任務において、「4人現場」は、物資、人材、手段、設備における主導性、各レベル、各勢力の断固たる参加、現場での毅然とした指導により、効率性をもたらし、1986年の大洪水時にハバク省クエヴォー県カウ川右岸ノイドイ水門で発生した事故やバクタイ省フォーイエン県カウ川右岸第1水門で発生した事故などの重大事故を成功裏に処理した。
この期間の「4点即応」のモットーは、洪水期の治水工事に効果をもたらしたと言える。多くのインシデントを検知し、うまく対処することで、レベル3から特別レベルまでの主川堤防の安全を確保したが、2つの特別なケース、1986年8月26日の夜に発生した外堤防の決壊は例外であった。この堤防は主堤防より低い標高で設計されたものである。紅河の洪水が増水すると、バンコック水門が作動し、外堤防からバンコック洪水緩和区域に洪水を流し、その後、デイダムを通じて洪水を迂回させ、ハノイ水文観測所の紅河水位が標高13.2メートルを超えないようにする。そのため、外堤防区間の資材、手段、堤防保護計画などは、他の堤防のように準備されていない。

ラオカイ省ヴァンバンコミューン、ランチュット村における洪水防止のための堤防建設は、自然災害による被害の最小化に貢献している。写真:ニャンダン新聞
各レベル、各部門、各分野、そしてコミュニティ全体での自然災害予防と管理の実践活動を通じて得られた成果と課題は、各地域、各地方の自然災害の特殊性から、自然災害予防と管理における「4つの現場主義」を実行するという精神が、各レベル、各部門、各地方の現実に適応した計画をもって、あらゆるレベル、各部門、各家庭で積極的に実行される必要があることを示しています。
自然災害は、頻度、強度、種類の多様化、影響範囲の拡大など、ますます複雑化しています。さらに、地域や地方によって地形、地理的位置、社会経済状況、自然特性が異なるため、「4つの現場」のモットーは、それぞれの地域の自然災害の実態に合わせて実践されなければなりません。
実際、21世紀の最初の3年間(2000年、2001年、2003年)には、メコンデルタで連続して大洪水が発生し、人命、財産、インフラに甚大な被害をもたらしました。死者の中には、溺死した子供も数多く含まれていました。
自然災害の予防と管理に関する法律に制定する
この現実から、中央風水害対策指導委員会は地方に対し、集中的な保育を直ちに組織するよう要請し、青年連合に草の根レベルの婦人協会と調整して実施するよう指示した。
集中保育の組織化は、洪水多発地域の子どもたちの安全確保に成果をもたらしました。実際、メコンデルタの洪水発生時に無料の集中保育を組織化したのは、自然災害における脆弱層の安全確保という「4つの現場」のモットーを実践するためでした。

自然災害が発生したときに受け身になってパニックに陥らないように、想定される状況を練習して計画を立てましょう。
2000年のラー川・ラム川洪水、2002年の紅河水系・タイビン川洪水、マ川水系全域・タンホア省チュー川の大洪水、そして2007年にホアンロン川(ニンビン省)で発生した水位3に達した異常大洪水など、上記の堤防では数百件の事故が発生し、その多くが堤防の安全を脅かしました。しかし、綿密な対応計画の策定と、各レベルおよび専門機関からの緊密かつ継続的な指導により、「現場4点」の堤防保護方針が効果的に実施され、堤防の安全は確保されました。
1999年に中部沿海各省で発生した歴史的な洪水への救助、救援、支援活動の実践から見て、自然災害の予防と対策活動において、「4. 現場主義」は実践すべき多くの内容の一つです。しかし、このモットーは、各地域、各レベル、各分野の特性に密接に対応し、それぞれの自然災害の種類に適したものでなければなりません。
「現場4点」のモットーは、特に堤防工事において長年実践されてきましたが、2006年1月16日付政府政令第08/2006/ND-CP号第10条第7項dにおいて、正式に法的文書として規定されました。その後、「現場4点」は、2007年11月16日付首相決定第172/TTg号(2020年までの自然災害の予防、管理、軽減に関する国家戦略を承認)の指導原則第II部第3原則の内容にも規定されました。さらに、「現場4点」は、2013年自然災害予防管理法第4条第3項に法典化されました。この規定は、あらゆるレベルおよび分野における実施にとって非常に重要な法的根拠となります。
効果的な実施を確保し、特に気候変動の影響下における自然災害の予防と管理の要件を満たすためには、「4現場」のモットーを、各地域および各自然災害の特性に応じて、各レベル、セクター、分野の自然災害予防と管理の計画およびスキームと多様で、柔軟で、実現可能で、同期した方法で策定する必要があります。たとえば、洪水と浸水の予防と管理の4現場、技術インフラ事故の処理の4現場、暴風雨と熱帯低気圧の予防と管理の4現場、鉄砲水と土砂崩れの予防と管理の4現場、干ばつと塩水侵入の予防と管理の4現場、寒冷気候の予防と管理の4現場、地震と津波の予防と管理の4現場などです。地形、気候、自然災害の特性が異なる地域における4現場のモットーは、状況に応じて策定し、有効性と実現可能性を確保する必要があります。
家庭やコミュニティにおいては、地域で発生する自然災害の実態を踏まえ、自然災害の予防と制御で培った経験を活かし、「他人が助けに来る前に、まず自分を救う」という方向で、家庭や家庭集団(家族間)規模での四方八方標語を積極的に策定します。
出典: https://nongnghiepmoitruong.vn/dung-thanh-luy-truoc-thien-tai-bai-4-chuyen-luat-hoa-phuong-cham-4-tai-cho-d783199.html

















































































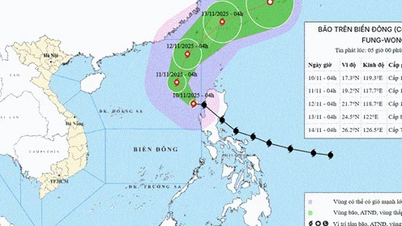






















コメント (0)