若い世代との10年間の友情。
2004年に日本で始まった「水育(みずいく)」プログラムは、2015年にサントリーペプシコがベトナムで開始し、小学生に節水について啓発する、長く記憶に残る活動へと発展しました。ハノイ市タンオアイ区とミードゥック区での課外授業から始まったこのプログラムは、過去10年間で全国100万人以上の小学生と数万人の教師や保護者に広がりました。
このプログラムのユニークな点は、その提供方法にあります。水、環境、そして自然に関する知識は、もはや単なる理論ではなく、絵を描いたり、ゲームをしたり、実際に体験したりするなど、魅力的なアクティビティを通して、生活に溶け込んでいきます。その結果、水資源の保全と環境保護のメッセージは記憶しやすく、実践しやすく、そして永続的な習慣となります。
教師をプログラムの推進力として、標準化された授業計画システムを通して教材、ツール、そして授業運営方法を提供し、環境保護の内容を魅力的な授業に組み込む支援を行っています。多くの教師が「水育 ― きれいな水が大好き」の活動に関わり、生徒たちの意識の変化とプログラムの成長を目の当たりにしてきました。水育の教育モデルは生徒を中心に据え、学校での指導、学校外での自然体験、そして学校施設の改善を通じたきれいな水へのアクセス向上という、包括的なアプローチで設計されています。

2023年は、文部科学省が水育教材を正式に承認し、小学校のカリキュラムに組み込んだことで、大きな転換点となりました。これは、この取り組みの実用性と持続可能性を明確に示すとともに、将来的に何百万人もの生徒たちに届く道を開くものです。
水育は、水と自然への愛を育むことを目的とした課外活動を通して、国立公園で生徒たちを対象とした魅力的な「森の授業」を数十回開催してきました。2024年からは、農林水産省と連携し、この体験学習をさらに充実・拡大し、「水育で自然体験」を全国の国立公園で実施しています。この活動は、生徒や若者に森林生態系と直接触れ合い、森林、水資源、そして人間の生活の関係性を理解する機会を提供します。生徒たちは、水、森、そして生態系に関する物語を見て、触れ、心を広げられます。水育は教室での教育にとどまらず、実践的な体験を通して、若い世代が水資源保全の重要性を深く理解できるよう支援しています。

「水の保全 - 未来を育む」コンテストで創造力を解き放ちましょう。
10年にわたる粘り強い取り組みを経て、「水育(みずいく)」は、環境教育活動の揺るぎない活力を証明しました。政府機関の支援、地域社会からの熱心な反応、そしてサントリーペプシコの長期的なコミットメントにより、このプログラムは今後もその影響力を拡大していくでしょう。
10周年を迎えた「水育(みずいく)~きれいな水が大好き~」プログラムは、在ベトナム日本大使館の後援を受け、2025年に「水資源を守り、未来を育む」と題したコンテストを開催します。このコンテストは幅広い参加者を対象としており、小学生は絵を描くことで参加でき、教師は独創的な授業プランを考案し、16歳から40歳までの若者や市民は、アートワークやポスターを通してメッセージを表現することができます。
このコンテスト (https://www.facebook.com/share/p/16VQ7fEzYp/) は、芸術的または教育的なプラットフォームであるだけでなく、コミュニティが共通の問題である水資源について意見を表明できる場でもあります。
最も期待されているのは、2025年9月30日から10月5日までハノイ・ブックストリートで開催される「水の保全 ― 未来を育む」展です。展示スペースでは、コンペティションの優秀作品に加え、過去10年間「水育」に関わってきた生徒、教師、そして地域住民からの心温まるストーリーが展示されます。
この展覧会は単なる展示ではありません。来場者が展示物を鑑賞しながら、「身の回りの水資源を守るために、私はこれまで何をしてきたのか、そしてこれから何をしていくのか」という問いに対する自分自身の答えを見つけることができる体験型の旅として設計されています。これはまた、水育が水資源の保全は個人や団体だけの責任ではなく、地域社会全体の共同の努力であるというメッセージを伝える方法でもあります。
出典: https://tienphong.vn/mizuiku-em-yeu-nuoc-sach-tron-10-nam-cau-chuyen-nao-dang-cho-ban-o-trien-lam-ha-noi-post1773483.tpo






![[画像] ベトナムの多彩なイノベーションの旅](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F14%2F1765703036409_image-1.jpeg&w=3840&q=75)























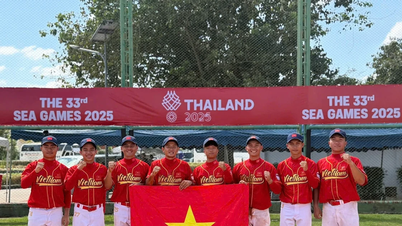


















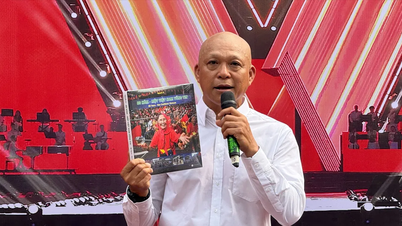








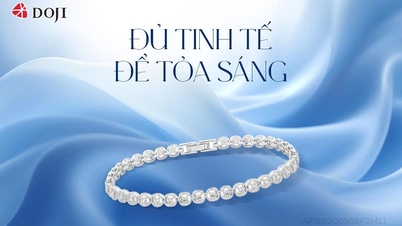















![[画像] ベトナムの多彩なイノベーションの旅](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/14/1765703036409_image-1.jpeg)




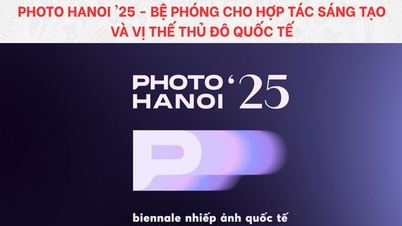















![[インフォグラフィック] ドンナイ省農民協会常任委員会(2025~2030年度)のプロフィール](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/14/1765708210139_thumbnail_ban_thuong_vu_sua_20251214164836.jpeg)















コメント (0)