「あなたの笑顔を見ると、私も幸せな気持ちになります…」
林正夫さんは、2024年5月から特別支援教育研究開発センターでのボランティア活動を開始しました。ベトナムを選んだ理由について、林さんは「親しみと絆を感じる土地」と語りました。「大学院時代に国際協力を専攻し、カンボジアの子どもの権利について研究するため、1年近くカンボジアに住んでいました。その間、何度かベトナムを訪れ、とても親しみやすい国だと感じました。ベトナムの人たちはとても親切でした。また、大学時代に保育と教育を学び、10年間、障がいのある子どもたちの支援に携わってきました。自分の経験が、ベトナムの子どもたちのために少しでも役に立てればと思っています」と正夫さんは語りました。
|
ダナン市障害者・孤児・貧困者支援協会傘下の特別支援教育研究開発センターで子どもたちを支援する林正夫さん。写真提供:JICA |
マサオさんによると、ベトナムに来るボランティアの多くにとって最大の障壁は言語だ。活動開始前に日本とダナン市でベトナム語を学んだものの、センターでの活動に直接参加すると、コミュニケーションのギャップに陥りそうになったという。「最初は同僚の言うことも、生徒たちの会話も全く理解できず、本当に大変でした」とマサオさんは振り返る。しかし、ベトナム人の同僚たちが、ゆっくり話したり、翻訳ツールを使ったり、Zaloでメッセージを送って理解できるようにしたりと、粘り強くサポートしてくれたおかげで、マサオさんは徐々にその壁を乗り越えていった。約1年後には、ベトナム人教師の直接のサポートなしに、教室に立って生徒たちを指導できるようになった。
マサオ先生の困難は、センターの生徒グループの特性にも起因しています。彼らは主に知的障害のある子どもたちで、8歳から18歳までの男子です。この時期は、心理、生理、行動、特にジェンダーに関連する行動において、多くの変化が起こる時期です。「子どもたちを導き、寄り添うことは、ここの教師全員にとって本当に大きな挑戦です」と彼は語りました。しかし、10年以上障害のある子どもたちと接してきた経験を持つマサオ先生とは、自然な繋がりが築けます。ほんの少し触れ合っただけで、子どもたちは積極的に先生に近づき、手を握ってゲームに誘ったり、サインを使って欲しいものを伝えたりしました。「こうしたサインを理解し、子どもたちの願いに応え、笑顔を見ると、嬉しくなり、やる気が湧いてきます。この気持ちは、日本であれベトナムであれ、同じで、変わることはありません」とマサオ先生は語りました。
センターでの最初の日々を振り返ると、正雄氏は生徒たちの自発的な反応に大変驚かされました。多くの生徒たちが怒ったり、叫んだり、教師の対応を困難にするほどの激しい行動に出ました。こうした行動は長年続いていたため、介入して変化させるのは非常に困難でした。しかし、忍耐強く注意深く観察することで、正雄氏は徐々に生徒たち一人ひとりに適切なアプローチを見つけ出していきました。彼は、忘れられないある事例を次のように語りました。「瞑想中によく怒る生徒がいました。観察を続けるうちに、その怒りは、物を正しい場所に置いてほしい、好きな音楽を聴きたいといった個人的な好みが満たされていないことに起因していることに気づきました。私がそれらのニーズを理解し、適切なレベルで満たそうと努めると、彼は徐々に怒らなくなり、落ち着いていられる時間がどんどん長くなりました。そのような瞬間に、私は自分がやっている仕事に真に意義を感じました。」
希望の種を蒔く
センターの専門マネージャーであるグエン・ティ・リュウ先生は、「マサオさんはセンターで教える4人目の日本人ボランティアです。着任当初から、生徒一人ひとりを丁寧に観察し、一人ひとりを訪問して彼らの状況やニーズをより深く理解することで、センターと生徒の家族の間に緊密な関係を築いてきました。そのため、保護者や生徒から厚い信頼を得ています。これまでの専門知識と経験に加え、ベトナム語の学習とベトナム文化の理解にも真剣に取り組み、生徒に効果的にアプローチしています。私たちは、彼の学ぶ姿勢と責任ある仕事への姿勢に心から感銘を受けています」と述べました。
|
ダナン市障害者・孤児・貧困者支援協会傘下の特別支援教育研究開発センターで子どもたちを支援する林正夫さん。写真提供:JICA |
リュウさんは、センターの教師を見つけるのは容易ではなかったと付け加えました。ここの生徒は主に男子生徒で、思春期にあるため、「教える」だけでなく「なだめる」ことも必要です。そのことを理解したマサオさんは、生徒一人ひとりの能力とニーズに基づいて、個々の能力を伸ばすことに常に気を配っています。このアプローチのおかげで、多くの生徒が、特に行動制御と積極的なコミュニケーションにおいて目覚ましい進歩を遂げています。また、各レッスンで生徒一人ひとりに適した教材を選ぶことにも細心の注意を払っています。
センターが認めたもう一つの良い変化は、生徒たちのための屋外活動の企画です。「センターの教師のほとんどは女性で、生徒は主に男性なので、以前は生徒たちを屋外に連れ出すのに苦労していました。マサオ先生が来てから、私たちはずっと自信を持つようになりました。柔軟性と体力が必要な状況でも、先生は私たちをしっかりとサポートしてくれます。おかげで、生徒たちを定期的に屋外に連れ出し、安全な移動スキルを身につけさせ、より多様な体験活動に参加させることができるようになりました」とリュウさんは語りました。
林正雄氏の努力と貢献は同僚や保護者から高く評価されていますが、本人は謙虚な姿勢を崩しません。何よりも嬉しいのは、自身の専門的な提案が同僚に受け入れられ、実践され、子どもたちの迷惑行為が大幅に減少していく様子を見ること。「残りの任期で、子どもたちが楽しく学びながら自立したスキルを身につけられるような支援教材をデザインしたいと思っています。現在、同僚たちと進路指導の一環として、子どもたちに麦わらバッグ作りを指導しています。商品が売れれば、センターのことをもっと多くの人に知ってもらい、子どもたちが将来自立できる機会を増やすことができると期待しています」と林正雄氏は語りました。
ベトナムにおけるJICAボランティアプログラムの30年間は、何百人もの人々が静かに貢献してきた道のりです。数々の素晴らしい物語の中でも、ダナン市で障がいのある子どもたちに寄り添い、優しい笑顔を向ける日本人教師、林正夫さんの姿は、友情の鮮烈な証であり、国境を越えて良いものを分かち合い、広めたいという思いの証です。林さん自身も謙虚に認めているように、彼の貢献は小さなものかもしれませんが、生徒たち、センター、そして障がいのある子どもたちを支援する人々にとって、それは大切で永続的かつ意義深い前進です。子どもたちが大人へと成長していく過程で、一つ一つのレッスン、あらゆる経験、そして自立へのあらゆる機会に、林さんは愛情と献身を注いでくれています。
JICAボランティア派遣事業は、日本政府の政府開発援助(ODA)の一環として、国際協力機構(JICA)が実施するものです。この事業は、開発途上国のニーズに応えるため、関連する専門知識、知識、経験を有し、受入国の社会経済開発および地域社会の福祉向上に貢献する意欲のある日本人を募集することを目的としています。ベトナムでは1995年から実施されており、過去30年間で計765名のボランティアがベトナムに派遣され、平均2年間の派遣期間で様々な分野で活動しています。活動には主にベトナム語が用いられています。現在、41名のボランティアが現地での支援活動に参加しています。 |
出典: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-17/thay-giao-nhat-ban-va-hanh-trinh-vi-tre-khuet-tat-1013360








![[写真] ファム・ミン・チン首相が中央競争・報奨評議会の第15回会議を議長として開催](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F27%2F1764245150205_dsc-1922-jpg.webp&w=3840&q=75)
![[写真] ルオン・クオン国家主席、ラオス建国記念日50周年記念式典に出席](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F27%2F1764225638930_ndo_br_1-jpg.webp&w=3840&q=75)










































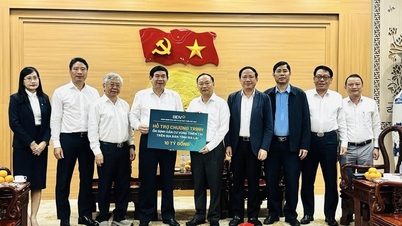











































![[オンラインフォーラム] タイグエン省における民族政策の効果的な実施](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/28/1764296450164_30729563efc1639f3ad0_20251128090933.jpeg)














コメント (0)