月曜日の朝、思わず立ち止まってしまうような瞬間に遭遇しました。校門に立つ教師が、6年生の靴紐を結ぼうと身をかがめていました。少年は擦り切れたリュックサックを握りしめたまま、車の流れを避けて身をかわしました。教師は一つ一つ丁寧に紐を結び、膝を撫でながら微笑んで言いました。「さあ、教室へ行きましょう」
ほんの数秒のことだったが、生徒の目には感謝と温かさが宿っていた。その光景を見て、私は教師にまつわる数え切れないほどの小さなエピソードを思い出した。あまりにも些細なことで、当事者自身も忘れてしまうこともあるかもしれない。しかし、それでも「人を育てる」という言葉について考えさせられるのだった。
最近、イノベーションやアウトプット基準、デジタルスキルといった話題は多く聞かれますが、子どもたちが教師の手によって真に少しずつ育てられている、 教育の「ミクロ」な部分に目を向けることはほとんどありません。多くの人は、教師という職業は授業計画と成績だけで成り立ち、責任を果たせばそれで十分だと考えています。しかし、私が出会った様々な話から、教師という職業は、誰からも強制されないこと、例えば、一緒に食事をすること、貧しい生徒にスリッパをあげること、苦労している生徒に真夜中に送る励ましのメールなど、実に様々なことの積み重ねの中にあることに気づきました。まさに「第二の親」のような精神が、心に深く刻まれているのです。

こうした沈黙の行動は、幾重にも重なる原因から生じています。地域差が依然として顕著な状況の特殊性も一因となっています。都市部では、教師たちは10代の若者の心理的プレッシャーに苦慮しています。一方、農村部では、食料、衣服、長距離移動、貧困といった問題が静かに深刻化しています。高地では、教師たちは山道を米を運び、寄宿生の昼食を作っています。その他の地域では、教師たちは鬱、校内暴力、そしてソーシャルネットワーク時代の生徒の孤独感にさえ直面しています。学校心理学のデータによると、情緒問題を抱える子どもの割合は年々増加していますが、支援体制は非常に脆弱です。こうしたギャップの中で、教師たちは「精神的な門番」のような役割を担うことになります。この役割は、公式には定義されていません。
物語の奥底を覗いてみると、最も大切なのは常に人です。毎朝お腹を空かせて授業に来る生徒に、自分の弁当の半分を分け与える先生。何ヶ月もの間、生徒の朝食代を黙々と返済する先生。午前1時に助けを求めるメッセージを受け取ると、慌ててシャツを着て、うつ病でパニックになっている生徒の家へ駆けつける先生。あるいは、辺鄙な村で、まるで我が子の世話をするかのように、一人ひとりの生徒にお風呂に入れ、爪を切り、衛生習慣を教える先生。こうした些細なことは、成果として数えるのは難しいかもしれませんが、生徒を人生に結びつける糸なのです。ゲーム中毒の生徒が先生にサッカーチームに引き抜かれ、キャプテンの役割を与えられた時、彼は頑張る新たな理由を得たのです。
これらが認識されなければ、払う代償は計り知れないものとなるでしょう。生徒にとっては、最も傷つきやすい時に見捨てられたと感じることを意味します。教師にとっては、沈黙の犠牲が理解されないことで疲弊することを意味します。そして社会にとっては、最も重要な文化の柱の一つである教師への信頼を失うことを意味します。情緒的なサポートを受けずに育つ若い世代は、脆弱で、容易に方向感覚を失い、自信を失いやすくなります。これは、教育だけではカリキュラム改革によって補うことができないものです。
しかし、こうした困難の中にも、依然として無数の明るい兆しが見られます。注意深く観察するだけで、小さなことから始まる多くの前向きな変化に気づくでしょう。親は子どもを他の子どもと比較するのをやめ、日々の努力を認めるべきです。学校は、記録や報告書に頼りすぎることなく、教師が生徒と交流し、生徒の声に耳を傾ける機会をもっと作るべきです。社会は、感謝の気持ちを花束で示すだけでなく、教師の時間、健康、そして評判を尊重することで、教師に親切を示すべきです。そして、より広い視点で見ると、学校心理を支援する政策や、恵まれない地域の教師の待遇改善は、教師が職務にさらに献身する助けとなるでしょう。
週明けの朝、校門の前で靴紐を結ぶためにかがみ込む先生の姿を思い出すと、あれは単なる偶然ではなかったと思えてきます。それは、先生が人生の中で幾度となくかがみ込んできたことの象徴なのです。砕け散った夢を拾い上げるためにかがみ込み、倒れた子供を抱き上げるためにかがみ込み、生徒の目線に立って「あなたを信じています」「あなたを信じています」と声をかけるためにかがみ込みました。そして、生徒が成長して戻ってきて、先生を抱きしめ、声を詰まらせながら「先生がいなければ、私は今日ここにいません」と呟く時、それこそが「人を育てる仕事」という言葉の真髄を最もよく表している瞬間でしょう。名声に彩られた仕事でも、光明も乏しい仕事でも、人の運命を変えるには十分な力を持つ仕事。こうした小さなことを守り、肩に置かれた手を大切にし、先生方に誇りに思ってもらえるような生き方をすること。それこそが、私たち一人ひとりが送ることができる、最も美しい感謝の気持ちなのかもしれません。
出典: https://vietnamnet.vn/cha-me-thu-hai-trong-su-nghiep-trong-nguoi-2464298.html


















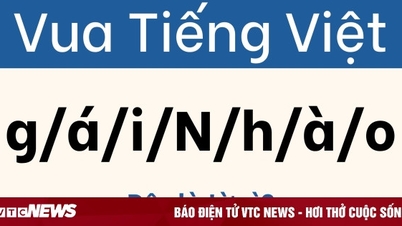















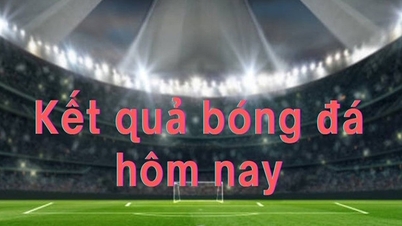










































































コメント (0)