編集者注: 第14回党大会に提出された政治報告草案では、「国家経済が主導的な役割を果たす」と「民間経済が最も重要な原動力となる」という二つの概念が、経済の二つの並行する柱として引き続き強調されている。 元国会経済委員会副委員長のグエン・ヴァン・フック氏は、ベトナム・ウィークリー紙の取材に対し、核心的な問題は「誰が誰よりも大きいか」ではなく、原則に従って運営される市場の枠組みの中で、2つのセクターが共に役割を果たせるよう、どのように制度を設計するかであると語った。 |
政治報告草案には、非常に重要な点が二つあります。一つ目は、民間経済が経済の最も重要な原動力であることを引き続き強調することです。二つ目は、国家経済の主導的役割を強調することです。草案で求められているように、各セクターが対立を生じさせることなく真にその役割を果たせるようにするためには、これら二つのセクターをどのように運営すべきだとお考えでしょうか。
グエン・ヴァン・フック氏:我が党は、どちらも正しく、かつ互いに矛盾しない二つの視点を提示しました。民間経済が経済の最も重要な原動力の一つであることを認めることは、国家経済の主導的役割を否定するものではありません。 ト・ラム書記長は、各セクターにはそれぞれ独自の使命があり、それぞれの役割を適切に果たして初めて、経済は均衡を保ち、持続的に発展していくと明確に述べています。
これまでの現実は、民間部門が成長、雇用、そしてイノベーションの重要な原動力であることを示しています。我が党は、民間経済発展に関する別個の決議を採択するにあたり、思考を大きく前進させ、この部門に対する認識と姿勢の変化を示しました。しかしながら、書記長は同時に、主導的な役割を果たし、大きな均衡を確保し、社会主義を方向づけ、民間部門では担えない社会目標を実現する国家経済の役割を忘れてはならないと強調しました。
「国家経済」という概念を正しく理解することが重要です。国有企業はこのセクターの一部に過ぎません。国家経済には、有形無形を問わず、あらゆる国家資源が含まれます。土地、石油・ガス、鉱物といった有形資源はよく議論されますが、開発空間、周波数、空域、海域、データインフラ、デジタル空間といった無形資源も、新時代において極めて重要な資源です。これらは国家の主権と発展の安全に直結するため、国家が保有・管理すべき領域です。国家経済セクターがこれらの「目に見えない資源」を効果的に管理・活用できるよう、より明確な制度化が必要です。

グエン・ヴァン・フック氏:国家経済の主導的役割を引き続き強調する上で、第14回党大会の文書は「主導」の意味合いを、新たな発展の実践に適した、開放的で柔軟な方向性へと明確にする必要がある。写真:レー・アン・ズン
主導的役割については、厳格に捉えるのではなく、発展段階に応じて柔軟に運用する必要がある。民間部門が困難や危機に直面した際には、国家経済は「戦場に飛び込む」必要がある。例えば、公共投資の加速、あるいは国家による救済や企業買収への参加などである。
逆に、民間部門が力強く、効果的かつ創造的に発展する場合には、国家経済はマクロバランス、社会保障、そして民間部門が望まない、できない、あるいは利益を上げられない分野の役割に後退すべきである。ここでの主導的な役割は「支配」ではなく「主導」である。四人兄弟の家庭で、子供が幼い頃は長男が責任を担うのと同様である。しかし、成長するにつれて、長男の役割も変化し、支援と調整へと移行する。
運営メカニズムに関して、政治報告草案は非常に進歩的な点を強調しました。それは、資源配分の基盤として「要求・提供」メカニズムではなく、市場メカニズムを活用する必要があるという点です。市場は資源配分において最も効果的な手段ですが、固有の欠点も抱えています。民間企業は収益性の高い分野にしか投資しませんが、市場は辺鄙な地域や収益性の低い分野には参入できません。したがって、国家はこれらの不足部分を補うために介入しなければなりません。これが、社会主義志向の市場経済における国家経済の主要な機能です。
市場メカニズムが有効に機能するための前提条件は、制度である。市場は、透明性、安定性、規律、公正性を備えた制度的基盤の上に機能して初めて、有効に機能する。制度が歪んでおり、市場規律が未だ形成されていない場合、効果的な資源配分は期待できない。したがって、「市場メカニズムを用いて資源を配分する」という表現は正しいが、それには条件がある。それは、市場が適切に機能するためには、制度が十分に成熟していることである。
したがって、第14回党大会の文書は、国家経済の主導的役割を引き続き主張する際には、新たな発展の実践と一致する、開放的で柔軟な方向への「主導」の意味合いを明確にする必要がある。つまり、国家は市場に取って代わるのではなく、主導的かつ調整的な役割を果たし、経済の社会主義的方向性を保証するということである。
第14回党大会の文書草案では、土地、労働、科学技術、金融、不動産といった「生産要素市場の発展と改善」が強調されています。しかしながら、現在のベトナムでは、これらの市場が真の意味で「市場」として機能していないという意見が多く見られます。「生産要素市場」を正しく理解するにはどうすれば良いのでしょうか。また、この文書が重視する「市場」と「市場制度」の違いは何でしょうか。
これは第14回党大会文書の中で非常に注目すべき点です。「生産要素市場の整備」について語る際には、まず市場と市場制度という二つの概念を正しく理解する必要があります。
市場は客観的です。ニュートンのリンゴの法則のように、需要と供給、価格と競争という自然法則に従って存在し、機能しています。ニュートンは重力を創造したのではなく、発見したに過ぎません。市場についても同じことが言えます。誰もそれを「創造」することはできません。市場を特定し、法則に従って機能するように調整することしかできません。
市場制度は、法律、政策、規則、社会規範、組織制度といった人間が構築した産物です。市場はこうした制度的枠組みなしには機能しません。例えば労働市場において、労働法、契約、賃金、保険、退職年齢に関する規制がなければ、市場は混沌とし、歪んでしまうでしょう。
言い換えれば、市場は経済の自然法則であり、制度はその法則が公正かつ効果的に実施されるための条件である。制度が歪めば、市場も歪められる。だからこそ、本文書は、各分野だけでなく、開発モデルの基盤レベルにおいても、制度の役割を強調しているのだ。
言い換えれば、市場は経済の自然法則であり、制度はその法則が効果を発揮するための条件である。第14回大会の文書が制度に焦点を当てているのも、同様の理由からである。生産要素の市場が依然として古い制度的制約に「縛られている」限り、近代的な市場経済は存在し得ない。
先ほど分析されたように、根本的な問題は市場そのものではなく、市場制度にあります。では、ベトナムの生産要素市場が真に市場メカニズムに沿って機能するためには、今後、制度と政策はどのような方向に調整されるべきだとお考えですか?
市場がルールに従って機能するためには、同時に制度化されなければなりません。つまり、国家は、需要と供給の法則が機能するために、十分に広範で透明性のある法的枠組みと環境を整備しなければなりません。
ベトナムでは、多くの要素市場が未だに未完成である。これは需要や供給の不足ではなく、制度上の制約によるものだ。土地市場は依然として行政の決定に左右され、科学技術市場には知的財産の価格決定メカニズムが未整備である。労働市場は偏見と硬直的な規制に支配されており、金融市場は依然として行政の枠組み内に限定されており、企業にとって多様なツールが不足している。
制度とは、法律だけでなく、公式・非公式を問わず社会規範も含みます。例えば、職場におけるジェンダーバイアスやビジネスにおける失敗への恐怖などは、市場の発展を阻害する「ソフトな制度」です。したがって、「市場化」は「制度化」と密接に関連し、法律の改正、考え方の変革、そして古い制約の撤廃が不可欠です。
重要なのは、この文書が同期化を明確に認識している点です。個々の市場だけでなく、土地、労働、金融、科学技術といった生産要素全体における制度を整備し、それらが調和し、相互作用し、互いに支え合うようにすることです。そうして初めて、市場は資源配分と開発促進のための真に効果的な手段となるのです。

土地は国民全体の所有物であり、国家によって管理されています。したがって、国家は「本来の価格」、つまり資源の真の経済的・社会的価値を正確に反映する主要な価格を決定する責任を負います。写真:ホアン・ハ
委員長、現実には、土地価格が「市場価格に従って」決定されると、不動産価格が急騰し、資本フローの歪みや開発資源のボトルネックが生じます。一方、中央委員会決議18-NQ/TWは、「市場原理に従って土地価格を決定するためのメカニズムと方法」がなければならないと規定しています。この2つの理解はどのように異なるのでしょうか。また、誤って適用された場合、なぜ経済に悪影響を及ぼす可能性があるのでしょうか。
これは土地法改正における極めて核心的な問題です。「市場価格に準じる」と「市場原理に準じる」は似た意味を持ちますが、本質的には異なります。「市場価格に準じる」とは、取引価格を基準とすることを意味しますが、ベトナムの状況では、投機や集団の利益によって取引価格が容易に高騰してしまいます。「市場原理に準じる」とは、評価方法が需給、収益性、土地利用効率の法則に基づく必要があることを意味します。つまり、操作された価格を模倣するのではなく、真の価値を反映する必要があるということです。
不透明な市場において取引価格を基準とすれば、必然的に歪みが生じます。土地価格は高騰し、資本は誤った方向に流れ、実質的な生産企業は土地にアクセスできず、投機家が利益を得ることになります。そのため、中央委員会は決議19-NQ/TW(2012年)の要約報告書において、「2013年土地法は『党の決議』の精神を完全には実現していない」と指摘しました。この法律は「市場価格」と「市場原理」を同一視しています。
決議18-NQ/TWは、この問題を非常に明確な要件によって克服しました。「市場原理に従って土地価格を決定するためのメカニズムと方法が存在しなければならない」。つまり、国は特定の価格を直接決定するのではなく、土地価格が投機や縁故主義に影響されずに実際の使用価値を反映することを確保するための制度的枠組み、データベース、基準、そして価格決定プロセスを構築しなければならないということです。
土地は国民全体の所有物であり、国家によって管理されています。したがって、国家は「本来の価格」、すなわち資源の真の経済的・社会的価値を正しく反映する一次価格を決定する責任を負います。市場における二次取引は、この本来の価格に基づいて需給バランスに応じて行われます。国家の役割は、土地市場の「リズムを維持する」ことであり、価格が過度に高騰してマクロ経済の不安定化を招くことがないように、また価格が抑制されて資源の過剰供給を引き起こすことがないようにすることです。
次へ:制度を国家競争力に変える:その根源は人にある
ベトナムネット
出典: https://vietnamnet.vn/khi-the-che-la-diem-can-bang-giua-nha-nuoc-va-thi-truong-2461496.html






































































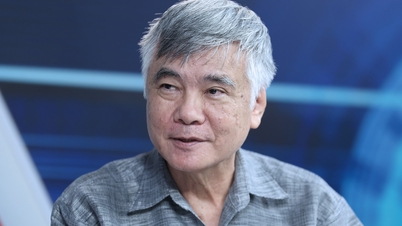






























![ドンナイ省一村一品制への移行:[第3条] 観光と一村一品制製品の消費の連携](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762739199309_1324-2740-7_n-162543_981.jpeg)






コメント (0)