
ワークショップで議論する学者たち
ド・フン・ヴィエット外務次官は開会の辞で次のように述べた。「過去15年間、東海に関する一連のセミナーは、地域および国際の専門家が率直かつ友好的に会い、意見交換し、共通の理解を深め、相違点を縮小する機会を創出してきました。今後、この対話は、重要かつオープンで包括的かつ創造的な地域海洋安全保障フォーラムとして発展していくことが期待されます。
ド・フン・ベト副大臣は、現在、世界の注目はインド太平洋地域に移り続けており、同地域は世界の成長の「中心」となり、世界の復興と将来の繁栄の重要な原動力となっていると述べた。しかし、その未来は、一般的に、そして特に地域の海洋空間における平和と持続可能な安定なしには保証できない。国連のグテーレス事務総長によれば、今日、戦略的競争は「大きな分裂」と「大きな亀裂」を生み出している。世界の多くの地域で紛争が起きています。インド洋から太平洋に至る海洋空間においては、対立や紛争のリスクは避けられません。このような状況では、海上の潜在的な脅威を継続的に特定し、新たな課題に対処するために既存の協力メカニズムを見直し、それらの脅威を防ぐために協力して行動する必要があります。
15年前と比べて、東海の状況はより複雑になり、解明すべき新たな「グレーゾーン」が数多く出現している。さらに、東海は依然として多くの潜在的な協力の機会を提供する地域です。特に、国家管轄権外区域における生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する新たな協定は、各国が海洋に対して共有する懸念の証です。ベトナムは最初の署名国の一つであることを誇りに思います。その文脈において、副大臣はワークショップのテーマの選択を高く評価しました。協力を通じてのみ、東海の色を「灰色」から「緑」へと変え、 平和と持続可能な発展に向けて貢献できると強調した。そのためには、1982 年の海洋法に関する国際連合条約 (UNCLOS 1982) に反映されている国際海洋法を尊重し、遵守することが重要です。
これまで、ベトナムとASEAN諸国は常に、安定したルールに基づく海洋空間を含む地域秩序の構築に努めてきました。ベトナムは、ASEANが最近採択した「インド太平洋に関するASEANアウトルック」と「海洋協力ビジョン」の実現と効果的な実施を強く支持する。同時に、ベトナムは二国間、多国間、新たなメカニズムを通じて、共通の目標に向けた新たな取り組みを常に支持しています。
ワークショップで講演したドイツ外務省東アジア・東南アジア・太平洋委員のマルティン・テュメル氏は、東海における最近の緊張の高まり、特に2023年10月22日にフィリピンの排他的経済水域(EEZ)で中国海警局と海上民兵の船舶がフィリピンの船舶と衝突した事件について懸念を表明した。テュメル氏は、繁栄を確保し、地域諸国の協力を必要とする国際法に基づく地域秩序を形成するためには、1982年の国連海洋法条約(UNCLOS)と、UNCLOS付属書VIIに基づいて設置された仲裁裁判所による2016年のフィリピンと中国の間の南シナ海仲裁に関する裁定を完全に遵守する必要があると改めて強調した。
代表団はまた、15年前には国際社会から大きな注目はなかったとも述べた。東海は地域諸国間の二国間紛争とみなされており、各国は紛争管理措置にあまり注意を払っていなかった。しかし、近年、東海問題は多くの新たな要素と様相を見せている。中国は裁定を認めず、九段線の主張を強行し、最近ではそれを破線であると発表したため、紛争は引き続き緊張した状態にある。海上では、すべての関係者が綿密な準備を行い、最新の船舶、衛星、ドローンなどの高度な機器を使用して、自らに有益な情報を記録し、公開する必要がある「グレーゾーン」活動が数多く存在します。東海は現在、紛争の危険性が高まっている国際問題とみなされており、紛争が起これば、それは容易にエスカレートし、拡大するだろう。同時に、各国は、東海地域における締約国の行動規範(COC)の構築プロセスなど、紛争管理措置の推進に関心を高めており、このプロセスは一定の進展を見せている。しかし、COC交渉においては、適用範囲、法的有効性、執行メカニズム、第三者の役割など、依然として議論の余地のある問題がいくつか残っている。上記の新たな側面と要因により、東海の問題は、世界的な経済的・戦略的競争、そしてインド太平洋地域における東海の役割と地位が高まっているという状況の中で、国際社会と地域社会の両方からますます注目を集めるようになっている。
平和な
[広告2]
ソース



![[写真] わだち掘れを補修したトゥドゥック市タンロン橋のクローズアップ](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/19/086736d9d11f43198f5bd8d78df9bd41)



![[写真] ルオン・クオン主席がレ・カインハイ大統領府長官に党員40年記念バッジを授与](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/19/a22bc55dd7bf4a2ab7e3958d32282c15)





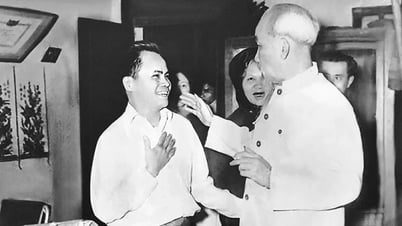






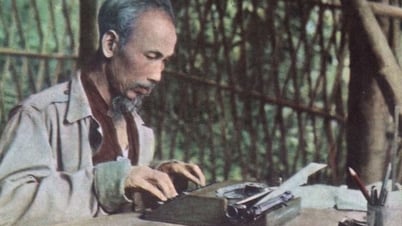










































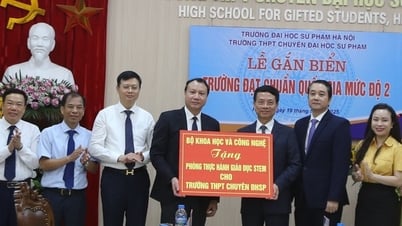



















![[ビデオ] - 貿易関係を通じてクアンナム一極集中生産物の価値を高める](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/17/5be5b5fff1f14914986fad159097a677)



コメント (0)