この一見シンプルな発言は、今日の我が国の創造活動全体の「底流」に触れています。世界が芸術を精神的な価値としてだけでなく、 経済資源や国家のソフトパワーとしても捉えるようになった創造の時代において、私たちは古い道を歩み続けることはできません。
我が国における文化芸術の管理は、長きにわたり行政色が強かった。あらゆる創作活動は、承認、評価、許可といった制度を経なければならず、それとは異なる表現は「センシティブ」あるいは「一線を越えた」とみなされる。こうした仕組みは、ある歴史的時期には、方向性を維持し、思想的基盤を守る役割を果たしていた。しかし、国が革新、統合、創造性の時代を迎えると、徐々に発展の障壁となっていった。創造性が恐怖に包まれると、芸術は安全な色調と馴染みのあるパターンにとどまり、突破口を開かず、新鮮で開かれた芸術を期待することは難しくなる。
問題の根源は、私たちが依然として文化芸術を「育成」すべき空間ではなく、「管理」すべき分野と捉えていることにあります。しかし、今日の世界は変化しました。フランス、イギリス、韓国といった多くの先進国では、芸術は創造的な経営モデルを必要とする分野と捉えられています。つまり、国家はもはや「指揮官」ではなく「環境の創造者」なのです。創造的な経営とは、アーティストの能力を信じ、実験を奨励し、法の枠組みの中で自由な空間を与えることを意味します。同時に、国家は芸術が健全かつ持続的に発展できるよう、財源、政策、技術を促進するという庇護的な役割も担います。このモデルの優れた点は、自由と責任、創造的な個人と社会共同体の間にバランスを生み出すことであり、これは行政による経営では実現できないことです。
振り返ってみると、イノベーションの兆しも数多く見られました。2022年の映画法、知的財産法の改正、中央決議、そして2025年から2035年までの国家文化発展目標計画などは、いずれも「クリエイティブマネジメント」の精神を実践するための道を切り開いています。
グローバル化とデジタル変革の時代において、旧来の経営理念はますますその欠陥を露呈しつつあります。歌がわずか数分でSNSで拡散し、映画、美術、演劇が国際市場に進出する今、行政による管理はもはや通用しません。現実が証明しているのは、経営思想が革新的であるところに芸術が栄えるということです。ハノイ、ホーチミン、ダナン、フエなどにおける音楽フェスティバル、現代美術展、インディペンデント映画、クリエイティブスペースの急速な発展は、その明確な証拠です。そこでは、若いアーティストたちはもはや「許可」を待つのではなく、自ら「機会を求め」、「国が資金を提供してくれる」のを待つのではなく、「スポンサーを募り」、「コミュニティの資金を集める」方法を知っています。彼らは経営に対立するのではなく、共に成長していくのです。
しかし、クリエイティブマネジメントモデルへの完全な転換には、多くの課題を乗り越えなければなりません。それは、一部のマネジメントスタッフの「支援・奨励」よりも「承認・禁止」に親しんでいる古い思考習慣、クリエイティブ経済、著作権、文化産業に関する理解と応用能力の限界、クリエイティブファンド、芸術支援機関、芸術振興センターといった仲介機関の不足です。そして何よりも、マネジメント機関とアーティストの間の調和は、文書で埋められるものではなく、対話、共有、そして共同行動によってのみ深められるものです。
准教授 ブイ・ホアイ・ソン博士
国会文化教育委員会常任委員
出典: https://www.sggp.org.vn/quan-tri-sang-tao-nghe-thuat-post822556.html


















































































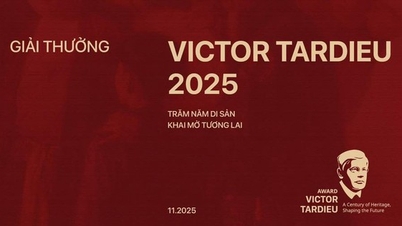




























コメント (0)