米国がインフレ抑制を目指している一方で、中国は逆の問題、つまりデフレに直面している。
2023年1月12日、アメリカ・ニューヨークの店舗で商品の価格が表示されている。写真:THX/TTXVN
米国の主要なインフレ指標である消費者物価指数(CPI)は7月に前年同月比3.2%上昇し、6月の3%から上昇し、最近の冷え込み傾向を打破した。米連邦準備制度理事会(FRB)は2022年初頭からインフレ抑制のため急速に貸出金利を引き上げてきた。先月の利上げにより、米国の金利は2001年以来の高水準に達した。
一方、中国国家統計局(NBS)は、7月の消費者物価指数(CPI)が2021年2月以来初めて下落し、生産者物価指数(PPI)は購買力の低迷により引き続き下落していることを示すデータを発表した。中国は正式にデフレに陥っており、政府は国内消費を刺激したいと考えている。
理論的には、価格が下がれば人々の購買力が増すため、デフレは良い傾向のように思えます。しかし、デフレは国の経済に悪影響を及ぼす可能性があります。まず、人々が来週や来月には商品の価格がさらに下がると信じれば、商品やサービスの購入をやめ、経済の生命線である消費者支出を圧迫する可能性がある。そうなれば、企業は人員削減や賃金削減、その他の調整を行うことで対応する可能性がある。
第二に、デフレは住宅ローンやその他のローンなどの負債を抱える個人や企業にとってマイナスのニュースです。それは、価格が下落しているにもかかわらず、債務の価値は変わらないため、消費者と企業に債務返済のために支出を削減する圧力がかかるからです。
デヴェレ・グループのナイジェル・グリーン氏は8月9日、中国のインフレは国外に広がる恐れがあるとの懸念を示した。
ブルームバーグによれば、中国がデフレに陥ると、多くの国の消費者は中国からより安い輸入品を購入できるようになる。しかし、多くの政府は、中国からの安価な輸出品によって、縮小しつつある対北京貿易赤字が反転することを望んでいないだろう。欧州連合(EU)の貿易担当事務総長は先週、中国に対し欧州からの輸入品の受け入れを増やすよう圧力をかける考えを示した。
そのため、たとえ中国のデフレが先進国の消費者を助けるとしても、 政治をより混乱させる可能性が高いとブルームバーグは主張している。
しかし、コンサルティング会社イースト・アジア・エコンのポール・ケイビー氏は「先進国では、中国からの安価な消費財は以前ほど人気がない」と述べた。
米国に関しては、米国の消費者物価指数は住宅、食料、エネルギー、医療費に大きく左右され、一般的に中国からの輸入に大きく依存していないため、中国のデフレが米国のインフレに与える影響は限定的である可能性が高い。
プラサド氏によると、中国のデフレが米国の内需に大きな影響を与えないと予想する理由は他にもあるという。近年、米国の中国からの輸入の割合は減少している。さらに、今年初めからメキシコは中国に代わって米国の最大の貿易相手国となり、4月時点で米国とメキシコの二国間貿易総額は2,630億ドルに達した。
世界経済が景気後退に陥るリスクがあり、債務問題が新興市場を悩ませていることから、世界の二大経済大国である北京とワシントンは長らく金融政策とマクロ経済政策の協調を強化するよう求められてきた。
二国間の緊張が続く中、インフレとデフレの乖離により、両国は議題において異なる優先順位を置かざるを得なくなる可能性がある。中国は、民間の製造業やビジネス部門が遅れをとっていたために不均衡になっていた国内経済を復興させ、技術革新を促進することに目を向けている。中国人民銀行は潤沢な市場流動性を維持しており、政策金利の引き下げには消極的だ。
米国側では、FRBは依然としてインフレ率を2%の目標まで引き下げようと積極的に取り組んでおり、その決定は国内銀行だけでなく新興市場にとっても試練となり続けている。
グエン・タン編纂
[広告2]
ソースリンク








![[写真] ト・ラム事務総長が南アフリカのアフリカ民族会議(ANC)第一副事務総長と会談](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/20/bb2999907e1245d5b4c7310a890d8201)




















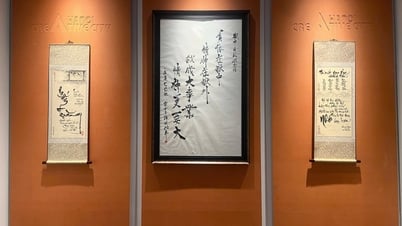
































































コメント (0)