
闇を抜けて「室内交響曲」
D. ショスタコーヴィチの音楽は、抑圧の闇と人間の意志の光、嘲笑的な態度と不屈の精神といった時代の矛盾を映し出す鏡であると言えるでしょう。
カール・ニールセンとドミトリ・ショスタコーヴィチという二人の作曲家を専門とする音楽研究者のデイヴィッド・ファニング教授は次のように述べている。「政府の要求による相反する圧力、ほとんどの同僚の忍耐、そして人類と公共に奉仕するという彼の個人的な考えの間で、彼は計り知れない感情の力を持つ音楽言語を作り出すことに成功した。」

ドミトリー・ショスタコーヴィチは1906年9月25日、サンクトペテルブルクの中流家庭に生まれました。化学者の父と才能あるピアニストの母を持つ家庭です。幼い頃からピアノに親しみ、作曲の世界に足を踏み入れ、第1回ショパンコンクールで2位を獲得。1926年に音楽院を卒業した直後に交響曲第1番を完成させ、革命後最初の才能ある作曲家として世間から歓迎されました。
ショスタコーヴィチは、革命の勝利によって育った世代の一員であると自覚し、常に自らが属する新時代のロマン主義に非常に本能的に共感していました。ソ連(旧)内外で数々の賞を受賞し、「20世紀で最も力強い音楽的声」の一人とされ、膨大な作曲遺産を残しました。

音楽監督オリヴィエ・オシャニーヌがコンサートで演奏するために選んだ室内交響曲(作品110a)は、悲しみに満ちた作品であり、音による自画像であり、ショスタコーヴィチ自身の痛みと極度の疲労の告白であり、病と孤独と苦悩を内に抱えた作品である。
ドミトリー・ショスタコーヴィチは54歳の時、第二次世界大戦の凄惨な惨状を描いた映画音楽の作曲のため、爆撃で荒廃したドレスデンを訪れたという逸話があります。しかし、当初の目的を無視し、彼は生涯で最も深く心に残る作品の一つ、「弦楽四重奏曲第8番ハ短調」を作曲しました。これは後にルドルフ・バルシャイによって弦楽のために編曲され、「室内交響曲 作品110a」となりました。

公式には「ファシズムと戦争の犠牲者」に捧げられているこの曲は、実際には作曲家自身への追悼曲である。彼のドイツ語のイニシャル(D. Sch)に由来するDSCH和音(D-E♭-C-Bの4音)が響き渡り、まるで各小節に刻まれた自我のコードのように、曲全体を通して繰り返される。
彼が「室内交響曲」に出演する際に作品のいくつかによく使っていた独特の署名は、メンバーそれぞれの個性を消し去ろうとするコミュニティの真っ只中で、「私はまだここにいる」という苦しい肯定として暗黙のうちに理解されていた。
聴衆は、混沌とした動きに満ちた作曲家の内なる世界を、暗く苦しい旅路を手探りで辿っているかのようだ。冒頭のラルゴの陰鬱さから、第2楽章アレグロ・モルトにおける戦争の恐怖を想起させる歪んだリズムと心に深く刻まれる反復まで。第3楽章の廃墟の中で幽霊が踊るような幽玄なワルツから、第4楽章の思慮深い葬送まで。そして、最終楽章の脆い静寂の中で、かすかな息づかいとともに終わる。それは、記憶、自我、そして各人の忍耐の限界を見つめる、悲しく哀愁に満ちた感情のようだ。

ホアンキエム劇場の観客のほとんどにとって、ショスタコーヴィチの内なる闇を探ることは容易な経験ではなかった。「室内交響曲」の憂鬱と混乱を通り抜けることは、作家の複雑な内面世界に触れる最も繊細な方法だった。そして、続く作品のまばゆい光に包まれ、その光が、たった今直面した暗い深淵と比べてどれほど美しいかを悟った時、人々は涙を流した。フランスの指揮者オリヴィエ・オシャニーヌが、ショスタコーヴィチの「語られざる物語」を、ピアノ、トランペット、弦楽のための協奏曲第1番という喜びに満ちた作品で締めくくったのも、おそらく同じ意図があったのだろう。
こうしてSSOは時を遡り、晩年のショスタコーヴィチの姿に出会う。彼は生命力と知性に満ち溢れながらも、奇妙な皮肉と奔放さを併せ持つ、若きショスタコーヴィチの姿である。ピアノ、トランペット、弦楽のための協奏曲第1番では、ピアノとトランペットは単なる楽器ではなく、理性と感情、恐怖と自由の間で論争する二つの声として聴こえる。トランペットは悲劇をからかい、傲慢に笑うかのようだ。一方、ピアノは涙を流しながらも、すべての人間への信頼に満ちた歌を歌い上げる。
そして「協奏曲第1番」で光を迎え入れましょう
ショスタコーヴィチの生涯、その思想、政治的見解、そして作品の一部は、生前、賛否両論の評価を受けました。しかし、彼が偉大な作曲家であったという事実は誰も否定できません。
多くの有名な批評家の目を通して、交響曲を見ると、叙事詩的な形式と力強いオーケストラ編曲において、ムソグルスキー、チャイコフスキー、そしてある程度はラフマニノフがショスタコーヴィチに与えた影響が見て取れます。
しかし、協奏曲、特にピアノ協奏曲においては、ショスタコーヴィチは偉大なロシアの模範から可能な限り遠ざかろうとしました。ショスタコーヴィチのピアノ協奏曲第1番を同時代の作曲家による類似の作品と比較すると、それらが同じジャンルに属するとは言い難いでしょう。

ラフマニノフ、チャイコフスキー、ブラームスがピアノ協奏曲をピアノ独奏による交響曲のようなものに拡張しようとしたのに対し、ショスタコーヴィチは作品をまったく新しい、風刺的で機知に富んだ、簡潔で美しいものに変えました。
ショスタコーヴィチは当初、レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団の首席トランペット奏者アレクサンダー・シュミットのためにトランペット協奏曲を作曲するつもりだったと言われているが、技術的な難しさを感じ、ピアノを加えて弦楽器のみのオーケストラによる2つの楽器のための協奏曲にすることを決めた。これはショスタコーヴィチにとっては非常に異例なことである。
この作品は、彼の音楽の珍しい側面も示しており、娯楽性、楽しさ、機知をもたらし、今日最も人気のある協奏曲の 1 つとなっています。
1933 年に作曲されたピアノ協奏曲第 1 番は、ショスタコーヴィチの最も華麗かつ大胆な作品の 1 つであり、若々しい精神、鋭い機知、そして予期せぬ深遠な美しさが織り交ぜられた風刺的な協奏曲です。
ピアノ、トランペット、弦楽器のために書かれたこの作品は、ほぼ二重協奏曲と言えるでしょう。トランペットは解説者、道化師、挑発者といった役割を演じ、ピアノと機知に富み意外性のあるやり取りを繰り広げます。この作品の推進力と遊び心に満ちたエネルギーは、名演奏家であると同時に、いたずら好きな風刺作家でもあった若きショスタコーヴィチの才能を反映しています。
この作品の4つの楽章は、様式と感情の旋風です。第1楽章の遊び心のあるファンファーレと鋭い2つの楽器の掛け合いから、第2楽章の温かく繊細なピアノの音色へと移り変わります。そして、第3楽章では、短く神秘的な休止が2つの世界を壮麗なハーモニーで際立たせ、最終楽章では皮肉な笑いといたずらっぽいウインクで締めくくられます。
この協奏曲を首都で演奏する役割を担うのは、ピアノソリストのルー・ドゥック・アンとトランペットソリストの山野井大樹の二人です。ベトナムを代表するピアニストの一人であるルー・ドゥック・アンは、名門音楽学校を卒業し、国内外で数々の賞を受賞し、名門オーケストラに出演し、権威あるコンクールの審査員も務めるなど、輝かしい実績を誇ります。
「協奏曲第1番」は、この愛すべき顔の演奏技術と感情の深さにより、聴衆の心に触れました。

彼の傍らでは、サン交響楽団アソシエイトトランペット奏者の山野井大樹がパートナー兼ジャグラーとして、それぞれの音楽の対話にウィットと叙情性を織り交ぜています。
これらはすべて、ショスタコーヴィチの逆説的な世界、つまり笑いが絶望と手を取り合い、風刺が作者のメッセージの最も真実な表現となる世界を照らし出します。
ショスタコーヴィチ ― 秘められた物語 コンサートは、「ミハイル・グリンカのワルツ幻想曲」で幕を開けました。夢の舞踏、澄み切った、ロマンティックで、息吹のように軽やかな空間。ロシア音楽のパイオニアであるグリンカは、優しく繊細な美しさで夜の礎を築き、ショスタコーヴィチの音楽世界は、歴史の重みにその夢の脆さを露わにしました。二人の作曲家は、異なる時代に、ワルツを人間の生命の象徴へと昇華させました。優雅で心に深く刻まれると同時に、不屈の精神と生命力に満ちた力強さも持ち合わせています。
出典: https://nhandan.vn/bang-qua-bong-toi-de-don-chao-anh-sang-post923587.html






















































































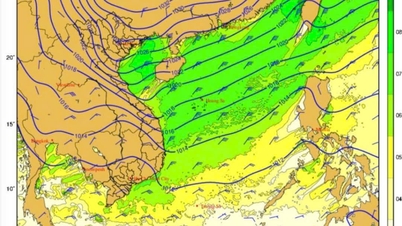

















コメント (0)