このフォーラムは、ラオドン新聞が主催し、「人材と雇用主をつなぐ」プログラム「ジョブリンク2025」の一環として開催された。
労働問題と「貧乏老齢」の課題
内務省ホーチミン市代表事務所のファム・アン・タン副所長によると、今年第3四半期末現在、ベトナムの労働年齢人口は5,340万人で、学位・資格保有者は29.3%に達し、同時期比0.4ポイント増加した。しかし、労働市場への新規参入者は急速に減少している。15年前は毎年110万人が労働市場に参入していたが、現在は約50万人にとどまっている。
タン氏は、適切な人材育成戦略がなければ、ベトナムは「まだ豊かではないが、既に高齢化している」状況に陥る可能性があると警告した。つまり、労働者が退職年齢を迎える前に十分なスキルを習得していない状態だ。「現在、労働者が不足しているのではなく、深い専門知識を持つ人材が不足している。特に、デジタル変革の過程において、公共部門には依然として情報技術に精通した人材が不足している」とタン氏は述べた。
この問題を解決するために、タン氏は次のような解決策を提案しました。企業(雇用主)は研修の目標を設定し、研修プロセスに直接参加し、各企業を研修機関として、単位が必要とする適切な業界と職業、労働市場が必要とする適切な研修を結び付け、研修機関に「正しく研修する、正確に研修する」ように指示し、設備や機械に投資してリソースの無駄を避ける必要があります。なぜなら、過去には多くの企業が頻繁に再研修を行う必要があり、非常に無駄が多かったからです。

企業は、無駄を生じさせる再訓練を避けるために、学校と協力し、訓練を行っています。
写真:イェン・ティ
ホーチミン市内務省副局長のルオン・ティ・トイ氏は、2025年から2030年にかけて、ベトナムの労働市場はデジタル経済、自動化、グリーン化、再生可能エネルギー、効率的な物流といった方向へと発展していくと認識した。これにより多くの新たな雇用機会が創出される一方で、労働者の専門知識、スキル、そして適応力に対する高い要求も高まるだろう。
合併後、人口約1,400万人を擁する「スーパーシティ」となったホーチミン市だけでも、2025年の最初の10ヶ月間で14万人の求職者と25万人の求人が記録され、前年同期比で大幅に増加しました。しかし、ホーチミン市は「未熟練労働力の過剰と質の高い労働力の不足」という矛盾にも直面しています。これは長年の課題であり、人材育成を促進するための解決策が求められています。
戸井氏は「市は人材育成を中心的な課題と位置づけており、人への投資が最も利益のある投資である」と強調した。

企業は研修施設に「正しく、正確に研修する」よう指示できる
写真:イェン・ティ
「どの業界でも仕事はある。チャンスは50/50だ」
フォーラムで、グエン・ティ・ヴィエット・トゥ師は、入学相談の際に、トゥ師は学生になぜその専攻を選んだのかをよく尋ねたと述べました。多くの学生は、家族の勧めでその専攻を選んだ、親戚がその分野で働いている、友人が同じ専攻を選んだなどと答えました。中には、「美人が多い」「卒業生の就職率が98%に達し、給与が最も高いグループに属している」といった理由だけでその学校を選んだ学生もいました。しかし、「どんな専攻を学びたいですか?」と聞かれると、「どんな専攻でも構いません」と答えました。
多くの学生は入学後に初めて自分の専攻が自分に合っていないことに気づきます。これは、学校が提供する人材の質に大きな影響を与えます。情熱を持って学ぶとき、その愛情は、何らかの理由で誰かのために学ぶときとは全く異なります。
親や学生からよく聞かれる質問は、「卒業後に就職するには、何を専攻すればいいですか?」です。
杜先生によると、これは非常にシンプルな質問で、どの業界にも仕事はあるということです。研修ユニットが特定の業界で研修を行うには、その業界が社会的に需要がある必要があります。多くの学校は「卒業生の就職率100%」と宣伝していますが、実際には、家族、学校、企業から学生に与えられる機会は50%で、残りの50%は学生自身の努力にかかっています。
三者連携を強化するソリューション
フォーラムでは、人材の質を向上させるためには、国家、学校、企業の連携を強化する必要があるということで専門家らが一致した。
グエン・ティ・ヴィエット・トゥ師は、研修機関が企業と協力するのは非常に困難であり、すべての企業が研修において学校との協力を望んでいるわけではないと率直に述べた。そのため、トゥ師は、企業に営業許可を与える際には、人材育成への貢献度に関する基準を設けるべきだと提案した。「企業は利益に加えて、社会的な責任を負わなければなりません。学校と協力して、国のために質の高い人材を育成していくのです」とトゥ師は付け加えた。
ホーチミン市農林大学の副学長、トラン・ディン・リー博士は、学校と企業は単に「握手する」のではなく、具体的な行動を伴ってしっかりと「握手」する必要があると考えています。学生は「どんな仕事に就けるか」ではなく、「何に貢献できるか」を自問すべきです。自分の未来は自分で切り開くという意識を持って、企業に働きかけてください。
ホーチミン市国家大学研修部副部長のドゥオン・トン・タイ・ドゥオン博士も同様の見解を示し、今日の人材育成は新たな文脈に位置付けられるべきだと述べた。研修は現実から切り離すことはできず、スキル、応用能力、そして継続的な適応力の形成と密接に結びついていなければならない。研修の目標は「共創」の方向に向けて構築される必要がある。つまり、学校、企業、そして政府は、プログラムの構築、研修、そして成果の評価というプロセスの初期段階から参加し、研修と雇用のエコシステムを形成する必要があるのだ。
グッド・ジョブズの営業部長、トラン・キム・トラン氏は、採用動向が急速に変化していると述べた。「企業はもはや『どんな資格を持っているか』ではなく、『何ができるか』、『新しいことを学ぶ能力はどれくらいあるか』、『仕事の変化にどれくらい適応できるか』を問うています」とトラン氏は述べた。
自学自習能力と学習能力は非常に重要であり、現代の労働者にとって生き残るためのスキルです。さらに、学生はコミュニケーション能力を養い、仕事におけるテクノロジーの活用や外国語の習得などに加え、プロフェッショナルな就労姿勢、責任感、迅速な適応能力などを維持し、構築し続けることで、労働市場における競争力を高める必要があります。
出典: https://thanhnien.vn/phu-huynh-hoc-sinh-hoi-hoc-nganh-gi-ra-truong-co-viec-lam-chuyen-gia-tra-loi-185251109155837243.htm






















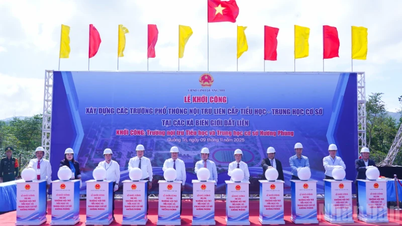

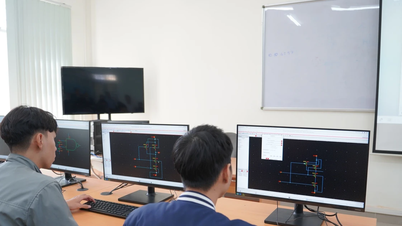

























































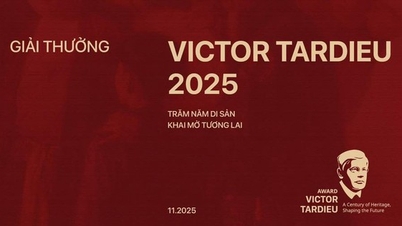




























コメント (0)