長期的なビジョンを持った戦略を実行することにより、ベトナムの高等教育は力強い変革を遂げ、深く統合し、国際競争力を高めることができます。
レ・ドン・フォン博士 - 高等教育研究センター(ベトナム教育科学アカデミー)元所長:古い価値観を守り、新しい価値観を創造する。

高等教育の再編は、単なる組織合併ではありません。より根本的には、大学の経営理念と教育使命の包括的な改革です。外部の経営管理者の視点から見ると、これは経営層や関係者がシステム内の構造変化をどのように認識しているかを示しています。関係者にとっては、これは旧教育機関の合併によって形成された新たな組織における教職員の配置転換と再編成のプロセスです。
最も重要なのは、高等教育機関における経営とガバナンスの考え方を改め、変化に適応しやすいリーンな運営モデルを構築することです。そのためには、古い習慣や慣習を克服する勇気が必要であり、それは決して容易なことではありません。
さらに、新しい教育機関の独自のアイデンティティを確立することも重要です。これは、労働市場のニーズと学習者の期待に応える研修プログラムの編成と調整を通じて示され、学生と利害関係者の権利が常に優先されることが保証されます。
複数の高等教育機関を新たな組織に統合することは、組織モデルや運営方法に関して必然的に課題を生じさせます。このモデルは外部から押し付けられることもあれば、内部主導で構築されることもありますが、いずれにせよ、異なる利害関係者間の対立が生じる可能性があります。移行期間中は、多くの加盟組織で人員の過剰が発生し、煩雑な組織構造となることがよくあります。
したがって、最も重要なのは、発展の道筋について合意に達し、各方面の利益を調和させるための具体的な措置を講じることです。再編プロセスは、合意と連帯の精神に基づき、共通の目標を個々の利益よりも優先させる必要があります。各ステップは慎重に検討され、十分な根拠に基づき、多段階にわたる議論が行われ、「衝動的にやる」という思考は絶対に避けなければなりません。
再編は必ずしもベトナムの高等教育に即座の飛躍をもたらすとは限らない。なぜなら、教育機関は、その歴史、学術的伝統、そして学生やパートナーとの強固な関係に基づいて初めて持続的に発展できるからだ。過剰な大学統合は、蓄積された価値の喪失につながる可能性があり、必ずしもより良い新たな価値を生み出すとは限らない。
リーダーの期待を現実のものとするには、学校は中核となる使命と長期的なビジョンを明確に定義する必要があります。なぜなら、その使命を他の学校にそのまま当てはめることはできないからです。前提条件として、あらゆるレベルの管理職と研修機関が自らの強みと弱みを認識し、州の管理機関にその本質的な価値を納得させる機会を持つことが重要です。
これに基づき、政府はベトナムの高等教育システムの包括的な再編計画、すなわち社会のビジョン、価値観、そして期待を反映した新たなマスタープランを策定することができる。この計画においては、大学が本来の価値を最大限に発揮できるよう再編され、同時に新たな価値観の形成の基盤が構築される必要がある。特に、経済効率のみに焦点を当てるのではなく、各高等教育機関が地域の社会経済発展にどの程度貢献しているかを優先基準とすべきである。
制度レベルでは、それぞれの研修プログラムや教育機関の特性を考慮した再構築が必要です。応用研修プログラムは、社会経済発展に貢献できるよう、より強力に展開する必要があります。一方、研究志向のプログラムは、単なる技能訓練ではなく、新たな科学的知識の創造を目指し、学部や学科の科学技術活動と連携させる必要があります。
このプロセスを成功させるには、資源状況が確保され、継続的に維持される必要がある。既存の資源は急激に削減されるべきではなく、運用上の混乱を回避するために適切に調整されるべきである。同時に、決議71で特定された新たな資源は、目に見える成果を生み出すのに十分な規模で提供される必要がある。
ホアン・ゴック・ヴィン博士 - 元教育訓練省職業教育局長: 「要請と付与」の仕組みや過度に官僚的な管理に陥らないようにする。

高等教育機関の再編・統合は、学術文化、専門分野、運営体制の違いが依然として大きいまま、単なる「機械的な学部追加」に終わるのではないかと懸念する声が多い。この懸念は当然と言える。名称を単に組み合わせ、機械的に統合するだけにとどまるのであれば、このプロセスは確実に失敗するだろう。
再編を成功させるには、高等教育機関をその使命と任務に応じて階層化すること、すなわち、基礎科学に重点を置く一流の研究大学、企業や地域のニーズに密接に結びついた応用大学、そして教育分野の人材育成を担う教員養成大学に階層化することが不可欠です。
この階層構造の中で、各校はパートナーとリソースを共有しながら、それぞれの強みを活かしていく必要があります。その核となる要素は、明確なガバナンスモデル、高い説明責任、そして単なる「名称変更」ではなく、実質的な変化を生み出すための十分な投資です。
合併後のガバナンスモデルと自治メカニズムも重要です。大学評議会の廃止を背景に、高等教育機関を地方自治体の管理下に置くという提案も出ています。しかし、行政管理と大学運営は文化が異なります。大学を行政単位として扱うことは、「要請・助成」精神、煩雑な手続き、そして創造性と自治の喪失につながりやすいのです。
確固たる基盤がなければ、自治は行政権力によって容易に影を落とされ、教育の質と予算の効率的な運用について学校に説明責任を負わせる仕組みも欠如する。したがって、運営を「現地化」するのではなく、企業やステークホルダーの参加を得た独立した学術評議会を設立する必要がある。このモデルは、学術の自治を維持し、学校と労働市場のより緊密な連携を促進し、透明性と明確な説明責任を確保することにつながる。
再編・統合の対象となる大学の選定基準も、教育訓練省が定める最低基準を超え、客観的、公開的、かつ透明性のある形で策定される必要がある。評価は、学術的能力、教員、施設、学生の就職実績、財政的自立性など、多面的な視点から行われるべきである。
特に、研修が地域・地方の経済発展とイノベーションに必要な人材ニーズをどの程度満たしているかが、中心的な指標となるべきである。研修が地域開発戦略と連携していなければ、たとえ基準を満たしていたとしても、場違いなものとなってしまう。
明確で透明性のある基準は、適切な人材の配置に役立つだけでなく、社会的な合意を形成し、教職員や学生の否定的な反応や不満を軽減します。透明性のあるプロセスと持続可能な開発への重点を目にすることで、単なる行政上の決定として捉えるのではなく、信頼を築くことができます。
ベトナム大学協会副会長、レ・ヴィエット・クエン博士:強力な大学システムが必要です。

21世紀の最初の20年間で、高等教育は多くの国の開発戦略の中核を成すようになりました。世界的な視点から見ると、高等教育の運営と改革には3つの大きな潮流が強く影響しています。それは、大学の学際性、多部門性、多機能化、合併や提携によるシステムの中央集権化と再編、そして社会的な説明責任を伴う自治権の強化です。
ヨーロッパでは、ボローニャ・プロセスによって高等教育の統合空間が創出され、大学は教育モデル、ガバナンス構造、そして開発戦略の調整を迫られました。フランス、ドイツ、オランダをはじめとする多くの国では、小規模大学や分散していた大学を統合し、国際競争力のある学際的な大学を形成しました。
アジアでは、韓国、中国、シンガポールも大規模な改革を進めてきました。中国は1990年代後半から大学合併を次々と実施し、数万人規模の学生を抱える大学を創設し、教育、研究、イノベーションを密接に統合してきました。シンガポールは、大学数を絞り込み、より国際志向の大学を創設するという合理化されたモデルを採用しており、これも再編と合併の成果です。
したがって、ベトナムはこうした潮流から逃れることはできません。分断され、分散した高等教育システムでは、統合を進め、国際ランキングで上位を獲得することは困難です。私たちは、科学技術とイノベーションを基盤とした知識基盤型経済へと成長モデルを転換する必要に直面しています。2045年までに高所得先進国となるという目標を達成するためには、ベトナムには質の高い人材を育成し、新たな知識を生み出すことができる強力な大学システムが必要です。
このような状況において、断片的で非効率的なシステムを維持することは、無駄を生むだけでなく、国の発展を阻害することになります。大学を統合し、学際的な研究・教育機能を備えた大規模で多分野にわたる大学を形成することは、戦略的な解決策です。これは教育上の要請であるだけでなく、国の将来に関わる政治的決断でもあります。
合併プロセスが社会に混乱や否定的な反応を引き起こす機械的な「官僚化」にならないようにするためには、基本原則を確立することに加え、持続可能な学際的な大学を形成するための厳格で科学的な基準に基づいて合併を行う必要があります。
地理的に:共有インフラストラクチャを活用して管理コストを削減するために、同じ地域 (市、州) 内にある学校を優先します。学生と教職員に困難をもたらす、遠く離れた学校の統合は避けます。
養成分野について:補完的な専攻を持つ学校が合併すると、学際的な大学が誕生します。専攻が重複する学校間の機械的な合併は、容易に衝突や人員過剰につながる可能性があるため、避けてください。
研究・研修能力に関して:同様の使命を持ちながらも強みが異なる大学(例えば、工学に強い大学と、経済学や社会科学に強い大学)を統合し、学際的な大学を創設することで、国内外の研究への参加を容易にするべきである。
規模と運営効率について:小規模校(生徒数3,000人未満)は合併を検討すべきであり、効率性が低く質の低い学校も合併計画に含めるべきである。
国家戦略に関して:経済、政治、社会の中心地(ハノイ、ホーチミン市、フエ、ダナン)に、地域レベルおよび国際レベルの研究大学を設立することを優先すべきである。各経済地域には、地域の人材ニーズと国際統合の両方に対応できる十分な規模の学際的な大学が少なくとも1つ存在すべきである。
さらに、各州には、直接的な労働力のニーズを満たすと同時に、その地域の教育の全体的なレベルを向上させる、合理的な規模の「コミュニティ大学」タイプの多分野にわたる多段階の大学が少なくとも 1 つ必要です。
考えられる合併モデル:
完全合併:学校はリストから外され、まったく異なる名前の新しい大学に統合され、新しい組織が設立され、現代的なガバナンスのメカニズムが設計されます。欠点は、抵抗が起こりやすく、伝統的なアイデンティティが失われる可能性があることです。
連合型連携:各校は個別の名称を保持しつつ、より大規模な大学(国立大学、地域大学モデル)に加盟する。これは各校のアイデンティティを維持し、社会的にも容認されやすいが、地域主義や統治における統一性の欠如につながる可能性がある。
ハイブリッド モデル:一部の学校は完全に合併し、他の学校は連合を形成します。柔軟性があり、混乱は軽減されますが、ガバナンスが複雑になり、重複する可能性があります。
学校クラスター:異なるレベルの教育や名声を提供する個々の教育機関が、同じ「ゲームのルール」に同意してクラスターを形成します。これは 1993 年以来教育訓練省によって推奨されていますが、これを採用している学校はほとんどありません。
合併後のガバナンス体制については、どのようなガバナンスモデルを適用するかが重要な課題となる。現状の欠陥から教訓を学び、大学評議会に代わるメカニズムを構築する必要がある。国際的な経験によれば、大規模で学際的な大学には、大学評議会が決定的な戦略的役割を果たす、専門的なガバナンス体制が必要である。大学評議会廃止の流れが続く場合、国は合併後に設立される大学に対し、新たなガバナンス体制を速やかに導入する必要がある。
合併後、学長は学者でなければなりません。学長は政治的立場だけでなく、大学運営能力と学術的知識を備えている必要があります。さらに、明確な階層構造が必要です。合併後の大学は、中央レベル(大学)とその構成単位(附属学校)の間に階層構造を持ち、「権力の重複」を避けるべきです。 - レ・ヴィエット・クエン博士
出典: https://giaoducthoidai.vn/tai-cau-truc-truong-dai-hoc-cong-lap-buoc-ngoat-chien-luoc-post753945.html




![[画像] ミーソン聖域で新たに発見された「聖なる道」のクローズアップ](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F13%2F1765587881240_ndo_br_ms5-jpg.webp&w=3840&q=75)



















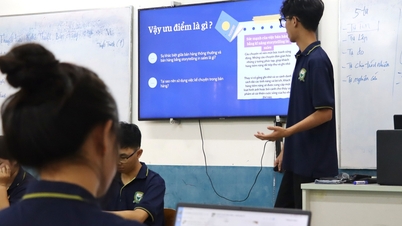




















































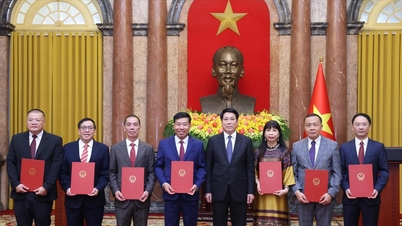



































コメント (0)