興味深いのは、南部のもち米の餅が近隣諸国のものと非常によく似ていることです。
ベトナム文化において、もち米で作られたケーキは非常に馴染み深いものです。中でも最も有名なのはバインチュンとバインテットですが、他にも実に様々な種類のケーキがあります。しかし、バインネップは東アジア地域に広く見られる文化的な特徴であり、どの地域でも非常によく似たケーキであることを知っている人は多くありません。

ココナッツの葉のケーキ。
ベトナムで人気のもち米の餅3種類、すなわちバインチュン、バインテット、バインウーは、中国でも入手可能です。中国文化圏では、もち米の餅は一般的にソン(粽)またはソントゥ(粽)と呼ばれます。しかし、この名前の最も一般的な意味はバインウーを指します。さらに、区別するために、それぞれの餅には形状に応じた独自の名前が付けられています。
バインチュンは方粽(フォントン)と呼ばれ、「フォン」は四角を意味するため、「フォントン」は四角い餅を意味します。このタイプの餅は古代白越文化に由来すると考えられています。現在中国では、バインチュンは過去に白越文化の影響を受けた一部の地域や民族でのみ見られます。また、バインチュンはベトナム文化の典型的な餅であるため、中国人はこれをベトナム・フォントンとも呼びます。
この餅は「角粽(ぎゃっとう)」と呼ばれています。「角」は角を意味し、この餅の角が鋭いことからそう呼ばれています。また、「角黍(ぎゃっとう)」という別名もありますが、意味は少し異なります。「角」は角、「沽」はもち米を意味し、つまり「角の形をした餅」という意味です。中国の民間伝承によると、修行によって神となった動物が「淑貂(ぎゃっとう)」という名で、水中に住む一角のヤギ(ユニコーンヤギ)です。端午の節句に淑貂神を祀るためにこの餅がよく使われることから、人々は角の形に作って「淑貂」と呼ぶようになったのでしょう。
バイン・テットは、胴体が長く筒状に見えることから、「長粽(チュオン・トン)」(「チュオン」は長いという意味)または「筒粽(ドン・トン)」(「ドン」は筒という意味)と呼ばれます。多くのベトナムの研究者は、南部のバイン・テットは北部のバイン・チュンの変種だと説明しています。ベトナム人がシヴァ神を崇拝するチャンパ文化と接触したため、バイン・チュンがシヴァ神の象徴であるリンガを象徴する丸い形に変化したという説さえあります。しかし、バイン・テットがベトナムだけに限ったものではないため、これらの説は説得力を失います。

ケーキテスト。
旧正月にもち米の餅を食べるベトナム人とは異なり、中国人は主に端午の節句(ドラゴンボートフェスティバル)にもち米の餅を食べます。
カオ・トム・マット、またはカオ・トムは、タイとラオスで人気のケーキです。このケーキの特徴は、バナナの葉で包まれた厚いもち米です。もち米には少量の黒豆が混ぜられることもあります。餡は通常バナナですが、インゲン豆、タロイモ、豚肉などに変わることもあります。包む際には、2つのケーキを結び合わせてペアにします。
そのため、カオ・トム・マットは仏塔の国タイのカップルにとって象徴的なケーキです。タイの人々は、僧侶たちが3ヶ月間の雨季の修行を始める際に、カップルが僧侶にカオ・トム・マットを捧げると、永遠の愛が訪れると信じています。
カオ・トム・マットは、タイの太陰暦12月15日に行われるマハチャト祭とも関連があります。仏教の伝説によると、この日は釈迦牟尼仏の先祖であるヴェッサンタラ王子の誕生日です。彼は深い慈悲の心を持ち、持てるすべてを惜しみなく与えました。そのため、この祭りはタイを含む上座部仏教の伝統を重んじる国々では、慈善行事とされています。
クトゥパットは、マレーシア、インドネシア、シンガポール、ブルネイ、フィリピンなどの東南アジアの島嶼国で非常に有名な餅です。この餅の主な材料は、セイヨウトチノキの実から作った水に浸した米またはもち米です。餅は、菱形に編み込まれた葉で包まれています。また、もち米に少量の黒豆やインゲン豆を混ぜることもあります。
このケーキの形には、様々な興味深い解釈があります。外側に編み込まれた葉っぱは人間の過ちを、内側の白いもち米は清められた魂を象徴すると信じる人もいます。また、外側に巻かれた葉っぱには厄除けの力があり、内側のもち米は豊かさと幸福を象徴しているため、家の前に飾ると悪霊を追い払うことができると説明する人もいます。
毎年イスラム暦の10月初旬、 世界中のイスラム教徒は断食月ラマダンの終了を祝うイード・アル=フィトルの祭りを祝います。東南アジアの島嶼国では、この重要な祭りを祝うために、イスラム教徒が大量のケトゥパット(お菓子)を用意します。
興味深いことに、ベトナム南部には近隣諸国の餅とよく似た餅があります。バインキャップはバインテットに似たタイプの餅ですが、胴体は平らで短く、中身は通常バナナか豆です。それぞれの餅には2つの側面があり、1つは平らでもう1つは曲がっています。包んだ後、2つの餅を結び、2つの平らな側面を押し合わせ、2つの曲がった側面を外側にします。「キャップ」という言葉は、互いに結びついて対になることを意味します。バインキャップは、タイのバインカオトムマットに似ています。
ココナッツリーフケーキは、もち米に少量の豆(通常はバナナ)を混ぜて作られます。ケーキは長方形で、両端が平らで、ケーキの胴体部分はココナッツの葉で包まれています。ココナッツリーフケーキは、東南アジアの島国で食べられるクトゥパットケーキに似ていることが分かります。
南部クメール人は、 アンザン省で人気のカトゥムまたはカトムケーキを食べて育ちます。これはクトゥパットケーキに似ています。カトゥムケーキは、もち米に少量の豆を混ぜて作られています。外側はヤシの葉を編み合わせて包み、その上に花びらを乗せています。全体的にはザクロの実のような形をしていますが、形は四角いです。
バイン・バー・チャンは、ベトナム語で中華風もち米の餅を意味します。元々は「ヌック・トン」と呼ばれ、肉入りもち米の餅のことです。「ヌック」は肉、「トン」はもち米を意味します。南西部の華人は主に潮州方言に属しているため、「ヌック・トン」は「バ・ツァン」と発音します。ベトナム人はこれを「バ・トラン」と誤って発音します。

カトゥムケーキ。
チャヴィン省には、三色のもち米が特徴のチャクオン餅という名物があります。これまで、ほとんどの研究者はこの料理はクメール文化に由来すると信じていました。しかし、中国にも全く似た餅があることから、中国文化に由来する可能性が高いです。一方、このタイプの餅には塩卵が使われていることに注意する必要があります。これはベトナム料理やクメール料理ではほとんど見られない食材ですが、中華料理では非常に人気があります。塩卵は多くの中華料理、特に餃子、ピアケーキ、月餅などに使われています。チャヴィン省、ソクチャン省、バクリエウ省は、潮州族の華人が多く住む3つの省です。彼らがこの三色のもち米餅を中国からベトナムに持ち込み、それがクメール人とベトナム人に取り入れられた可能性があります。
[広告2]
ソース



![[写真] ダナン:数百人が嵐13号後の重要な観光ルートの清掃に協力](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/07/1762491638903_image-3-1353-jpg.webp)


































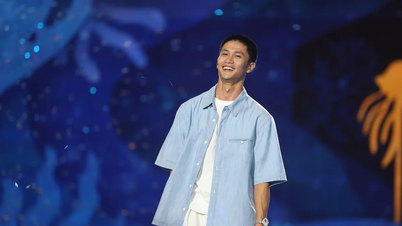

































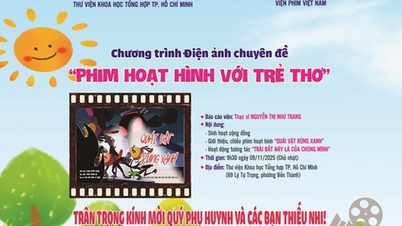





























コメント (0)