最近、地元警察は「オンライン誘拐」の多発事件を取り締まっています。被害者は電話やインターネットを通じて、直接会うことなく悪意のある人物に操られ、孤立や脅迫に陥ります。この新しい形態の犯罪は、ますます巧妙化し、危険度を増しています。
 |
| メディアは、被害者に罪悪感を抱かせるのではなく、被害者が自らの体験を共有することが、自分自身と地域社会を守る道であることを理解できるよう支援する必要がある。(イラスト写真) |
なぜ若者は「バーチャル」の罠に陥りやすいのか?
注目すべきは、悪者が若者、主に学生をターゲットにしていることです。
彼らはテクノロジーの使用には熟練していますが、社会的交流の欠如、人生経験の少なさ、批判的思考力、リスク識別力、好奇心、 探究心、法律に関する知識の不足により、脅迫の電話を受けると簡単に混乱状態に陥り、平静さを失ってしまいます。
上記の理由に加えて、心理的な観点から見ると、都市部の学生、特に他地方から大都市に留学に来る学生は、勉強、試験、生活費、アルバイト、恋愛など、多くのプレッシャーに同時に直面することがよくあります。
つまり、プレッシャーが蓄積されると、精神的に弱くなることが多いということです。予期せぬ状況(例えば、親戚が困っている、うっかり違法行為に加担したとして捜査を受けているなど)に遭遇すると、自然とパニックに陥り、詐欺師の指示に簡単に従ってしまうのです。
犯罪者は若者のこの心理的メカニズムを理解しているため、常に緊急事態のシナリオを作り出して、被害者の不安や感情的な心理を直接攻撃します。
「ネット誘拐」事件の複雑な展開に直面し、メディアは警告記事を継続的に発表し、個々の事件の報道にとどまらず、悪質な行為者の詐欺の仕組みを解説することで、一般市民、学生、保護者に明確な理解を促しました。
そこから、技術的な罠を見分けるスキル、情報確認スキル、家族との安全なコミュニケーションチャネル、疑わしい兆候があったときにすぐに警察に通報する方法などを身に付けましょう。
責任あるメディア
一連のセキュリティ警告に対し、学生が「ネット上で誘拐される」ことは容認できないとする意見がソーシャルネットワーク上に現れた。
これらの意見は、「『オンラインで誘拐』される学生は非常に非難されるべきであり、非常に恥ずべきことであり、若者である価値がない」、「親に負担をかけ、当局の時間を無駄にしている」、「これらの学生の弱さは、犯罪者が繁栄するための肥沃な環境を作り出している」と述べています。
こうした流れは、やや極端な文体とやや厳しい視点で、問題の原因を説明し、その解決策を提示し、悪質な対象者への厳正な対応を求めるのではなく、むしろ被害者を非難する方向に世論を誘導しているように見受けられる。
このようなコミュニケーション方法は良くなく、逆効果になる可能性があります。被害者を責めたり、責任を押し付けたりするのは適切ではありません。
「ネット上で誘拐」される学生は、知能が低いから、あるいは無責任だから誘拐されるのではなく、犯罪者が人々の心理的な弱点を突く方法を知っており、常に進化し続ける極めて高度な技術的トリックを使用するから誘拐されるのです。
実際、大人やビジネスマン、学者など、若者よりも人生経験豊富な人が被害者となる詐欺事件は少なくありません。
一方で、被害者を「非難されるべき、恥ずべき存在」とレッテルを貼ってしまうと、意図せずして被害者を犯罪者扱いしてしまい、嘲笑や非難を恐れて情報を共有したり、隠したりすることを躊躇するようになります。これは、犯罪者が活動を続けるための条件をさらに作り出すことになります。
何よりも、メディアは非難の文化にノーと言い、被害者を侮辱するようなコンテンツを宣伝すべきではない。
メディアは、若者が経験を共有し、互いに警告し合うよう促し、若者の警戒心を高めるよう警告し、同時に、子供が家から離れて勉強している場合には親同士が定期的に連絡を取り、話し合うよう提案する、橋渡し役としての使命を担わなければなりません。
メディアは被害者に罪悪感を抱かせるのではなく、被害者が自らの体験を共有することが、自らを守り、地域社会を守る方法であり、家族、学校、そして社会が常に傍らにいることを理解できるよう支援する必要があります。これこそが、デジタル社会における責任あるジャーナリズムとメディア教育の正しい精神です。
出典: https://baoquocte.vn/dung-truyen-thong-kieu-do-loi-hay-canh-bao-va-dong-hanh-330324.html






![[写真] カットバ島 - 緑の楽園の島](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F04%2F1764821844074_ndo_br_1-dcbthienduongxanh638-jpg.webp&w=3840&q=75)
































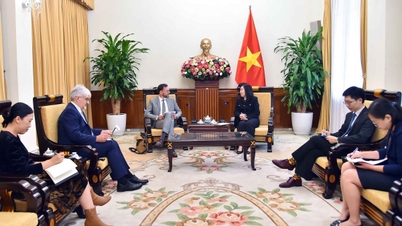









































































コメント (0)