現行の規定によれば、2014年社会保険法第58条では、退職時に年金率75%に相当する年数を超える強制社会保険納付期間を有する従業員は、年金に加えて一時金も受け取る権利があるとされている。
一時金は、年金率75%に相当する年数を超える社会保険料納付年数に基づいて算定されます。社会保険料納付年数1年につき、社会保険料として平均給与の0.5か月分が支給されます。
任意の社会保険加入者については、2014年社会保険法第75条に次のように規定されています。社会保険の納付期間が年金率75%に相当する年数よりも長い従業員は、退職時に年金に加えて一時金も受け取ります。
一時金は、年金率75%相当年数を超える社会保険料納付年数に基づいて算定されます。社会保険料納付年数1年につき、社会保険料納付額の平均月収の0.5ヶ月分が支給されます。

社会保険料の納付額が、端数月を含む年金率75%に相当する年数を超える場合、以下のように計算されます。1~6か月は半年として計算され、7~11か月は1年として計算されます。
2024年社会保険法では、現行社会保険法と比較して、法律で定める定年退職年齢に達した時点から退職時までの期間において、給与の75%に達する年数を超えて給与を支払っている人について変更があります。
2024年社会保険法第68条により、退職一時金の受給要件が変更されました。これにより、社会保険の納付期間が35年以上の男性労働者、および納付期間が30年以上の女性労働者は、退職時に年金に加えて一時金を受給できるようになります。
上記期間を超える各納付年数に対する一時金の額は、定年年齢を超える各納付年数に対する社会保険料の支給の基礎となる平均給与額の0.5倍に相当します。
年金受給資格者でありながら社会保険料を納付し続けている場合、法定退職年齢に達した時点から退職時までの最長納付年数(75%)を超える納付年数ごとに、社会保険料納付の基礎となる平均給与の2倍に相当する金額が支給されます。
以前、社会保険法改正案を審議した際に、最長年金加入期間(75%)を超えて納付した人への補助額を引き上げるべきだという意見が多くありました。
[広告2]
出典: https://vietnamnet.vn/nguoi-lao-dong-ve-huu-duoc-nhan-tro-cap-mot-lan-2308535.html














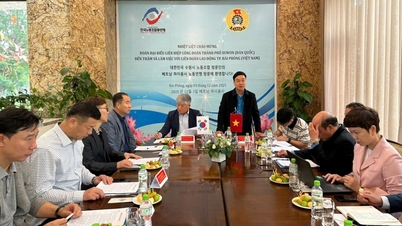






















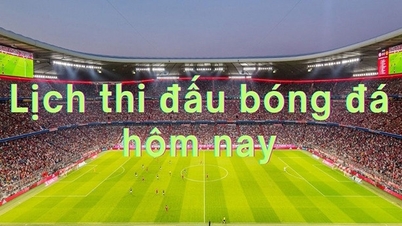













































































コメント (0)